��23�� �勳���w���ꋳ��w��\�����i����20�N�W��23���j
���w�I�F������ލ��ꋳ��̌����@ �|���̑����猻���i���ȁj�����߂�| |
�͂��߂�
�@�����Q�O�N�R���Q�W���Ɍ������ꂽ�V�����w�K�w���v�̂̒��Q����Ɋւ���L�q���Ɂu�\�����H�v���āC���̂�������蕨����������肷�邱�ƁB�v�Ƃ������ڂ�����B���a�S�S�N�̊w�K�w���v�̈ȗ��C�������ڂ���폜����Ă����w�����e�ł���B���N�V���Ɍ��J���ꂽ���w�Z�w���v�̉���̓����ڂɊւ������ɂ́C�u�g�̉��̕�����̌��C�S�̓����Ȃǂ��Ƃ炦�Ď��̂��������蕨����������肷�邱�Ƃ́C���k�̕��̌����⊴����L���Ȃ��̂ɂ��邱�ƂɂȂ���B�Ⴆ�C������S�����ɓ`���悤�ɁC�`�ʂ��H�v���ď������ƂȂǂ̎w���Ɍ��ʓI�ł���B�v�Ƃ���B��Ȃ��Ƃɉ�����̂̕����ʂ͑��̍��ڂ̉���̔������x�ł���C���e�I�ɂ���̐��̂����ĂƂ͌�����B
�@�������C�w���v�̍���҂̍ŏI�́u�w���v��̍쐬�Ɠ��e�̎�舵���v�̍��ڒ��Ɂu��Q�̊e�w�N�̓��e�̎w���ɂ��ẮC�K�v�ɉ����ē��Y�w�N�̑O��̊w�N�Ŏ��グ�邱�Ƃ��ł��邱�ƁB�v�Ƃ���B���Q�̎w�����ڂɈʒu�Â���ꂽ�u���́E����n��v�͑S�w�N�Ŏ��{�\�Ƃ������ƂɂȂ�C�����Čy�������Ƃ͂����Ȃ��B��̓I�ȓ��e�ɂ��Ă͎��H�҂ł��錻��̋����̔��f�ɂ䂾�˂�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B
�@���w���ނɂ́C����ƌ���ł��Ȃ��w�K���l������B���w�Ɋ֘A���鋳��_�����Q�Ƃ��Ă����̖ڎw���������͑��l�ł���C���݂��l�X�Ȍ����̏�C���H�̏�ł��̌����������Ă���B
�@�_�҂͍�N�x�܂ł̂R�N�ԁC���w�Z�̋��猻��Łu���w�I�F���v�Ƃ����e�[�}�̉��ŁC�l�X�Ȏ��H���s���Ă����B�{�_���̊j�ł���u�����n��v�́C��N�x�̖勳���w���ꋳ��w��Œ�Ă����������p���E���W���������H�ł���B�����e�[�}�u���w�I�F������ލ��ꋳ��̌����v�̍ŏI�i�K�Ƃ��āC����܂ł̌����E���H��U��Ԃ�Ȃ���E��Ă��s���C�V�����w�K�w���v�̂ɂ��L�q�̂���u���́E����n��v�̈Ӌ`�ɂ��āC�l�@����B
�@
��@���̑����猻���i���ȁj�����߂�
�P ���̑����猻�������߂� �|���ނ̐��E�ς��g��������n��|
�@
�@��N�x���\�����ɂ������Ă͈ȉ��̂悤�ȓ��e�ł���B�i�{�����̍Ō�Ƀ_�C�W�F�X�g�ł�t�����̂ŎQ�Ƃ��Ă������������j�B2000�NPISA�̖��u�������v�́C�قȂ���̂̌����C�قȂ錻���F���̂����������Q�l�̏��̎q�̘b�ł������B�_�҂͂��̖�肩��C�قȂ�R���e�N�X�g�̉��ɂ��镡���́u���t�v���֘A�Â���F���̂�������̊ϓ_�̈�Ƃ��Ďw�E���C��������Ɂu���w�I�F���v�Ɩ��t�����B��������u�ʌȓ�̎������֘A�Â��邱�Ɓv���ɂ��u�����F���̗͂����鋳��v�ƈʒu�Â��������x�j���̌��t��C���\�e�N�X�g�i���w�j���ӎ����ō�i�Ƃ��č\������ہu���Ȃ̌������E���ώ@�\�Ȏp�Ƃ��Ėڂɉf��v�Ƃ������H���t�K���O�E�C�[�U�[���̌��t�������C�u���w�I�F���v�̖{���₻�̌��p��T�����B�@
�u���炭�������E���痣��Ă����Ƃ����Ă��C�����߂�Ƃ��ɁC�Ȃɂ������ł͂����Ȃ��s���K�͂��g�ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ���C�ق�̋͂��ȊԂł��C���Ȃ̌������E���ώ@�\�Ȏp�Ƃ��Ėڂɉf��Ƃ���ɓ���������B�v�i���P�j�i�}�Q���}�̔ԍ��͑O�\�̂��́j
�@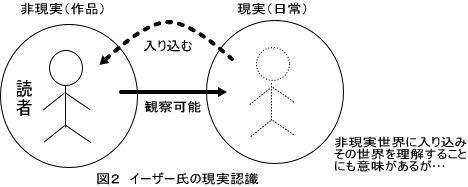
�@��X�͈�l��l�قȂ������̂̌��������āC���ꂼ��́u�����v���Ă���B�u�������v�ɓo�ꂷ��S���l�����̃x�N�g�����قɂ����l�̏��̎q�̉�b�́C��X�̓���́u�����v���̂��̂ł�����B���l�ȉ��l�E�}���ȕω�������Ƃ��錻��ɂ����āC�^�ɑ��҂̗���ɗ����Ă��̂��l����͓̂���B����͎����̌����F���̂��������U�̂Ă�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ����炾�B
�@�������̌����悤�ɁC���̊w�K�ɂ́C���҂̌����F���̂�����ɐG��C����̔F����L���ɂ�����ʂ�����B���ꂾ���łȂ��C�C�[�U�[���̌����悤�ɁC���\�e�N�X�g�i���j���E�Ɋ��S�ɓ��荞���C���Ȃ킿����̎����̔F���ƑS���قȂ鑼�҂̗���C���҂̍l������g�ɂ������C�l�͓����͈ӎ����Č��邱�Ƃ̂Ȃ������g�̉��̐��E��C�����̌����F���̂������V�N�Ȃ܂Ȃ����Ŋώ@�ł���悤�ɂȂ�B�����̌����F���̂��������U�̂Ă邱�ƂŁC�t�ɂ�����q�ϓI�Ɋώ@���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�{���\�ł́C���̂悤�Ȍ����F���|���w�I�F���|�̗͂���ނ��߂̋�̓I�Ȏ��H�̈�Ƃ��āC�L�[���[�h�T���ɂ��lj��ƁC���o�����L�[���[�h�𗘗p���������n����s�����B
�Q �����n��̕����I���� �|���ȔF���|
�@�V�����w�K�w���v�̂ł��w�����ڂ̈�Ƃ���Ă���u���́E����n��v�ɂ́C�����I�Ȍ��ʂƂ��āu���ȔF���v�̍�p������B���c�b�ꎁ���ҏW�����w���Ȉӎ������̌��݁x�Ƃ����{�̒��ŁC�X�����F�������̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u����̕��@�͎����Ɠ����ɋ�z��t�B�N�V�����������̏d�݂�S���C�����Ɣ��������肠�����Ƃ��K�R�ƂȂ�B�ނ���C����͂��̂��߂ɗL���Ȍ��\�`�Ԃł���B�i�����j�l�͎��Ȃ����̂Ɏ����������q�ׂ�͍̂���ł���B�ނ���C�w�������c�c�ł�������x�Ƃ����`�Ŏ��Ȃ̉\�Ԃ��q�ׂ���̒��Ŏ��Ȃ̐^���������ɂȂ邱�Ƃ��悭����B�v�i���Q�j
�@�����ɂ��Č�邱�Ƃ͎�����F�������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�J�E���Z�����O�ɂ����āC�N���C�G���g�i�˗��ҁj�͎����ɂ��Č��ߒ��Ŏ��Ȃ̓��I���E���ĔF���E�č\�����C�������Ă������߂̋��łȐ��_�I��������s���B�J�E���Z���[�͂��̎菕��������̂ł���B�������C�l�͎����ɂ��Č�낤�Ƃ��Ă��C�������g�ɑ������ς�펯�ɂƂ���āC�Ȃ��Ȃ��{���̎��Ȃ����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̎��C���̌`���Ƃ��ċ�z��t�B�N�V������p����ƁC���\�Ɍ������āu���Ȃ̐^���������ɂȂ�v�B
�@������̂悤�Ȋϓ_�́C����Ȃ̖ڕW���Ă͖T�n�I�Ȃ��̂ł������蓾�Ȃ����C�{���\�ɂ����Ă͕����I���ʂƂ��Ď��H���͂̊ϓ_�̈�Ƃ���B
��@���H��u�����n��w���삳��̊�ɂȂ�I�x�v
�@�ȉ��͕���19�N�x�����̋Ζ��Z�ł���啪��w���畟���Ȋw���������w�Z�R�N����Ώۂɂ������H�L�^�ł���B
�@ �P �� ���@���t���D��Ȃ����E�ɏo�
�A �Ώۊw�N�@���w�Z�R�N�i�S�N���X�@160���j
�B ���{���� ����19�N9���`����19�N10��
�C �P���ݒ�̗��R
�@�{�P���ɂ����đΏۂƂȂ�w�K�҂́C�C���^�r���[�������̗l�X�Ȋw�K�������o�āC���X�Ɏ�������芪�����E�ɑ���S��[�߂���B�N�x���߂Ɏ��{���ꂽ�S�������̌��ʂ�����C������������C���͂̕������m��I�ɂƂ炦�n�߂��w�K�҂̎p���͂�����ƌ����Ă���B�������C����̔F���݂̍���͈ˑR�Ƃ��Ĉ�ʓI�ł���B���܂��܂ȕ����̊Ԃɂ���W�������߂�C�����F���̗͂���ĂĂ����K�v������B
�@�{�P���ɂ����ẮC���쓹�v�w�A���X�J�Ƃ̏o��x�����ނƂ����B���̋��ނ͒��Ґ��쓹�v���C�ꖇ�̎ʐ^�ɂ���Ď����̐l�������I�ɕω������Ă������ߒ��������Â������z�ł���B�ʐ^�ɏo��O�̒��҂́C����������邽������̐l�X�Əo��Ȃ��Ƃ����u�߂��݁v�̒��Ő����Ă����B�������C�o��Ȃ��u�߂��݁v�́C���̂܂o��ݏo�������͂ƂȂ��Ĕނ̐S�����Ă����B���҂Ɨ���Ă���Ƃ��������C�t�ɑ��҂�ϋɓI�ɋ��߂�C�����ɂȂ����Ă���B����Ɉꖇ�̎ʐ^�����ݏo�����u�o��v�́C�P�ɒ��҂ƃA���X�J�̐l�X�Ƃ̂��ꂾ���ł͂Ȃ��B���҂̐l��������Â����ꖇ�̎ʐ^���������C�ނ͂��̎ʐ^���B�e�����W���[�W�E���[�u���B���̐l���Ƃ��琂��Ă���B���̓_���{���ނ̍ő�́u�v�ł�����B���́u�l�Ɛl�Ƃ��o�������Ȃ��s�v�c���v�Ƃ������e�I�ϓ_�ɂ��C�{���ނ͑��҂Ƃ̊W���ɖڊo�ߎn�߂��w�K�҂ɓK�������ނƂ�����B
�@�w���ɂ������ẮC�����i�K�ŁC�܂����쓹�v����̎ʐ^�W����C�ӂ̎ʐ^���ꖇ�I���C����ɂ��Ċ��������Ƃ����������B����͒P���I����̔F���̕ω����w�K�҂Ɏ��������邽�߂̎肾�Ăł�����B���ɁC�{����N�ǂ�����u�L�[���[�h�T���v���s�����B�u�߂��݁v�u�����v�u���R�v�u�s�v�c���v�u�o��v���́u�L�[���[�h�v�Ԃ̂Ȃ�����ӎ��������B����͍�i���́u�v���w�K�҂Ɉӎ��������Ƃł�����B���i�K�Ƃ��āC�����i�K�Ŗ��炩�ɂȂ����u�v�̈������ꂼ�ꔭ�≻���C�\���I�Ȕ��̒��Ɉʒu�Â��邱�Ƃŕ�����q�ϓI�ɂƂ炦�������B��O�i�K�Ƃ��āC���쓹�v����̎ʐ^��i����C�w�K�҂����삳��̐l���Ƃ́u�o��v����������̂�I���C��i�̉��ɍ��߂�ꂽ���҂̐l�����S�l�ǂŕ��ꉻ�������B���̍ہu�L�[���[�h�T���v�̍ۂɒ��o���ꂽ�u�L�[���[�h�v���J�[�h�ɂ��āC��������ۂɕK�v�ȃJ�[�h���S�l�ǂŘb�����킹���B�I�J�[�h���`�R�̉�p���ɓ\��t�������C�u�L�[���[�h�v���݂̊W��}���������B���̂悤�Ɋw�K�҂ɂ���Ē��o���ꂽ�ϓ_�i�u�L�[���[�h�v�j�𑫂�����ɂ��ēlj���i�߁C���ݎ�������ނ̐��E�ς𗘗p���āC�n�슈�����s�����B�܂�u�ǂށv���ƂƁu�����v���Ƃ��C�ЂƂȂ���̊����Ƃ���̂ł���B����Ɋ������������i�\�����C���ꂼ�ꋳ�ނ���ǂ݂Ƃ������E�ς�����n��̍ۂɗL���ɓ����Ă��邩�ǂ����N���X�S�̂ŋᖡ�������B�ȏ�̂悤�ɖ{�P���ɂ����ẮC�u�L�[���[�h�v�C���Ȃ킿��i���̌��t��S�������Ƃ�����ŋ��������C�w�K�҂̓��ʂŁu��i�v�ƂȂ��Č������邱�Ƃ�ڎw�����B����Ɋl���������E�ς��g���āC�e�L�X�g�O�̏��|�ʐ^��i�|��ǂ݉������B�����̉��l������I�ɓ`�B����̂ł͂Ȃ��C���k�X�ɋ��ޓ��̌��t�̈����Ƃ炦�����邱�ƂŁC��̓I�Ɏ����⎩���̎��͂̐��E�����߂�p���|���w�I�F���|��g�ɕt�������邱�Ƃ��˂���Ė{�P����ݒ肵���B
�D �w�K�w���ڕW
| �@���ޓ��́u�S��\���v��u�L�[���[�h�v���̂Ȃ�����Ƃ炦�����C���ނɓ���ꂽ�u���w�I�F���v��g�ɕt��������Ɠ����ɁC���̔F�����g���������n��ɂ���āC�����⎩���̎���̌��������߁C����̐��������l����ԓx��{���B |
�E �w�K�w���v��i�����Ԑ�11���ԁj�@
�k�P�l�ʐ^��i�ӏ܁i�P���ԁj
| �@���҂̎ʐ^��i���ӏ܂��C���z����������B(1) |
�k�Q�l�L�[���[�h�T���i�P���ԁj�@�@
| �@���ޖ{����N�ǂ��C�u�L�[���[�h�v�𒊏o�����C���ނ́u�v���m�F������B(1) |
|---|
�k�R�l���ޖ{���̓lj��i�R���ԁj
| �@�O���܂łɊm�F���ꂽ�l�@�|�C���g�i�j����ɁC���ⓙ�ɂ���ċ��ނ�lj�������B (3) |
�k�S�l�����n��u���삳��̊�ɂȂ�I�v�i�T���ԁj
| (1) �C�ӂ̎ʐ^��i�����`�[�t�ɂ��āC�����n��̂��߂́u�L�[���[�h�֘A�\�v��n�点��B (1) (2) �u�L�[���[�h�֘A�\�v����ɁC���쓹�v����̎ʐ^��i�����`�[�t�ɂ���������n�삳����B (2) (3) �Ǖʂɑn�삵������\���C�ӏ܂������B (2) |
�k�T�l���Ȃ̕ϗe�����z�ɏ����i�P���ԁj
| �@�ŏ��ɑI�ʐ^�Ƃ��̊��z���������C�{���w�K��̈�ۂƔ�r���Ċ��z����������B (1) |
�F �w�K�w���̎���
�@�P �ʐ^��i�ӏ� �i�P���ԁj
�@�P���̓����Ƃ��āC���ށw�A���X�J�Ƃ̏o��x�̍�Ґ��쓹�v����̎ʐ^��i���w�K�҂Ɍ����C���z�����������B�P�O���̎ʐ^�W��p�ӂ��āC�P�N���X�S�l�ǁ~�P�O�ʼnǂ݂��C���̒��ŋC�ɓ�������i����l����I�����B�����āu�ǂ�Ȏʐ^���H�v�u�ǂ����C�ɓ��������H�v�u�ǂ��v�������H�v���̊ϓ_��^���āC�S�O�O�����x�̊��z�����������B���̎��_�ł́C���ޖ{���ɂ��ẮC����������Ƃ����\���������Ă��Ȃ��B����͋��ޖ{����ǂނ��ƂŁC�ʐ^��i�ɑ������ς����܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł���B
�@�P���Ɋ��������Ƃ���������́C�o�ꂷ�铮���ɂ��ē���I�Ȓm������������́C�l�X�ȃp�^�[�����������B���ꂼ�ꂪ�ΏۂƂ����ʐ^��i�ɂ��āC���̑S�Ă��R�s�[���āC���z���p���̗��ɓ\��t�������C��U��������B�P���̍Ō�ɁC�ŏ��ɏ��������z�����Ĕz�z���āC�P����̊��z�Ɣ�r�����邽�߂̏��u�ł���B�i������犴�z�̓����ɂ��Ă͌�ŕ��͂���B�j
�Q �L�[���[�h�T�� �|���Ɏ��I��Ԃ�n��o���| �i�P���ԁj�@
�@�u�L�[���[�h�T���v�́C�_�҂�����̎��Ƃ̍ہC��Ɋe�P���̓����i�K�ɂقڑS�Ă̋��ނň�т��čs���Ă��銈���ł���B���Ƃ��Ƃ́C�{���̈ꕔ���ɂ�������đS�̂��ՓI�ɑ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ���⍑��̋��Ȋw�K�҂ɑ��āC�{�����̌��t�̈�ЂƂɈ������킹��ړI�Ŏn�߂������������B���Ƃ̓����i�K�ŁC�_�����ł���L�[���[�h�C���w��i�ł���ΐS��\�������ꂼ��w�K�҂ɒ��o�����C���̑S�Ă�����ɏ������ׁC�L�[���[�h�i�S��\���j���݂̂Ȃ��肪�킩��₷���悤�ɂ��Ă���B�܂�������ۂɁC�w���҂��L�[���[�h�Ԃ̂Ȃ���ɂ��Ă̈Î������Ԃ₫�C�w�K�҂��C���[�W�����N���₷���悤�ɓ��������Ă���B
�@���Ƃ̍ۂɂ̓L�[���[�h�i�S��\���j���ȉ��̂悤�ɒ�`�Â��C�w�K�҂Ɏ������B
�s �L�[���[�h�̒�` �t
�@�@ �{�����ɉ��x���J��Ԃ��o�ꂷ�錾�t�B�i�ے������̂��܂ށj
�@�A �i�����܂������Ďg���Ă��錾�t�B�i�ے������̂��܂ށj
�@�B �����Ӗ������قȂ錾�t�i�\���j�B
�@�C ��x�����g���Ă��Ȃ��Ă��C������d�v�ȈӖ��������t�i�\���j�B
�s �S��\���̒�` �t
�D�u���ꂵ���v�u���Ȃ����v���̂悤�ɁC���ڐl�̐S��\���������́B
�E�u�肪�k����v�̂悤�ɁC������Ԃł���Ȃ��炻�̐l���̐S���킩����́B
�@�@�L�[���[�h���ꂼ��͒P�̂ł͎����I�ȈӖ��������ĂȂ��B���ꂪ����ɕ��ׂ��邱�Ƃɂ���āC�L�[���[�h�ԂɁu�v�����o���C�w�K�҂̃C���[�W�����N����B����Ɏ��I��ԂƂ������ׂ����t�̂Ȃ�������o���C�w�K�҂̕��w�I�F���𑣂��B�܂����t�̈��̈Ӗ��ɂ��Ă��C����I�ȃR�[�h�ł͓ǂ݉����Ȃ��Ƃ�����ۂ��w�K�҂ɗ^���C���������ߒ����p������������B
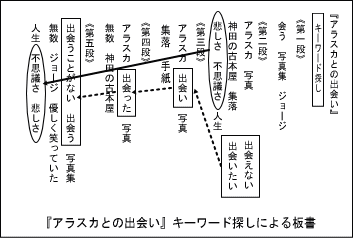
�@
�@��L���͎��ۂ̎��Ƃł̂��̂ł���B���Ō��ꂽ�ӏ��ɁC�w�A���X�J�Ƃ̏o��x�ɂ�����C�ł��傫�ȁu�v������B�i����傫���܂�����L�[���[�h�u�߂����C�s�v�c���v�ƁC�S�҂��т��L�[���[�h�u�o��v�́C�M�҂ƃA���X�J�C�����ăW���[�W�E���[�u���C���Ƃ��琂̂�����������������̂ł���C��i�̃e�[�}���̂��̂Ƃ�����B�������C�P���Ɂu�o��̕s�v�c���v�ƂȂ��Ă��܂������ł́C���ޗ����͐Ȃ�B�M�Ґ��쓹�v���́C�u���m��ʐl�ɏo��Ȃ��߂����v�������Ȃ��琶���Ă����B�W���[�W�E���[�u���C���̎B�e�����₵���Ƃ��g�����V�V���}���t���̎ʐ^���������C������B�e�������[�u���C���̎v���Ɛ��쎁�́u�߂��݁v�����������ʁC�u�o��v�����܂�n�߂�B�܂�C���̕���́u�v�������L������l�̒j�̕���v�Ƃ������ߏ�̒n��������Ă���B���̂悤�Ȋϓ_�̊l���́C���̒P���̍ő�̖ړI�ł���u���삳��̊�ɂȂ��Ďʐ^��i�����ߒ����v�Ƃ����������s�����߂ɕs���ł������B���쎁�����[�u���C���̎ʐ^�����Ă��̉��ɂ���v���������p�����悤�ɁC�w�K�ҌX�ɂ����쎁�̎ʐ^��i��ʂ��Đ��쎁�̐l�����琂��Ă��炢�����ƍl��������ł���B
�@���̓_�C���Ɂu�߂��݁v�Ɓu�s�v�c�v�Ƃ����L�[���[�h�́C�ɂ߂Ď��I�ȂȂ���������Ă���C�w�K�҂̈ӎ���P���ȁu�o��̕s�v�c���v�ȂǂƂ������\�ʓI�ȉ��߂���������������ʂ��������B�Ȃ��u�߂��݁v���u�o��v�������N�����̂��B�P�ɍ���ɃL�[���[�h�����ׂ��邾���ł��C�w�K�҂̒��ӂ����N������ʂ����������C�w���҂́u�w�o��x���w�s�v�c�x�Ȃ̂͂Ȃ�ƂȂ������邯�ǁC����ɂȂ��w�߂��݁x���W���Ă���̂��́C���\�l����������ˁB�v�ƈÎ�����^���C�w�K�҂̔����𑣂��G�}�Ƃ��Ă̓������������Ă���B
�R ���ޖ{���̓lj� �|���e�I�Ȋϓ_�ł́u���҂̔F���v�| �i�R���ԁj
�u�L�[���[�h�T���v�ɂ���Ē��ꂽ�L�[���[�h�𑫂�����ɂ��Ȃ���C����̐ݖ��ݒ肵�C�t���[�`���[�g�I�Ȕ��ɂ���ċ��ޓ��e�̐��m�ȗ����ɓw�߂��B���{�����͈̂ȉ��̂悤�ȓ��e�ł���B�i�y�[�W���́u����R�v�����}���ɂ��j
�EP174L9�u�W���[�W���[�u���C�Ƃ������O���ˑR�L���̏����������������͂��߂��B�v�ɂ��āu�L���̏����������������n�߂�v�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H
�E�ŏ��̈Ӗ��i���͈̔͂ŁC�W���[�W�E���[�u���C���͕M�҂ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ȑl���ł���ƕ����邩�H
�EP175L19�u�����������Ɓv�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H
�EP176L3�u�ǂ����Ă��C�ɂȂ�ꖇ�̎ʐ^�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȏʐ^���H
�EP177L18�u���̏W���������Ƃ��̋C�����́C����Ɏ��Ă����v�ɂ��āu����v�Ƃ́H
�EP177L19�u�l�͂ǂ����Ă��C���̐l�X�Əo������Ǝv�����v�ɂ��āC�ǂ����Ă����v�����̂��C�z�����ē�����B
�E�ŏ��̃A���X�J���s�Ŋ��������Ƃ��܂Ƃ߂�B
�EP180L12�u���킹���ɉf���������̎p������悤�v�ɂ��āC�킩��₷������������ƁH
�EP180L20�u�ǂ�ȋC�����Ŗl����ɗ����̂����m�炸�v�ɂ��āC�ǂ�ȋC�������z�����ē�����B
�EP181L8�u�ŁC������Ă��邩���B�v�u�ڂ̉����C�D�������Ă����v�ɂ��āC�ǂ̂悤�ȋC�������H
�E���̕���ɂ�����ő�̏o��͂Ȃɂ��H
�@��L�̐ݖ�́C���e�𐳊m�ɗ������邽�߂̂��̂������B�P���̍ŏI�ړI�ł���C�ʐ^��i�����`�[�t�ɂ���������́C���쓹�v������l���Ƃ��āC��i�̐��E�ς��g���C���쓹�v����Ƃ����u���҂̔F���v��g�g�݂ɂ������̂��ƍl���Ă����B���̂��߁C���Ɂu�߂��݂����ݏo���o��̕s�v�c���v�𐳊m�ɓlj����邱�Ƃ��C���̊w�K�i�K�ŕs���ł������B
�S �ʐ^��i�����`�[�t�ɂ��������n�� �|�L�[���[�h�֘A�\��p���� �i�T���ԁj
�@���ޖ{���̗������I�������C���悢�敨����Ɏ�肩�������B�ĂтS�l�ǂɂȂ�C���쓹�v�����10���̎ʐ^��i�W�����āC���ꂼ�ꃂ�`�[�t�ƂȂ�ʐ^��i����I�����B���ɁC���͂̍\�����l���邽�߂̕⏕�Ƃ��āu�L�[���[�h�֘A�\�v���S�l�ǂ̊e�ǂɍ�点���B���̒P���̖ړI�́C���ށw�A���X�J�Ƃ̏o��x�̐��E�ς��g���āC�ʐ^��i�����`�[�t�ɂ�������n����s���Ƃ���ɂ������B����ɂ́u�ǂ݁v�̐[���𑣂����߂́u�����v�����C�Ƃ����ړI������B��i���̑S�ẴL�[���[�h���݂̊֘A�ɖڂ����������邽�߂Ɂu�L�[���[�h�T���v�̍ۂɒ��o�����L�[���[�h�Q�ɁC�Ăш������킹�C���ނ̐��E�ς��ĔF��������K�v���������B
| �k�Ɍ� | �W���[�W�E ���[�u���C |
�ʐ^�W | ���R | �A���X�J | �Ö{���X | �C�k�C�b�g �̑� |
�s�v�c�� | �莆 |
| �Ԏ� | �D���� ���� |
���R | �o����Ƃ� �Ȃ� |
���� | �ꖇ�� �ʐ^ |
�W�� | �l | �l�� |
| �J���u�[ | ���� | ��炵 | �������ߕt ������ |
�Ƒ� | �g�i�J�C | ���l�� | �������� | �N�} |
| �߂��� | �o� | �o� ���� |
�o��Ȃ� | �i�����j | �i�����j | �i�����j | �i�����j | �i�����j |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�L�[���[�h�J�[�h�v�i�S31���j
�@�܂��u�L�[���[�h�T���v�̍ۂɒ��o���ꂽ�L�[���[�h�i31�j�̑S�Ă��L�[���[�h�J�[�h�ɂ��āC�S�l�ǂɔz�z�����B����Ɋe�ǂɁu���삳��̊�ɂȂ�I�v�Ƒ肵���`�R�̐F��p����z�z���āC���̏�Ƀg�����v�̂悤�ɃJ�[�h���܂��U�炳�����B�����ĉ�p����ŃJ�[�h���������������C���쎁�̎ʐ^��i�����Ȃ��畨����̍ۂɕK�v�ɂȂ肻���ȃL�[���[�h���C���݂̊W���l�������Ȃ��璊�o�������B�i��N�x�u�[�u���v�����C�g�̍ۂɗp������@�Ɠ����ł���C�j�i�@�̉��p�ł���B�j
�@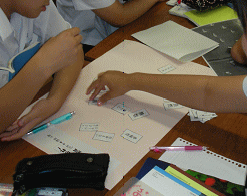 �@�@�@
�@�@�@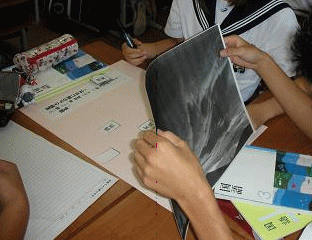 �@
�@
�@�E�}�́u�L�[���[�h�J�[�h�v�́C�藣���ăJ�[�h�ɂ������̂�ǂɈ�C�藣���O�̈ꖇ�̃v�����g�̏�Ԃ̂��̂�S���ɔz�z���Ă���B�L�[���[�h�́C�ʐ^��i����A�z�������t��V���Ɏ菑���Œlj����Ă悢�Ƃ����B
�g�p����J�[�h�͂T�`�V���Ɍ��肵���B����ȏ�̖����ɂȂ�Ƃ����L�[���[�h���Ȃ��������ō앶���邱�Ƃ��ł��C���t�ƌ��t�̊Ԃɐ��܂��u�v�̋@�\���C�������Ď�܂��Ă��܂��ƍl��������ł���B�܂��C���ꂼ��̂Ȃ�����֘A�\��ɐ}�����邽�߂ɂ��V�����x�����E�������B
�@�����n�삳����ۂɁC���̂悤�Șb�������B
| �@�i�������D�����፷���Ō��߂Ă���A�U���V�̐Ԃ����̎ʐ^�������Ȃ���j���̎ʐ^�̃A�U���V�́C��̂�������߂Ă���̂ł��傤���B�ʐ^���������Ɍ�����ƁC�A�U���V�͎������߂Ă��܂��ˁB�N�����̕���������ƁC���x�̓A�U���V�͌N���������߂܂��B�A�U���V�͖{���ɂ����\������Ă��܂��ˁB�@�����悳�����ł��B�������C���ۂɂ̓A�U���V�͉������߂Ă���̂ł��傤���B�A�U���V�����ۂɌ��߂Ă���̂́C���̎ʐ^���B��ꂽ�u�Ԃ̃J�������\���Ă��鐯�쓹�v����ł���ˁB�܂�C�A�U���V�̎ʐ^�������������Ă���Ƃ��C������������ꏊ�ɂ͎����z���Đ��쓹�v�������Ă���B�܂�C�ʐ^��ʂ��āC�������Ɛ��삳��͏d�Ȃ��Ă���킯�ł��B���삳����V�V���}���t���̎ʐ^���������C���[�u���C���Əd�Ȃ��Ă����̂����m��܂���ˁB�����C�Ȃ��A�U���V�͎������Ɍ������Ĕ���ł���̂��B����삳��ɂȂ肫���āC�z���̓t����]�ōl���Ă݂܂��傤�B |
�@���҂̎��_�ɗ����C���҂̔F�����g���āC����̗l�X�ȕ������ĔF������Ƃ����̂����̒P���̖ڕW�̈�ł������B�ʐ^�Ƃ������ނ́C������ӏ܂��邱�Ǝ��̂����ҁi�����ł͐��쓹�v���j�̔F������ɓ����Ƃ������Ƃł�����B�w�A���X�J�Ƃ̏o��x���ޖ{���̓��e�I�ϓ_�ł����鑼�҂̔F���̊l�����ʐ^��i���g���Ď��ۂɍs���C����������ɏ����|���ꉻ����|���ƂŁC�l�������F�����ӎ������邱�Ƃ�ڎw�����B
�@�u�L�[���[�h�֘A�\�v���ɂP���ԁC������ɂQ���Ԃ�������C�T�ǂ��Q���Ԃɕ����Ĕ��\����s�����B���\�̍ۂ͂S�l�Ǔ��ŁC�ʐ^�̉���W�C�L�[���[�h�֘A�\�̉���W�C����̘N�njW���S�����C�K���S�����Q������悤�Ɏw�������B
�@��i������Љ��B
�i�ȉ��́u�[�Ă��v�Ƃ�����i�́C�A���X�J�̍L��ȋ�S�̂��^���Ԃɐ��܂����ʐ^�����`�[�t�ɂ��Ă���B���쌠���l�����āC�ʐ^�̌f�ڂ͍s��Ȃ��B�j
�@�薼�w�[�Ă��x �@�[�Ă����݂��B���{�Ƃ������C�ƂĂ��Ȃ��L������C���f���Ă���ƊȒP�ɂ������܂ꂻ�����B���͒��Ԃ���A����āC���̏ꏊ�ɂ����B�u���̎��Ԃ͗[�����ƂĂ����ꂢ������C�����G���B����B�v���������āB �@����ۂ́u�ԁv�������B�����ƈ��]���Ă݂Ă��ڂɉf��̂͂���ς�ԂŁC����͎��ɂȂ������l���v���o�����Ă��ꂽ�B��ł���B �@�D�����l�������B��Ɏ����x���C����葱���Ă��ꂽ�B�����ˑR�͂邩�����̓y�n�C�A���X�J�ɗ����������ƌ����o���������B��ɁC�Ȃ��A���X�J�Ȃ̂��C�����ʼn����������̂��C�͂�����ƌ��t�ɂ��Đ������邱�Ƃ��ł����C���ǂ����������B�Ȃ�ƌ��������̂��낤�B�[��ꎞ�ŁC�ǂ����炩�݂��`�̂����ɂ��������Ă����B���ꂪ�Ȃ��������ł点���B�������ޏ��́C���̖ڂ��܂��������āC �u���Ȃ��̐l���Ȃ���C�D���ɂ��Ȃ����B��������̂��̂����̖ڂɎʂ��ċA���Ă��Ȃ����B�v �ƁC�����₩�Ɍ������B�����������̂��Ђ낦��Ƃ�����ˁC�Ə��āB �@�ڂ̑O���}�ɂЂ炯���悤�ȋC�������B�ł���������B�����猩�����́C�����ɗ[�Ă��������B �@������B���R�������B�����������ƐS�ɐ��݂��ށB �@�������C���グ���͗D�������Ă����B �@���R�͋��R�ɂ���č��グ���Ă���B��u�ł���ȑf���炵�����i��`���Ɠ����ɁC���͉�Ȃ������̐l�ƁC����Ȍ`�ōĉ���Ă����B �@�N�ɂǂ����ӂ����Ă悢���킩��Ȃ��āC�܂����ǂ������v��������̂�����ǁB���͂��ꂷ����S�n�ǂ��B �@�����Ђ������������̂��̂��C���Ȃ��ɓ͂������B �@���͂������ƃJ���������܂����B �@�����_�̊Ԃ���C�D�����u�ԁv���~���Ă��āC���͂���ɂ����܂��B �@�p�V���@�Ƃ������C���悢�������ɉ^��ď����Ă������B |
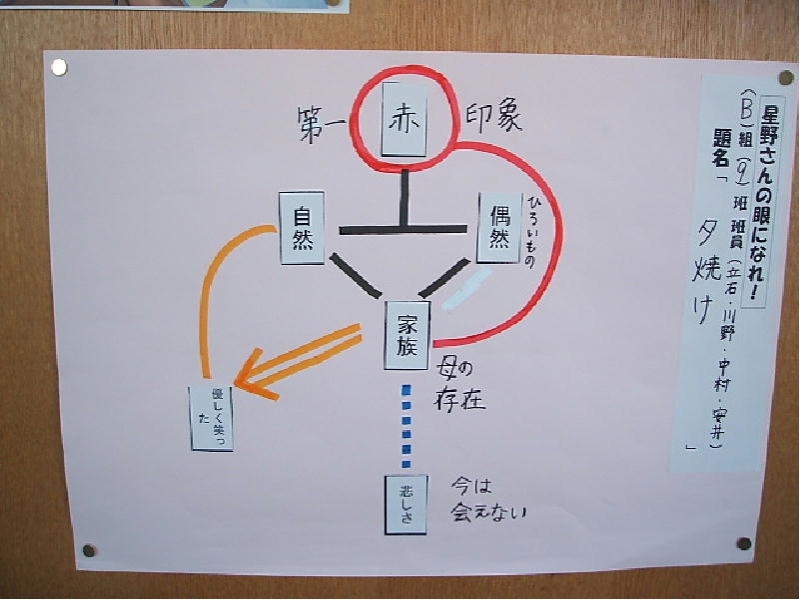
�@����n��̍ۂɗp����L�[���[�h�́C���ޒ��Ɏ��ۂɎg���Ă�����̂�K���������邱�Ƃ������Ƃ������C�g�p���ɂ��Ă͌��肵�Ȃ������B�܂��C���`�[�t�ƂȂ����ʐ^�����ĘA�z����錾�t���L�[���[�h�Ƃ��Ēlj����Ă����Ǝw�������B�Ⴆ��i�u�[�Ă��v�ł́u�ԁv���w�K�҂ɂ���Ēlj�����Ă���B�܂��u�L�[���[�h�֘A�\�v�̃L�[���[�h�͂����܂ł�������\�z����ۂ̊�揑�Ƃ��Ĉ����C�\��t����ꂽ�L�[���[�h��K�������S�č�i���ɓo�ꂳ���Ȃ��Ă��悢�Ƃ����B����́C�L�[���[�h�g�p�̐�����݂��Ȃ��Ă��C���ށw�A���X�J�Ƃ̏o��x�̐��E�ς�w�i�ɂ��������n�삷��w�͂��C�w�K�҂������Ă���Ɣ��f��������ł���B�u��v�́w�A���X�J�Ƃ̏o��x�ɂ͑S���o�ꂵ�Ȃ��B�܂�u�ԁv���F�����āu��v��A�z���Ă���̂́C�����n�삵���w�K�Җ{�l�Ȃ̂ł���B�u���R�v��u�i�o��Ȃ��j�߂����v���̋��ޒ��̃L�[���[�h���C���̐��E�ς�ۂ����܂܂ň����Ȃ���C���t�ƌ��t�̊Ԃ߂�C���[�W�Ƃ��āC����̐S�̒����̂������݁C����̎v�������o���Č����ɗ��p���Ă���B
�u�[�Ă��v�̂悤�ȁu�Ƒ��v��A�z����^�C�v�̍�i�͑��������B����́u�l�ɏo��Ȃ��߂��������R�̏o��ݏo���v�Ƃ����C�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ�����e�[�}�ɂ����w�A���X�J�Ƃ̏o��x�̐��E�ς���C�\�z���ꂽ���Ƃł͂������B
�@�܂����̂悤�ȍ�i������B
�i�A���X�J�̓~�̐^�����ȑ�n��w�i�ɔ����L�c�l��������������ƌ��Ă���ʐ^�����`�[�t�ɂ�����i�ł���B�j
�@�薼�w�ǓƂ���̏o��x �u���͐��쓹�v�C���C�A���X�J�ɂ���B�v �@�ƂڂƂڂƓ~�̊�������������B���͍��C�A���X�J�̓��y�̂悤�ɓ�����Ă���B �@�Ȃ��Ȃ낤���B�����ł�������Ȃ��B���͐́C�_�c�̌Ö{���ň���̖{�ɖڂ��Ƃ܂����B����̓W���[�W�E���[�u���C�Ƃ����l�̎ʐ^�W�������B �@�p�����p�����ƃy�[�W���߂���ƁC�ꖇ�̎ʐ^�ɏo������B���̎ʐ^���l�Z�������Ă���ƁC���̍��̋C�����ƃs�b�^�������悤�Ȏʐ^���ƋC�������̂������B����Ŏ��̓A���X�J�Ɍ��������B�A���X�J�ł͂�������̐l�⓮���ɏo��C�����������C���̓��y���n���n�߂Ă����B���̎��������B �@���̖ڂ̑O�ɂ܂����ȃL�c�l����C�p���������B�܂����ȃL�c�l�͂ƂĂ����炵�����̔�������Ɨn�������悤�Ɏ��̋C���������������炢�ł������B �@�������L�c�l�Ɩڂ����킹�Ă���ƁC�Ȃ����C�S�ʼn�b���Ă���悤�ȋC�ɂȂ����B �u�l�C����l�ڂ����c�˂����������āC���v������H�v �u����c����B���͍��C�ǂ����Ă������킩��Ȃ��Ďʐ^�ɋ����������āC�A���X�J�ɗ����B�ł��N�ɉ�Ă悩������B�Ȃ��C�������y�ɂȂ��Ă����B���肪�Ƃ��B�ǂ������H�N�̎ʐ^���ꖇ�B�肽�����c���������H�v �u�{���ł����H��낱��Łc���肢���܂��B�v �u����C�Ȃ��Â�������Ă����Ȃ������H�v �u������ł��B�l�Ɠ��v����̋��ʂ̋C���������̎ʐ^�Ɏc���Ďv���o�ɂ������āc�B�v �u�������c�B����Ȃ炢�����낤�B�v�i�ԁj �u���肪�Ƃ��������܂����B����͈ꐶ�̕ł��ˁB�v �u�������Ȃ��C�����̂��̎������͈ꐶ�Y��Ȃ���B���ꂶ�Ⴀ�c�B�v �u���悤�Ȃ�c�B�v �@�܂����̈�l���͎n�܂����B���x�͂ǂ��֍s�������c�Ȃɂ��āC�ǂ�Ȏʐ^���B�낤���c�B�i�ԁj �@���͂܂��~�̊��������ƂڂƂڂƕ����͂��߂��B�ł��C���x�̗��͂Ȃ�ƂȂ����邭�������B�C�̂����Ȃ̂��낤���c�B����C����͂����ƋC�̂����Ȃ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����v���Ȃ��������Ɛi�ݑ����C�ǂ�ǂ����̌i�F���ς���Ă����c�B�s���N�C�C�ԁC�����Ĕ��c�B�܂����̋G�߂�����Ă����B�v���o�[�����������B�ꐶ�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����B�܂�����炢���Ȃ��B����Ȏv�����B���͍��C������������Ă���B �u����H�v���͂��C���ɏo�����B�O�ɂ͈�̑傫�ȕW�D���c�B �@�悭���Ă݂�Ƃ����ɂ́w��]�ւ̓��x�Ə�����Ă������B �@���͂܂������ĂȂ������B���������������c�B���̓����܂������i�߂����̂��Ɓc�B |
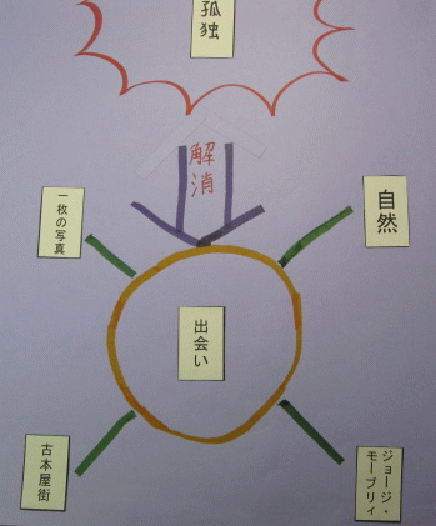
�@�薼�u�ǓƂ���̏o��v���̌��t�u�ǓƁv�́C�E�̃L�[���[�h�֘A�\���番����悤�ɁC�L�[���[�h�̈�Ƃ��Ďg�p����Ă���B���ޖ{�����ɂ́u�ǓƁv�Ƃ������t�͓o�ꂵ�Ȃ��B���ޓlj��̒i�K�ŁC�V�V���}���t���̎ʐ^�̃C���[�W�����ꉻ����w�K���s�����B���̍ۂɁC���\���ꂽ���t�̒��̈�ł���B�u�l�Əo��Ȃ��߂��݁v���u�o������v�Ƃ����C�����ɂȂ���Ƃ����{���ނ̃e�[�}�ɂ��u�ǓƁv�Ƃ������t�͓����Ă���C���ނ̉B�ꂽ�L�[���[�h�ƌ�����B���������āC���̔ǂ̑n�삵�������́C���ޖ{������ǂݎ�邱�Ƃ��ł��鐯�쓹�v���̐l�����ɂ���߂ċ߂��l�����`�����Ă���B
�@��i���̉������u�L�c�l�Ɩڂ����킹�Ă���ƁC�Ȃ����C�S�ʼn�b���Ă���悤�ȋC�ɂȂ����v��u�l�Ɠ��v����̋��ʂ̋C���������̎ʐ^�Ɏc���Ďv���o�ɂ������āc�v�Ƃ������쎁�̐S�̒��́u�L�c�l�̌��t�v���番����悤�ɁC���̍�i�͏d�w�I�ȍ\���������Ă���B�L�c�l�����߂Ă��鐯�쎁�̔F���C�L�c�l�̕\��ɉf�荞��ł��鐯�쎁�̐S�C�����Ă���쎁�̋C�����ɂȂ��ĔF�����悤�Ƃ��Ă���w�K�҂̐S�C�l�X�ȔF�������ߖ@�I�ɍ\������C��i�Ƃ��Ă̋��ʂ̒n��������o���Ă���B��i�̌㔼�ł́C���쎁�̐l�����ے��I�ȕ\���ł܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ă���B���X�g�́u��]�ւ̓��v�͂��̍�i�̍�ҒB�̐S�̒��ɂ�������Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�ȏ�̂悤�ɁC�w�K�҂ɂ���ėl�X�ȃ^�C�v�̍�i���n��o���ꂽ�B�F�i�L�c�l�C�A�U���V�j�̔F���Ɛ��쎁�̔F����������L�q�������́C�u�o��v��u�F���v���̂��̂��e�[�}�ɂ����N�w�I�Ȃ��́C�����������Ă��鎩�����g�̎p�����̂܂ܕ\���������̓��X�B���ޓ��ō�҂̐��쓹�v��������Ă���C�u���킹���ɉf���������̎p������悤�ɁC����Ȃ������̋��R�������Ă����v�A���������C���ނ�ǂ݁C���̐��E�ς�ʂ��Ďʐ^��i�����߂Ă���w�K�҈�l�ЂƂ�̐S�ɂ܂œ`����Ă��Ă���B�i�_�҂̃C���^�[�l�b�g��̃z�[���y�[�W�u�F�j�̏Z���v��10�ǁ~�S�N���X�S40��i���C���`�[�t�ƂȂ������쓹�v���̎ʐ^��i�C��揑�ł���u�L�[���[�h�֘A�\�v�t���Ōf�ڂ��Ă���̂ŎQ�l�ɂ��Ă������������B�j
�@�T �w�K�O��̊��z�Ɍ��錻���i���ȁj�F���̕ω� �i�P���ԁj
�@�P���̍Ō�ɁC�P���̍ŏ��ɏ��������ʐ^��i�̊��z�i���Ɏʐ^��i�̃R�s�[���\���Ă�����́j
���Ĕz�z���C������i�ɑ��ĒP���I�����݂ǂ̂悤�Ɋ����邩���w�K�҂ɏ��������B�w�K�҂ɂ���đ��푽�l�Ȋ��z�����܂�Ă����B�ŏ��̊��z�ƕω����Ȃ��Ƃ������Ƃ��C���R�������Đ��S���ɂ킽���ċL�q�������̂��������B�����ł͓����I�Ȃ��̂��Љ��ɗ��߂�B
�@���̊��z�́C�L��ȃA���X�J�̎��R��w�i�Ƀ��[�X�̐e�q���̂�т�Ɛ��ӂɂ�������ł���ʐ^��i��Ώۂɂ��Ă���B
| �y�P���ɓ���O�̊��z�z�@ �@���̎ʐ^�̓A���X�J�̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�X�т̒��̂Ђ炯���n�Ƀ��[�X�������Ɉ��݂ɗ��Ă��镗�i���Ƃ������̂ł��B�����C�ɓ������Ƃ���͔w�i�̖X�̐F�����ꂢ�Ń��[�X���Ɍ���t���Ă������瓯�S�~��ɔg���`����Ă���l�q�ł��B�Â��ȐX�̒��Ƀ��[�X�������Ȃ��悤�Ȋ��������Ă����B���������������X�ӂ��Ă��̂���тɐX�̖����Ă��銴�������܂����B���̎ʐ^�����Ĉ�l�ł���ȍL���X�̌Ƀ|�c���Ƃ�����ǂ�ȋC�������邾�낤���ƍl���܂����B�ŋ߁C���{�ł͐����̖��⎖�����₦�������������Ă��邯�ǎʐ^�̒��̏ꏊ�ɍs���ΐÂ��Ȏ����߂������Ƃ��\�ł��B���肪�Â��Ől�Ɛl�Ƃ̂����̂��߂��Ƃ�C�ӌ��̂Ԃ��荇���Ȃǂ����ɂ��݂܂��B�����̂悤�Ƀj���[�X�ŕ���Ă��鐭���Ƌ��̖��B�l�Ԃ��n��o�����n�����g���Ƃ����ЊQ�B����������肩�痣�����̂͂��̎ʐ^�̕��i�̂悤�ȏꏊ�������Ǝv���܂��B �@�@�@ �@�i�������͈��p�҂ɂ��j |
| �y�P���I���i�K�ł̊��z�z �@���̎ʐ^�̓A���X�J�̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�X�т̒��ɂ���Ƀ��[�X���������݂ɗ��Ă���ʐ^�ł��B �@���̎ʐ^�̒��̓̃��[�X��e�q�Ƃ��Č���ƁC��e�̌���q�ǂ������Ă����Ă��܂��B�q�ǂ��̕��͏��߂Čɐ������݂ɍs�����ߏ��X�I�h�I�h���ĕ�e�ɂ��čs���Ă��܂��B�����������߂Ă��炯�̎q�ǂ��ɂƂ��āC�X���ʂ��C�܂ōs�����͐V�N�ł��B�X�̒��ł��������������Ƃ̂Ȃ��q�ǂ��͌̍L���ɋ����܂����B�����Ď���̕��i�ɂ��B��e�ɂƂ��Ă͎q�ǂ���A��Ă����̂�����C���G�ɒǂ��������邩�S�z�Ŏd������܂���B�ł��ꉞ�C�܂ŏo�Ă����̂����琅�͈��܂Ȃ��ƂƎv���C�I�h�I�h���Ă���q�ǂ������C�������ݎn�߂܂����B �@�̎���͋C�����̂����Â����ŕ�܂�āC���[�X�̐e�q��������������ݍ��ނ悤�ɐÂ��Ȏ��Ԃ�����Ă��܂��B�������ޏ����ȏ����ȉ����Â��ȐÂ��ȐX�̒���ʂ��Ă��܂��B |
�@�y�P���ɓ���O�̊��z�z�̉��������́C�w�K�҂̓���̉��l�ς��C�ʐ^��i�Ƃ̂Ȃ�����������܂܁C���͒��ɓ������܂��悤�ɋL�q����Ă���B�܂�w�K�҂̔F���͓���̈���o�Ă��Ȃ��B����ɑ��āy�P���I���i�K�ł̊��z�z�́C�ʐ^�̍ו��Ɏ���܂Ŋw�K�҂̊ώ@���s���͂��C���̌��ʂƂ��Ďʐ^��i�̑n��o�����E�Ɋ��S�ɐZ�肫���Ă���l�q������������B�����ɕ`����Ă��郀�[�X�̐e�q�W�͐��X������������B
�O �����̂܂Ƃ߂ƍ���̉ۑ�
�@�P �����̂܂Ƃ�
�@
�@�_�҂́u���w�I�F���v���C�u�قȂ��̗v�f�i���t�j�Ԃɐ��܂��w�x�ɂȂ�������o���C������C���[�W�ŕ�U����́v�ƒ�`���ĂR�N�ɓn���ċ�̓I�Ȏ��H���s���Ă����B����͑����x�j���̐����u�W�I�ȔF���̗́v��C�ǎҘ_�̗��_�I��Ղ�������H���t�K���O�E�C�[�U�[���́u�s�ׂƂ��Ă̓Ǐ��v�̋L�q���e�ɋ������ϓ_�ł���B���̎��H�̉ߒ��ŁC���t�ƌ��t�̂Ȃ�������m���ɔF������w�K�����Ƃ��āC���n���L�[���[�h�T���C����n�쓙���ʒu�Â��Ă����B
�@����ȕ��͂�ǂނƂ��C�w�K�҂͕��͒��َ̈��ȗv�f���֘A�Â��鎋�_�����o�����C�ꕔ�̗v�f�݂̂�ΏۂƂ��ĉ��߂��Ă��܂��X��������B��������C�w�K�҂̎����Ă������I�ȉ��l�ς�F�������̂܂܍�i���߂Ɏg�����Ƃ��ł��邩�炾�B�������C���̂悤�ȓlj��̂�����ł͍�i������̂܂��~�߂����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B����I�ȔF���̂�������ӎ������C�g�ݑւ��邱�Ƃɂ���Ă����C��i���E�𐳊m�ɓǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��B����͍l�����̈قȂ�l���̐S�̒��̐��E����e���邱�ƂƓ������B���̎�i�Ƃ��āC���ނ��璊�o�����L�[���[�h���g���āC���̐��E�ς�ۂ����܂܁C�����n�삷�邱�Ƃ��s�����B�܂�C�u�����v���ƂƁu�ǂށv���Ƃ���̉����C���ޗ����̐[�������Ȃ����w�K�����Ƃ��ĕ���n����ʒu�Â����̂ł���B
�@�܂��C����̔��\�ŏЉ�����H�ɂ����ẮC���ނ𐳊m�ɓlj����C���ސ��E������̂܂�e���邱�ƂŁC�t�ɋ��ފO�̓��퐢�E���V�N�Ȃ܂Ȃ����Ō��߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ƃ��������𗧂Ă��B��̓I�ɂ́C���ފO�̌����̈ꕔ�ł���ʐ^��i���C�{���́u���ҁv�ł���ʐ^�̍�҂̎��_���猩�ߒ����C����ꉻ���邱�ƂŁC�g�̉��̌������u�����v����ԓx�̊l����ڎw�����B
�@����ɂ͋��ޓ��̃L�[���[�h��Ǝ��̕���Ƃ��čč\������ۂɁC�w�K�ҌX�Ɏ���̓��ʂ�[�����߂�p�������܂�Ă���\�����w�E�ł���B���̓���ϓ_�ł͂��邪�C���̂悤�ȋ��\�e�N�X�g�̎��u���ȔF���v�̓����ɂ��Ă��Nj����Ă����\��ł���B
�@�Q ����̉ۑ� �|�L���_�I�ϓ_����̘g�g�ݍč\�z�|
�@
�@PISA2000�N�̖��u�������v���N�_�Ƃ��āC�����ƈقȂ���̂̌��������鑼�҂̗���ɗ����Ƃ̓���ƁC������\�ɂ���u���w�I�F���v�̌��p�ɂ��ĒT���Ă����B�w�K�̗l�X�ȏ�ʂɂ����āC���t�ƌ��t�����߂����킹�C�����I�Ȍ��t�̂Ȃ���|���\�e�N�X�g�|���������ɑn��o���B�����ǂ݉������Ƃ��C�u���w�I�F���v�̊l���ɂȂ���B����͓���̐g�̉��́u�����v���C����ς��̂āC�����̂��̂̌�����g�ݑւ��Ȃ���F�����邱�Ƃɂ��Ȃ���B
�@���̂悤�Ȋϓ_���������g�g�݂Ƃ��ċL���_�͗L���Ȋϓ_�̈�ł���B
�@���N�O����L���_�ڈ��������ȏ����ނ���������B�_�҂����Z����Ŏg�p���Ă��铌�����Ђ́u���I���ꑍ���v�͕]�_�̈ꕪ��Ƃ��āq�L���_�r�Ƃ����Ɨ��������ڂ�ݒ肵�C�|�����q�u������Ƃ������t�v�C�r��ÕF�u���̂ƋL���v�ƂQ�̋��ނ�z�u���Ă���B���ꂾ���łȂ��q���ꕶ���_�r�q����N�w�r���̊ϓ_����C�S�]�_���ނ̔������u����v�Ɋւ��e�[�}�ݒ�ƂȂ��Ă���B���ޓ��e�Ƃ��Ắu�L���_�i����_�j�v�͑��݉��l�𑝂�����C�펯�I�ȋ��{�̈�ɂȂ����Ƃ���������B�������C�L���_�I�ϓ_�́C����Ɋւ��闝�_�ł���Ȃ���C����Ƃ������Ȃ̋�����@�ɖ��m�ɔ��f����Ă���Ƃ͌�����B
�@���������勳���w��w�@�ɍ݊w���ɘ_�҂��������C�m�_���u�w���ȔF���x�𑣂����ꋳ��̌����v�̊j�ɁC�L���_�⌻�ۊw���������B���ޓ��e�Ƃ��Ă̋L���_�⌻�ۊw������������鍡�C�u���w�I�F���v�̘g�g�݂��C�L���_�̊ϓ_����č\�����������Ƃ��������ł���B�@
������
�@�{�_���͑O�C�Z�ɂ�����_�҂̎��H�𒆐S�ɍ\�������B�u���w�I�F���v�̘g�g�݂́C�勳���w��w�@�ɍݐЂ����ۂɏ������C�m�_���u�w���ȔF���x�𑣂����ꋳ��̌����v�W�����ċL�q���Ă���B�i�_�҂̃C���^�[�l�b�g��̂g�o�u�F�j�̏Z���v�ɘ_����S���Љ�Ă���̂ŎQ�l�ɂ��Ă������������B�j
�@�Ō�ɁC���̐ق��_���ɑ��āC��N�x�Ɉ��������Ĕ��\����@���^���Ă����������勳���w�̐搶���Ɋ��ӂ������܂��B
�@�Q�O�O�W�N�W���Q�R���i�y�j �@����
�s ���p���� �t
�i���P�j���H���t�K���O�E�C�[�U�[�w�s�ׂƂ��Ă̓Ǐ��x244�Ł`245�� 1982�N3��24���@��g���X
�i���Q�j���c�b��ҁw���Ȉӎ������̌��݁x43�� 2006�N3��30�� �i�J�j�V���o��