第二節 吉野弘『I was born』の授業 『現代詩の授業』
本節においては、足立悦男氏の『現代詩の授業』から、吉野弘氏の作品『I was born』を教材とする授業実践の分析を行う。この実践は、昭和四十九年九月十八日に、足立悦男氏が当時継続的に授業担当していた広島大学付属高等学校の高校二年生を対象に実施された。記録の全文は本論文資料編に資料②として記載する。
前節の中学生を対象とした教材『するめ』の授業の分析結果を受けて、考察のポイントを以下の点に絞り込む。
A 作品を構成する要素間の接合可能性の暗示。(「空所」の演出)
B 生徒に対する情報提示と、「空所」とのバランス操作。
C 生徒の読みの過程に即した授業展開。
A~Cすべて「教師から生徒への働きかけ」を中心に設定している点については、『するめ』実践の分析と同じである。
Aは、第一章から繋がる「自己認識」のテーマを直接受ける考察ポイントである。第二章第二節において考察したように、「イメージ」は、セグメント間の非日常的な結合可能性である「空所」を補填する働きを持つ。セグメント相互の非日常的な結合が、反作用として「現実」の真の姿を浮き彫りにする。ここでは、特に板書に着目し、教師の働きかけによって作品の触発力がどのように高められているかを考察する。
BやCは、Aを補助する機能に関する考察ポイントである。
まずBについては以下の通りである。「空所」は非現実的結合可能性であるため、我々が日常使用しているコードが使えない。そのため、生徒が自力で「空所」を見出すことができず、セグメント間の関係を無視して、日常的価値判断の範囲内にとどまってしまう可能性がある。そのため教師は、全体の接合可能性に関する情報を生徒に提示し、生徒が作品世界に入っていくため手助けをする必要がある。しかし、情報が多すぎるとき今度は生徒の読みがその情報の方向に固定されてしまう可能性がある。指導者がそのバランスをどのようにとっているかを考察する。
Cについては、「空所」の持つ触発力をより効果的に発現させるためには、生徒の「読み」の過程に可能な限り接近した指導が望ましい。これは、単に「生徒の主体性を尊重する」といった目的ではなく、作品世界の持つ「共通の地平」に、生徒のいる位置から効果的に接近させていくことを狙う指導といえる。指導者が生徒の「読み」をどのように授業展開に反映させているかを考察する。
教材『I was born』及び副教材『父』を以下に記す。(以下の引用は『現代詩の授業』からの抜粋であり、①~④の番号は足立悦男氏による。授業の便宜上の仮の番号である。)
I was born 吉野 弘
① 確か 英語を習い始めて間もない頃だ。
或る夏の宵。父と一緒に寺の境内を歩いてゆくと青い夕靄の奥から浮き出るように 白い女がこちらへやってくる。物憂げに ゆっくりと。
女は身重らしかった。父に気兼ねをしながらも僕は女の腹から目を離さなかった。頭を下にした胎児の柔軟うごめきを 腹のあたりに連想し それがやがて 世に生まれ出ることの不思議に打たれていた
女はゆき過ぎた。
② 少年の思いは飛躍しやすい。その時 僕は〈生まれる〉ということが まさしく〈受身〉である訳を ふと諒解した。僕は興奮して父に話しかけた。
─やっぱり I was born なんだね─
父は怪訝そうに僕の顔をのぞきこんだ。僕は繰り返した。
─I was born さ。受身形だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ。自分の意志ではないんだね─
その時 どんな驚きで 父は息子の言葉を聞いたか。僕の表情が単に無邪気として父の眼にうつり得たか。それを察するには 僕はまだ余りに幼なかった。僕にとってこの事は文法上の単純な発見に過ぎなかったのだから。
③ 父は無言で暫く歩いた後、思いがけない話をした。
─蜻蛉という虫はね。生まれてから二、三日で死ぬんだそうだが それなら一体 何の為に世の中へ出てくるのかと そんな事がひどく気になった頃があってね─僕は父を見た。父は続けた。
─友人にその話をしたら 或日 これが蜻蛉の雌だと言って拡大鏡で見せてくれた。説明によると 口は全く退化して食物を摂るに適しない。胃の腑を開いても 入っているのは空気ばかり。見ると その通りなんだ。ところが 卵だけは腹の中にぎっしり充満していて ほっそりした胸の方にまで及んでいる。それはまるで目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが 咽喉もとまで こみあげて居るように見えるのだ。淋しい 光りの粒々だったね。私が友人の方を振り向いて〈卵〉というと 彼も肯いて答えた。〈せつなげだね〉。
そんなことがあってから間もなくの事だったんだよ。お母さんがお前を生み落としてすぐに死なれたのは─
④ 父の話のそれからあとはもう覚えて居ない。ただひとつ痛みのように切なく僕の脳裡に灼きついたものがあった。
─ほっそりした母の 胸の方まで 息苦しくふさいでいた白い僕の肉体─。 (注1)
父 吉野弘
何故 生まれなければならなかったか。
子供が それを父に問うことをせず
ひとり耐えつづけている間
父は きびしく無視されるだろう。
そうして 父は
耐えねばならないだろう。
子供が 彼の生を引き受けようと
決意するときも なお
父はやさしく避けられているだろう。
父はそうして
やさしさにも耐えねばならないだろう。 (注2)
足立悦男氏はこの授業実践のテーマを次のように設定している。自我との確執に悩む高校生にとって、〈父〉との関係は深い関心事である。そういった高校生に、吉野弘氏の描く〈父〉を真正面から対峙させる。そして、詩世界の〈父〉体験を内面化させる。
『父』と『I was born』はどちらも、同じ詩集に収録され(詩集『消息』)、父と子の拮抗する関係性の厳しさを内包している。『父』がやや父親の側からの視点で書かれているのに対し、『I
was born』は子供の側からの視点で書かれている。従って、両者は相補的な関係にあり、教材、副教材として同時に扱うのに適している。実際の授業展開も、二詩の比較を授業の前半と後半に行い、授業展開を経て二詩の内容が連関していくように工夫されている。
『I was born』の実践は二学期だが、『父』は一学期の既習教材である。本時は『父』の復習から始まる。『父』における〈父〉と〈子〉の対立構造を浮き彫りにした板書が、『I was born』における〈父〉と〈子〉の対立構造とせめぎ合いを見せる。『I was born』に対する授業展開は、全体の印象から始まって、各連を一つずつ対象としていく。最後に、二詩の比較をした後、吉野弘氏自身の解説が紹介されて授業が終わる。『父』の段階では「生」に対して受身的な解釈に終わっていたものが、『I was born』を経た授業終盤には、「生」を積極的に肯定する方向へと変化している。
先に述べたように、本論文における分析は、板書を観点の中心に据えて行う。以下は、そのような観点に基づく授業展開表である。
(『I was born』の授業展開表)
| 段落 | 対象内容 | 指導内容 | 板書とその内容 |
| ① | 二詩の比較 | 〈導入〉・二詩の題名から受けた印象 | |
| ② | 『父』 | 〈展開〉 ・奇習教材『父』の復習、生徒の意見 |
(板書1)『父』の内容の構造図 →予定的 |
| ③ | 『I was born』全体 | ・詩から受けた最初の印象 | (板書2)大岡昇平『野火』からの生徒の連想 →(即時的・偶然的) |
| ④ | 第一連(全体) | ・第一連の色彩のイメージから、他の連の色彩のイメージへ展開 | (板書3)一、二、三、四連を貫く「白」のイメージ |
| ⑤ | 第二連 | ・第二連の内容の要約 ・書かれた時点の推察 |
(板書4)第二連における「父」と「僕」の比較と、問題点の明確化 →予定的 (板書5)「蜻蛉」と「母・僕」に関する生徒の解釈 →(予定的)+(即時的) 上半分 下半分 |
| ⑥ | 第三連 | ・父親が「蜻蛉」のエピソードを持ち出した理由 ・「『蜻蛉』のエピソードは唐突では?」→揺さぶり |
(板書5)「蜻蛉」と「母・僕」に関する生徒の解釈 →(予定的)+(即時的) 上半分 下半分 |
| ⑦ | 第四連 | ・第四連と他の連の関係 | 生徒の意見から(板書5)の補足 |
| ⑧ | 二詩の比較 | ・二詩の比較 | |
| ⑨ | 全体 | 〈まとめ〉・教師視点でのまとめ。 ・作家自身の解説の提示 |
(板書6)吉野弘氏自身の解説の簡単な構造図 →(予定的) |
段階①においては、二詩を比較する観点から、題名から受ける印象を生徒達に発表させている。これは〈導入〉としての指導であり、板書もない。授業終盤の段階⑧で再び二詩を比較するための準備といえる。この段階での生徒の発言は「とても厳しい関係」「キザだなってことだけ」などで、表層的理解にとどまっている。
段階②においては、既習教材『父』の復習・整理がなされている。ここで板書1が提示されている。この板書は『父』の内容を構造的に捉える板書である。(板書1~6及び罫線内の引用は資料編資料二からの抜粋)
| Ⅰ 何故生まれねばならなかったか。 〈少年〉 〈父〉 Ⅱ ひとり耐える (無視) ─ 耐える ↓(成長) ↓ Ⅲ 生を引き受ける決意(避ける) ─ 耐える |
(板書1)(引用者注・板書番号は引用者による)
生徒の比較的自由な見解「父への反発」「この少年にはついていけない」などを引き出した後、それらを整理する授業展開に持ち込む。細かい質問の積み重ねでやや誘導的に詩の構成を板書1に仕立て上げている。(資料編資料二参照)補助教材としての『父』の位置を時間をかけずに明確化する意図が見える。
本教材『I was born』との結合可能性を持つのは「少年」と「父」の対比構造と、「生」という言葉である。さらに「ひとり耐える」「引き受ける」などの、「少年」の態度としてネガティブなイメージを持つ語句についても、他の展開との結合可能性を持つ。これらについては展開に沿って考察していく。
段階③においては『I was born』についての最初の印象を発表させている。「題のつけかたがうまい」「なんてたあいのない少年だろう」など依然として生徒の読みは表層的である。
それら生徒の「初読の印象」として出てきた意見の中から板書として採用されたのは、大岡昇平の『野火』への連想内容である。『I was born』自体に関する他の生徒の意見を対象とせず、一生徒が指摘した『野火』の中のことば「人生は偶然に生まれて偶然に死ぬという、二つの偶然の間にある」を『I was born』についての最初の板書としている。授業展開としては一見奇異である。
| 生の偶然性 ─ 生の責任 (野火) |
(板書2)
これは即時性・偶然性の高い授業展開といえる。この即時性・偶然性が、本論文題四章における「質問授業」の分析の際も重要な観点となってくる。授業展開が生徒にとって予測可能なコンテクストにある時、教材の持つ触発力はその機能を十分に発揮できない。即時性・偶然性を持つ授業展開は、生徒の読みの過程に的確に対応すると同時に、展開そのものに「空所」を作り出し、生徒の能動的授業参加を促す。注意すべきは、この段階で黒板には板書1と板書2の二つしか書かれてない点である。しかも授業記録を参照する限り、特に板書1と板書2を繋げるような発言は指導者にはない。生徒達の「自由な」発言の中から、対象教材外の『野火』に関する連想を、指導者は黙って板書している。
即時的・偶然的とはいえ、全く必然性のない展開は、むしろ生徒の意欲を低下させる。これまで述べてきたように、何かに結実する可能性を持たない活動は人の心を疲弊させる。また「空所」は結合可能性としての存在である。板書2においては「生」と「責任」という言葉が板書1との関連性を生み出している。「生」は全体を貫くテーマでもある。「責任」は板書1の「引き受ける決意」と明らかな連関を持つ。従って、板書1と板書2の間には結合可能性としての「空所」が明確に成立している。黒板を見る生徒達の心に、様々なイメージを喚起する機能を持つ。
即時性・偶然性を持つ授業展開は、本節冒頭で設定した考察ポイントAの「『空所』の演出」や、Cの「生徒の読みの過程に即した授業展開」に相当する。
段階④においては、第一連に関して色彩のイメージがやや誘導的に問われている。第一連の「白」のイメージに関連して他の連のイメージが問われ、それら全体の構造が板書3として提示されている。
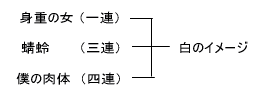
(板書3)
第一連を対象としながら、他の連に展開していく過程は、予定的な展開といえる。これは全体の構造を生徒に示すことによって、作品の「共通の地平」を暗示する効果がある。しかも、〃色彩〃というイメージしやすい観点から作品の全体構造に切り込んでおり、生徒の作品世界へのアプローチを補助する意図に基づくと考えられる。
板書3については、板書1、板書2との関連性は特に見いだせない。問いの質は生徒からの限定された解答内容を期待できるものであり、板書2がきわめて偶然性の高い内容であることから、必然的な内容による授業展開の安定化を狙ったものと考えられる。これは本論文考察ポイントBのバランス操作に相当する。
段階⑤の対象箇所は第二連である。ここでは「第二連の中心的な内容を要約すると?」という、比較的単純な問いで内容に切り込んでいる。そして、誘導的に特定の生徒に第二連の構造を語らせ、それを板書している。この板書は明らかに予定的である。
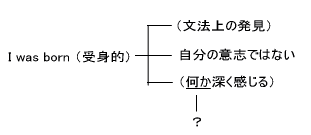
(板書4)
一見してわかるように、板書4は「僕」と「父」が明確に対比されている。これは『父』に関する板書1と構造的に似通っており、黒板上にネットワークを作っている。また「自分の意志ではない」という語句は、板書2の「偶然性」と連関を持っている。板書中の「?」は次の授業展開を暗示している。
ここまでの展開でわかるように、 板書1~4はそれぞれ独立し完結した構造を持っている。それらの連関は明確には示されてはいない。四つの板書の実際の位置関係は記録にないが、展開を見る限りは一見無作為に黒板上に並べられていると考えられる。繰り返し述べてきたように、「空所」は結合可能性としての断絶箇所である。黒板上の四つの板書が、結合可能性を内包した状態で、一見何の脈絡もなく並べられている。
以上の分析を図示する。
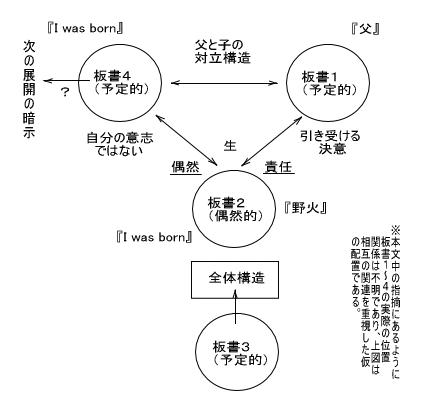
右の図からわかるように、予定的な板書である1、4、3の関係構造を2が異なる角度から広げている。単に授業内世界を広げるだけでなく、結合可能性としての「空所」が存在することに特徴がある。それぞれの板書がそれぞれの板書に対して関連する内容を持つ。そして右図の矢印は実際の板書には存在しない。そこに「空所」が生まれている。板書間の結合可能性が生徒のイメージ喚起を促すのである。
「空所」は本来文芸理論に関する概念だが、ここでは授業展開の一部として成立している。「文学のシステムを持つ授業」と言える。教師とテクストと生徒の「三者」の協力によって授業という作品が構成されている。
段階⑤にはさらに「この詩は〈僕〉のいつの時点で書かれたと推察できるか。」という問いが存在するが、本論文の枠組みからは特に言及すべき点はない。
第三連を対象とする段階⑥は、以下の限定された問いを中心に授業展開されている。(罫線内は資料編資料二からの抜粋である。)
| T この連は〈蜻蛉〉のエピソードが中心だね。一、二連と関連づけて、その位置づけをはっきりさせるために、つぎの一点だけ考えてみてください。父親は〈僕〉に、何のためにこのエピソードをもち出したのだろうか、という点です。 |
これに対して生徒は「〈父〉は〈蜻蛉〉のせつない感じを母のイメージとダブらせて何かを話して聞かせたかったのだ。」と答えるが、その解答中の「何か」をさらに発問として授業展開させている。この時の「その何かってのは、黒板にも『?』をつけておいたが、何だと思う?」という問いかけは、板書4での問題提起である「?」を直接受けた発問設定である。偶然的でありながら予定された展開といえる。しかし、板書5として採用した生徒の発言「〈蜻蛉〉の死は母の死に繋がるから、生と死の交代、さらには人間の運命のようなもの」は、第三連及び第四連の構造を明らかにしながらも、偶然的要素をも内包している。

(板書5)
板書5の上半分は、板書3において既に暗示された内容の確定である。これは指導者の側からは予定された展開といえる。しかし、下半分「人間の運命」については、極めて偶然性の高い展開から生まれた板書といえる。ただし少々他の要素との繋がりにかけるといった印象は否めない。そのためか板書の直後に指導者は生徒達に対して「揺さぶり」をかけている。
| T それにしても、わたしにはこの〈蜻蛉〉のエピソードは、一、二連とつづけて読んでくると、少し唐突じゃないかという気がするんだが……。 |
それに対して、一人の生徒が板書1に結合する発言をしている。
| P21 そう。その母の死とひきかえに〈僕〉は生まれたという関係が、父と子の関係の、もう一つの別の関係としてあるでしょう。それを父として偶然性としてじゃなくて、偶然ってのは、初めの方でP13君が出したことばだけど、それからP20君のように、人間の運命的なものだと言ってしまえば、それまでだって気がするんです。……(かなり次のことばをさがしあぐねている……そうじゃなくてね、生を引きついでいるという感じ。 |
右の発言中の「生を引きついでいるという感じ」は、作品『父』に関する板書1の少年の側の「生を引き受ける決意」に明らかな関連性を持つ。授業展開における生徒による「共通の地平」の発見である。この発言は詩の解釈に関する教室の雰囲気を決定づけており、次に指名された生徒もその意見に単純に同意している。
授業のクライマックスともいうべき段階⑥は、そこまでの各段階の板書の結合結果として、必然的に成立していることがわかる。しかも、その解釈は教師による押しつけではなく、生徒の「空所」を補填する「イメージ」によって生み出されている。
段階⑦、段階⑧については、段階⑥において既に「読み」の方向性が確定しているためか、それほど大きな動きは見られない。各段階を比較的あっさり通過しているのは、授業の残り時間との兼ね合いもあったのかも知れない。
段階⑨の〈まとめ〉は教師による総括である。段階⑥での「生を引き継いでいるという感じ」などの発言について、教師の視点からの意味づけを行っている。その後に、吉野弘氏自身の解説を紹介し、その要点を板書している。
| 生に負い目を感じていた自分 ↓ (死生観の変革) 生が死を圧倒しているものと感じる |
(板書6)
この板書は授業全体の〈まとめ〉ではない。直後に「作者といえども、その詩を前にしては一人の読者です。だから、この詩をどう受け止めるか、それは各自の今後の体験によって決定すればよいと思う。」と説明していることからも、生徒達に対する最後の「揺さぶり」を狙ったと考えられる。
ただしこの板書内容については、ここまでの授業展開から浮いているといった印象は否めない。指導者の意図しては『父』の内容が「耐える」「生を引き受ける」といったやや受身的な内容を持つので、それを「生が死を圧倒」といった内容が示すように、より能動的な方向に引き上げていく効果を狙ったのかも知れない。それでも、授業の他の要素との関連については明らかに説明不足であり、直後に終業のチャイムが鳴っていることからも、時間が足りなかった可能性は高い。
以上が『I was born』を教材とする実践の分析内容である。
特に前半部の授業展開に、「空所」を生み出すための様々な工夫が見られる。指導者自身の「読み」を展開の基盤に据えながら、生徒の「読み」の実態に即して板書を有効に活用している。板書は単に授業の流れを作り出すだけでなく、各段階の考察において生徒を触発する材料として提示されている。板書一つ一つは完結した構造を持っており、表面上は固定的な関連性を持たない。しかし、一つ一つに伏流ともいうべき語句の関連を持っている。それが、授業展開上の「空所」を作り出し、生徒のイメージを喚起している。
生徒は「空所」をイメージによって補填する過程で、「父」や「生」に関する日常的な捉え方を揺さぶられ、それらの意味・価値を再認識・再構成していこうとする態度を持つ。単に自分と異なる価値観などに触れるだけではそのような態度は生まれない。多様な価値から常に過剰な刺激を受け続ける現代の生徒達にとって、教室で与えられる価値は、彼らの生活のほんの些細な一部分でしかない。獲得済みの多くの価値にもう一つの価値を付け加えるに過ぎない。しかし、言葉と言葉の関係に生まれた「空所」をイメージによって補填する作業は、既に獲得している価値群の構造を揺さぶり、それらの実態を浮き彫りにし、変革可能な存在にする効果を持つ。(第二章第二節参照)
次章への考察ポイントとして特に注目されるのは、板書2や板書5などにみられる即時性・偶然性の高い展開である。これらは生徒の「読み」の過程に対応するだけでなく、授業展開に意外性を持たせ、生徒の意識を自動化から引き剥がす効果があると考えられる。
本節においては、足立悦男氏の詩教育の実践を対象として、本論文の枠組みとの関係を観点に分析を試みた。
次章では、この章の分析結果を踏まえて、論者自身の実践「質問授業」について考察する。
《第三章第二節》
(注1)足立悦男『現代詩の授業』211~213頁 昭和五十三年十一月十日 文化評論出版
(注2)(注1)に同じ、209~210頁
目次に戻る