実践事例(平成18年度)
① 単元名 ひびきあう言葉と心 〜詩創作、キーワード探しからリライトまで〜
② 対象学年 1〜2年(4クラス 160名)
③ 実施期間 平成17年5月〜平成18年11月
④ 単元設定の理由
小学校時代から40人41脚等の活動を通してのびのびと育てられた学習者達は,入学当初から他者や学校行事に対する積極的な姿勢を持っていた。しかし,その積極性故に他者との距離を測りかね,言葉によって傷つけたり,また傷つけられたり等の小さな衝突が絶えなかった。中学校生活も半ばを過ぎ,本校の最も特徴的な活動であるSGEの取り組みを通して,学習者一人一人が少しずつ自分と周囲の他者との関係の網の目を意識し始めた。そして,「言葉」が,自分と他者とをつなぐ存在であることにも気づき始めていた。
このような発達段階にある学習者に対して,平成17年6月から平成18年11月までの1年半に渡り,「文学的認識力を育む」という観点のもと,授業実践を行ってきた。文学の装置である「異化」や「空所」が効果的に機能する学習活動を,様々な単元を貫く傍系的観点として日々の実践に組み込んできた。したがって帯単元「ひびきあう言葉と心」は,帯単元的な取り組みである。まず平成17年6月(1年次)に「現実を壊せ!」という題目のもと,四人班による詩のリレー創作をさせた。次にその半年後の平成18年1月(1年次)に生徒個々に本格的な自由詩の創作を行わせた。平成18年6月(2年次)に「ゼブラを揺さぶる言葉を探せ!」という題目で,ハイム・ポトク『ゼブラ』(金原瑞人訳)を教材に「キーワード(心情表現)探し」を行い,夏休みをはさんで平成18年9〜10月(2年次)に,抽出したキーワード(心情表現)を使って『ゼブラ』のワンシーンをリライトさせた。(平成18年9月には映画『ハウルの動く城』と『ゼブラ』との比べ読みも行っている。)
帯単元「ひびきあう言葉と心」の中心に位置する教科書教材『ゼブラ』は,学習者と同世代の主人公ゼブラが,自動車事故で傷ついた心を,他者との心の交流を通して癒していく物語である。準主人公ともいうべきウィルスンも,ベトナム戦争で友と左手を失い,傷ついた心を癒そうとよすがを求めてさまよいながら生きている。同じような境遇にある2人が出会い,お互いの心に興味を持ち,それを理解しようとする過程で自然に2人の心が癒されていく。以上のように『ゼブラ』は主人公2人による相互カウンセリングともいうべき物語であり,自己と他者とのつながりを認識し始めている学習者の,発達段階に適した教材だといえる。また作品中,「ヘリコプター」や「ゼブラ(しまうま)」等のキーワードに関する記述は作者によって最小限に抑えられており,読者のイメージの喚起を促す「異化」や「空所」等の文学の機能が働きやすくなっている。「文学的認識力」の観点に適した教材だといえる。
指導にあたっては,本校の研究主題である「協働の学び」と教科の目標である「文学的認識力」との接点を強く意識する。まず平成17年の詩創作においては,本来個別の活動であるべき詩創作を4人班でのリレーで行う。詩創作はそれ自体教育的価値のある活動だが,ここでは一見無関係に見える言葉と言葉の間につながりを見出すことを主目標にする。他の学習者が無作為に提示する言葉と言葉の間にコードを見出し,一定の意味を持つ「作品」として構成する。これは詩創作で学習者が陥りがちな,既成の「詩的」表現をただ想起し書き写すだけの活動を回避するためでもある。また読解教材に対する「キーワード探し」の際,教材中の全ての言葉につながりを見出す訓練にもなっている。半年後の学習者個々による詩創作の際にも,類型表現を避け,言葉と言葉の間に非日常的なつながりを見出すことを活動の中心に据える。そのような認識のあり方を小説教材『ゼブラ』の読解に生かし,「心情表現」と「キーワード」を関連づけながら抽出させ,4人班によって心情表現グラフを作成させると同時に最重要キーワードをグラフ上の任意の位置に貼り付けさせる。最終段階として,ゼブラがウィルソンの個人的な思い出であるヘリコプターを芸術作品として創作する場面を,ウィルスンの視点でリライトさせる。その際,「キーワード(心情表現)探し」で抽出されたキーワードを使ってカードを作り,リライトの土台となる「キーワード関連表」を作成させる。
以上のように本単元(帯単元)においては,言葉と言葉が教室という場で響きあい,学習者の意識内で「作品」となって結実することを目指す。これは本校国語科の2年次の目標である「それぞれの認識の活動要素についての知識を生かして,より豊かに作品を味わう」に合致する。その際,教室という場の「協働の学び」の機能を効果的に利用し,共同作業の過程でそれぞれの視点をせめぎ合わせ,昇華させた結果としての「読み」の獲得を目標とする。何かの価値を教条的に伝達するのではなく,生徒個々が教材内の言葉をありのままとらえることで,主体的に自分や自分の周囲の世界を見つめる姿勢〜文学的認識〜を獲得させることをねらう。
⑤ 学習指導目標
・ 一つ一つの言葉を様々な視点で関連づけることで,言葉に対する見方や考え方を広げようとする態度を育てる。(関心・意欲・態度)
日常生活における身の回りの言葉と言葉や,教材内の「心情表現」や「キーワード」等のつながりをありのまま捉えさせ,教材に内包された「文学的認識力」を身につけさせると同時に,自分や自分の周りの現実をありのまま見つめ,自らの生き方を考える態度を養う。
・ 選んだキーワードを発表しあい,自分のキーワードと他の学習者のキーワードのつながりを考えながら聞く態度を身につけさせる。(話す・聞く力)
・ 選んだキーワードをグラフ化したり,キーワードを利用してリライトすることができる。(書く力)
・ 他者の意見を参考にしながら、作品世界とそれを構成する言葉をありのままとらえる態度を身につけさせる。 (読む力)
・ 文章中の特徴的な表現に着目し,言葉に対する感覚を豊かにさせる。(言語事項)
⑥ 学習指導計画(総時間数16時間)
〔1〕つぶやき学習(4時間)
〔2〕であい学習(3時間)
(1) 4人班での詩のリレー創作によって,言葉と言葉の非日常的なつながりを作り出し,出来上がった作品を 鑑賞しあう。(2)
(2) 個別の詩創作で,言葉と言葉の非日常的なつながりを使って自分の思いを表現し,出来上がった作品を鑑賞しあう。(2)
〔3〕たしかめ学習(7時間)
(1) 教材本文を通読し,ワークシートを使って「心情表現」及び「キーワード」を抽出する。 (1)
(2) 抽出した「心情表現」や「キーワード」を発表しあい,それらを4人班でグラフ化する。完成したグラフを教室全体で鑑賞しあう。 (2)
〔4〕みつめ学習(2時間)
(1) 抽出したキーワード(心情表現)間のつながりを意識しつつ,教材内容を理解する。 (4)
(2) ゼブラがウィルソンの個人的な思い出であるヘリコプターを芸術作品として創作する場面を,ウィルスンの視点でリライトする。「つぶやき学習」で抽出したキーワードを使って,リライトの土台となる「キーワード関連表」を作る。(2)
(3) それぞれの班のリライト作品を教室全体で鑑賞しあう。 (1)
〔5〕あゆみ学習
単元のまとめをする。 (2)
日常生活の中で単元で学んだ能力や態度を活かす。
⑦ 学習指導の実際
文学的認識は文学作品だけに内包されているわけではない。目の前の現実をありのまま捉えることもまた文学的認識といえる。例えば桜の花を見るとき,我々は「はかない」という単語を思い浮かべる。しかしそれは時に単なる知識であるかも知れない。実際の桜の花を見て,その美しいピンク色を見,ごつごつした木の幹を感じ,花びらが散っていく様子を眺め,そこで初めて桜の花の「はかなさ」を理解したと言えるはずだ。これは例えば論説文にも言えることだ。ある論説文を読む時,言葉のつながり全体を捉えることができなければ,その文章を理解したとは言えない。文章中の言葉相互のつながりが難解だからといって,それを無視して解釈していては,正確に読解できたとは言えない。これまで出会ったことのない言葉のつながりであっても,日常的認識を超えてそれをありのまま理解しようとした時,初めて文章は本当の姿を読者に見せる。すなわち「論理力」も広義には文学的認識と言える。
そのような観点に基づき,一年次から「言葉と言葉のつながりをありのまま見つめる」ことを授業の傍系的目標として実践してきた。
〔1〕つぶやき学習
「4人班による詩のリレー創作」(その①)〜平成17年6月(1年次)〜
平成17年6月(1年次)に,4人班による詩のリレー創作を行った。詩創作は本来国語科教育においても高度な学習活動に位置づけられる。それを中学入学直後の導入の時期に,さらには4人班という学習形態で行ったことには理由がある。それは言葉と,それによって表現されるべき現実をありのまま見つめさせるということだ。
例えば何の指示も出さずに学習者に詩創作をさせると,独自性に富んだ作品が生まれる一方,既成の表現,例えば流行の歌謡曲の歌詞等をまねるようなケースも多くなる。これでは言葉と言葉のせめぎ合いから生まれる文学的認識は機能できない。これは読解においても同様であり,学習者が自分の日常的な価値判断の範囲内で登場人物の心情などを読み取り,都合の悪いキーワード等を無視してしまうケースが考えられる。これでは本来言葉と言葉のひびきあいから生まれてくるべき解釈にたどり着けずに終わってしまう。言葉と言葉の間に生まれる関係がたとえ非日常的なものであっても,そこにつながりを見出したとき初めて作品を理解したと言える。
4人班による詩のリレー創作は,学習者の意識を他の学習者の力を借りて日常的な表現から引きはがし,文学的認識に向かわせることを目的とした。「友達の力をちょっと借りて…現実を壊そう!」というテーマを設定し,まず「現実を壊す」ことの意味を説明した。吉野弘氏が著書『詩の楽しみ』で語っている「類型表現を壊す」ということについて「炎のつらら」という言葉を紹介して説明した。「炎」と「つらら」は本来正反対の性格を持つ。それらをひとつながりの表現として使うことで,現実を文学的認識で捉えることに成功している。たとえばそれは「冬の寒い日に朝日に照らされて燃えるように輝く氷のつらら」かも知れないし,あるいは「夜の闇を切り裂いて空に鋭く突き刺さる炎」かも知れない。どちらにしても「冷たい氷のつらら」や「燃えさかる熱い炎」等の日常的表現より,「炎のつらら」と表現する方が想像力をかき立てられる。
それらの説明の後,「友達の力をちょっと借りて…現実を壊そう!」というテーマを提示して,作業に入らせた。4人班を作った後,まず4人で書きたいものについて話し合わせた。書きたい物が決まったら,縦4行に区切られたプリントを配布し,まず最初の1行にそのテーマに関して自分なりに思いついたことを書かせた。1行書いたら4人班で時計回りにプリントを渡し合い,それぞれ隣の学習者が書いた1行目につながるように2行目を書かせた。同じように3回ずつプリントを隣に回し,1行ずつ全員が担当して,全ての行が4人それぞれによって書かれた4行詩が4つ出来上がった。
典型例と思われるものを幾つか紹介する。(実際には同じ題名の詩が4つ完成しているはずだが,本時では班から1つの発表に限定したため,資料としては残っていない。)
「のり」は比較的授業の狙い通りに仕上がった例である。最初の「のりのりのりののり」を書いた学習者は遊び心いっぱいのようだ。次の行を担当した学習者は授業冒頭での説明「炎のつらら」を強く意識して,「時」と「ねばねば」という言葉の非日常的組み合わせを考え出している。3行目を担当した人物は,2行目の表現やリズムを引き継ぎ,「時」を「青」に置き換えて表現している。「青」という単語がどのような発想によるものかは分からないが,「時」と「青」が横でつながりあい,不思議なハーモニーを奏でている。(例えば私などは「青春」という単語を連想する。)最後の「時間でかたまる」は,おそらくは2行目の「時のねばねば」からの連想であろう。単独では平凡なこの表現が,他の行の結びとしてしっかり機能している。
「のり」
のりのりのりののり
時のねばねば
青のねばねば
時間でかたまる「消しゴム」
えんぴつの花
緑のネコ
存在のない生き物
ポケットモンスターのどうくつ「時計」
まわる車
止まらないとげ
矢じるし
数字のギアチェンジ「くし」
やさしい牙
牛のマラソン
おにくのときょうそう
貞子のすいえい
「時計」では言葉がつながっている部分とつながっていない部分の違いがはっきり見える。1行目から3行目にかけては,それぞれの学習者が時計について思ったことをただ順番に並べていっただけでありつながりは見えない。しかし4行目の「数字のギアチェンジ」は,明らかに1行目の「まわる車」からの連想である。この作品に限らず,学習者一人ひとりが活動の意味を理解し始めた3,4行目当たりから,言葉と言葉のつながりが生まれている作品が多かった。
「消しゴム」は,2行目の「緑のネコ」から言葉の非日常的つながりが始まっている。3,4行目を担当した学習者が,困惑しながらもなんとか言葉をつなごうとしている様子がよく分かる。ただ「消しゴム」自体のイメージからあまりにかけ離れてしまった。
「くし」も,行間のつながりは生まれているが,「くし」自体のイメージからかけ離れてしまった一例である。さらに最後の1行「貞子のすいえい」は,3行目までの流れをリセットしてしまっている。ただこれは「くし」自体のイメージからあまりにかけ離れてしまった3行目までの流れを,「くし」そのものに引き戻そうとする学習者の密やかな抵抗であったのかも知れない。(恐怖映画のキャラクターである「貞子」はべったりとした髪の毛が印象的である。)
授業者としての反省点は多かった。特に,それぞれの行が全くつながりを持たないままただ並べられているだけといった作品が多く,文学的認識が機能する直前で本時が終了してしまっていた。
「4人班による詩のリレー創作」(その②)〜平成17年6月(1年次)〜
前時の反省を踏まえて,新たに以下のような指示を与えてリレー創作を再び行った。(他の3クラスは最初から以下の指示を与えて実施している。)
幾つかの作品を紹介する。
前の人が書いた行の内容をよく読んで,そこにつながるようなストーリーを考えよう。だから,最初の1行の担当者の責任が大きい。「炎のつらら」のように,一見矛盾しているようで書きたい物のイメージがよりよく読む人に伝わるような,世界中の誰も聞いたことのない自分達だけの言葉の組み合わせを発明してみよう。
「時計」①
時のはこ船
新しい土地を求めて旅に出た
途中で死んだ
しょうがないからやっぱり生きよう「時計」③
仲良し三人組
みんなが遊んでいた
あ,すれちがった…。
そして,また出会う。「時計」②
長い手と短い手の持ち主
かげのない不思議な存在
実在しない世界
みんなが天国さようなら「時計」④
はりがかちかちなっている
少し重たそうな長い針
必死に必死に働いている
そしてある日土にかえった
同じ題名の4つの詩は,全て同じ班の4人によって書かれた物である。ただし,一人一人の学習者が担当する行は,作品毎に1行ずつずれている。それぞれの作品のどの行を誰が担当したかという点については記録を残していない。しかし,一人の学習者が表現するイメージが,4つの作品それぞれで変化していることは確実に見て取れる。学習者のイメージが他の学習者の力を借りて,パターン化された日常的表現を破り去り,対象となっている現実を,新鮮なまなざしで捉えようとしている。また,班を一巡してそれぞれ一行目を書いた作品が完成して自分の手元に戻ってきたのを見て,学習者の意識はさらに揺さぶられる。自分の認識が,あるいは引き裂かれ,あるいは増幅され,他者によって新たな認識として生まれ変わっている様子を見る。
「雲」①
ふわふわ,わたがし。
昼なのにキラキラ輝く天の川
白い光
雲の上では,いつでも快晴。「雲」③
おもちゃの宝箱
楽しさいっぱい元気が出る出る!
あけてびっくり箱から雲が
飛び出した
青い空に散らばっていく「雲」②
空に浮かぶ白い生き物
動き回って形を変える
どこかでいつも見守って…。
いつもやさしくにらんでる。「雲」④
フワフワうかぶ白いあめ
風に乗って流れていく
追っても追っても追いつかない
あぁあ…。
だけどつかんで食べちゃった
また,それぞれ異なる表現を用いながらも,意外なほど共通したイメージを作りだしていることが分かった。例えば「時計」の最終行を比較すると,共通して「出会い」と「別れ」というテーマを含んでいることが分かる。人を待つことなく過ぎ去っていく「時間」のイメージであろうか。実施時期が1年次6月であり,中学入学直後の不安がにじみ出ていた可能性もある。
「雲」は比較的日常的なイメージの作品に見える。しかし使われている言葉の一つひとつに着目すると,一つひとつの作品が異なる認識のもとに書かれていることが分かる。ここでは詳説はしない。
「詩創作」〜平成18年1月(1年次)〜
4人班によるリレー創作から半年を経た冬に,学習者個々による詩創作を行わせた。その際以下のような指示を出した。
リフレインや対句的表現,韻などについては,学習済みではあったが,こだわらなくてもいいと指示した。これは学習目的を言葉と言葉のつながりに絞り込むためだ。
まず自分が書きたい物をなにか見つけてみよう。詩を書く時はなにか書きたい物が心の中で燃えさかってなければ駄目だ。でも,燃えさかったものをそのまま口にするのでは叫ぶのと変わらない。書きたい物について,一方では燃えさかったまま冷静な目で見つめてやらなければならない。その時,書きたい物をそのまま説明してはいけない。平凡な言葉をスロットマシーンのように適当に思い浮かべながら組み合わせてみる。するとある瞬間,偶然書きたい物とほぼ同じイメージを持つ言葉の組み合わせが生まれることがある。それを逃さず捕まえて紙に書き写す。あとは,4人班で創作したときのようにそこにストーリーを継ぎ足していく。つまり,書きたいことを説明するのではなく,同じ雰囲気を持つストーリーを考えるのだ。この方法の利点は,日頃は人に言えないような心の中の思いを,みんなの前で思いっきり話すことができることにある。さあ,思いっきり秘めた思いを言葉にしてはき出してみよう。
以下に幾つか,やや短めのものを中心に作品を紹介しておく。(論者のインターネット上のHP「熊男の住処」に生徒全員の作品全176編を掲載している。)
一つひとつの詩の詳説は省略する。(「白い怪物」を学習者が書いていた時,窓の外では雪が降っていた。)
「川の流れ」
あの日のままの記憶を
僕は今でも追いかけながら
川の流れは僕らを映し
さみしいけれど
なつかしい空
川の流れはつながった。「未来を探す」
真っくらな闇の中
きこえる音は心臓の音
やみに包みこまれ
不思議な街とその中で
私は1人 歩き続ける
「でんしゃ」
地面がゆれた
私をとり残して
人がゆれた
淋しく黙ったまま
私は窓の外を見つめて
まっ黒な空を
あざやかに色づけている「白い怪物」
次々に出てくる白い怪物
何人も何人もたおしても
次々に出てくる白い怪物
ようやく全員倒したと思っても
次々に出てくる怪物
ようやく全員たおしたら
死がいが ひらひらとまっていた。
どの作品も吉野弘氏の言う「類型表現」を見事に突き破っている。自分の心の中の想いや目の前の光景をありのまま見つめ,それを同じ雰囲気を持つ言葉の組み合わせに置き換えようとしている。この時,作品中の一つひとつの言葉は,単なる辞書的な意味を離れ,言葉と言葉のつながりだけが作り出す新しい意味を獲得している。既成の表現による説明的な文章では伝えることのできない学習者の生きた想いが,読む者に伝わってくる。
次時には,全員の作品をプリントにして配布し,鑑賞会を行った。4人班でそれぞれの作品に対する感想を発表しあい,班でベストと思われる作品を選出させ,クラス全体に紹介させる等の活動を行わせた。
〔2〕であい学習
「教材『ゼブラ』のキーワード(心情表現)探し」〜平成18年6月(2年次)〜
「キーワード(心情表現)探し」は,論者が日常の授業の際,主に各単元の導入段階にほぼ一貫して行っている活動である。もともとは,本文の一部分にこだわって全体を鳥瞰的に捉えることのできないやや国語の苦手な学習者に対して,本文内の言葉の一つひとつに引きあわせる目的で始めた活動だった。授業の導入段階で,論説文であればキーワード,文学作品であれば心情表現をそれぞれ学習者に抽出させ,その全てを黒板上に書き並べ,キーワード(心情表現)相互のつながりがわかりやすいようにしている。「キーワード探し」自体は,増淵恒吉氏の著作を初めとして,様々な文献にその方法が記載されており,特に目新しい活動というわけではない。
授業の際にはキーワード(心情表現)を以下のように定義づけ,学習者に示した。(以下の定義は前年度の研究紀要に記載した内容だが,論の展開上再掲しておく。詳細な解説については本校の前年度の紀要を参照していただきたい。)
キーワードの定義
心情表現の定義
① 本文中に何度も繰り返し登場する言葉。(否定語を伴うものも含む)
② 段落をまたがって使われている言葉。(否定語を伴うものも含む)
③ 同じ意味を持つ異なる言葉(表現)。
④ 一度しか使われていなくても,文脈上重要な意味を持つ言葉(表現)。
キーワードそれぞれは単体では辞書的な意味しかもてない。それが黒板上に並べられることによって,キーワード間に「空所」を作り出し,学習者のイメージを喚起する。黒板上にいわば詩的空間とも言うべき言葉のつながりを作り出し,学習者の文学的認識を促す。詩創作によって,一見関係がないように見える言葉の間につながりを見出す練習をした学習者の目を,ここでは読解に向けさせることを狙った。
⑤「うれしい」「かなしい」等のように,直接人の心を表現したもの。
⑥「手が震える」のように,動作や状態でありながらその人物の心がわかるもの。
『ゼブラ』は,教材研究の結果,キーワードも作品の展開上重要な役割を担っていることがわかった。黒板を上下に二分し,「響きあう『言葉』を探そう!」という題目のもと,心情表現とキーワードを学習者に挙手によって同時に抽出させ,黒板上に書き並べていった。段落構成は本文中に空行が二カ所あり,それをそのまま三段構成とした。板書する際にはゼブラの心情を黒板上部に,ウィルスンの心情を黒板下部に書き込んだ。アンドレアの心情はその中間である。
『ゼブラ』キーワード(心情表現)探しによる板書
ゼブラは,仕掛けの多い文学作品である。しかし作品中,言葉と言葉のつながりについての説明は最小限にとどめられている。つまり作品自体がたくさんの「空所」を最初から持っている。しかし,それら「空所」の存在は,一読程度ではなかなか理解できない。挙手によって黒板上にキーワードが書き込まれていくにしたがって,少しずつ「空所」の存在が浮き彫りにされていった。
最も大きな「空所」は,第二段と第三段の間の心情変化にある。第三段中盤までのマイナスの心情群が,なぜ第三段のハッピーエンドにつながっていくのかを,単純な論理構造で説明することはできない。それらを理解するためには,「想像力」や「しま馬」「ヘリコプター」等のキーワード群の助けが必要になる。それら全ての言葉の間に「空所」が存在する。左図の矢印の関係は,初読状態ではつながりの可能性さえ学習者によって意識されにくい。それを黒板上に視覚化し,「空所」が機能しやすい状態にするのである。
「教材『ゼブラ』の心情表現グラフ作り」〜平成18年6月(2年次)〜
「キーワード(心情表現)探し」をした後に,それらの言葉をつなぎ合わせて心情表現グラフを作らせた。これは「キーワード探し」と一体となった活動である。(「心情表現グラフ」の詳細については,本校前年度の紀要に記載してある。そちらを参照していただきたい。)この活動も4人班を用いて行わせた。40人学級10班それぞれに,A3用紙やマジック等を配布し,班毎に1枚のグラフを作らせた。グラフ内には,ゼブラとウィルスン両主人公の心情変化を折れ線グラフで書き込ませ,要所に心情表現を書き込ませている。さらに,班毎に最も重要と思われるキーワードを話し合わせ,グラフとは別の紙片に書き込ませて,グラフ上の任意の場所に貼り付けさせた。完成した班から提出させ,黒板上に貼り付けていった。
典型例を二つ紹介する。
4人班で作った心情グラフA
4人班で作った心情グラフB
心情グラフA,Bの最も大きな相違点は第二段から第三段にかけての変化をどう捉えたかにある。ゼブラもウィルスンも班ごとに解釈が分かれた。
ゼブラの心情が,事故で最も低い位置まで下がっている点については各班で一致した。多くの班が第三段のハッピーエンドに向かって上がったり下がったりをくり返しながらも左斜め上に向かって上がっていくグラフを描いた。中にはグラフAのように第二段でいったんゼブラの心情が最も低い位置まで下がるという解釈をした班もあったが,ラストのハッピーエンドにどうつなげるかで苦労していたようだ。
ウィルスンの心情についてはほとんどの班がグラフAのような解釈をした。しかし実施4クラスとも,ごく少数ではあるがウィルスンの心情がラストでややマイナスに傾くという解釈をとった班があった。これは奇をてらっているようだがそうではない。自分の辛い過去の象徴であるヘリコプターをゼブラから執拗に見せつけられたウィルスンが,むしろ心が傷ついていると解釈するのは,途中経過をよく把握した読みともいえ,初期の段階の読みとしては理にかなっている。
これらのグラフが,完成するにしたがって黒板に貼り付けられていき,黒板上で比較された。学習者は他の学習者の解釈と自分の解釈を心の内面でせめぎ合わせる。今回新しい試みだった最重要キーワードを心情グラフ内に位置づけるという取り組みは,この段階ではグラフとつながりを持つまでには至らなかった。しかしその後の授業展開で,そのキーワードの存在を強く意識させる効果はあった。
以上のように,「キーワード(心情表現)探し」に引き続いて,「心情グラフ」を作らせることによって,初読段階では見落としやすい言葉と言葉のつながりを意識させている。つまり文学的認識が読解においても機能しやすいような働きかけを行った。
次時において,各グループ毎に発表会を行い,それぞれの班の発表に対して感想を書かせている。
〔3〕たしかめ学習
「教材『ゼブラ』と映画『ハウルの動く城』の比べ読み」〜平成18年9月(2年次)〜
第一段から改めて読解を進め,抽出したキーワードを小出しにするような授業展開を通して,各登場人物の人間像が少しずつ明らかになっていった。ゼブラから自分の辛い過去の象徴であるヘリコプターの絵や模型を渡されるシーンをウィルスンの立場からリライトすることは,構想段階から単元の中心的目標だった。このシーンは,自動車事故で傷ついた左手と対決するゼブラの物語と,左手を失う原因となったヘリコプターと対決するウィルスンの物語が,同時並行的に記述されている。傷ついた二人が互いの過去を理解し合う過程で相手の過去に自分の過去を重ね合わせ,二人の共同作業でそれぞれの心を癒していく。もちろん以上のような説明は一つの解釈に過ぎず,必ずしも学習者にそのような理解への到達を目指させる必要はない。しかし,一見無関係に見える言葉と言葉の間につながりを見出す力である文学的認識が機能するためには,ゼブラの過去とウィルスンの過去をせめぎ合わせる視点が不可欠だった。リライト段階でそのような理解に到達していることが望ましかった。
そのような登場人物相互の関係を理解するための補助として,映画『ハウルの動く城』を鑑賞し,「比べ読み」を行った。『ハウルの動く城』は,人間関係に疲れて傷ついた心を持つ二人の男女が,お互いのことを理解し合う過程で心のエネルギーを取り戻していく物語である。作品中に魔法のドアが登場するが,それが開かれる度,二人はそれぞれの過去に導かれる。それは時には自分自身の過去であり,またある時には相手の過去である。そのような設定自体がたくさんの「空所」を持っており,鑑賞者のイメージを強く喚起するように働いている。
「比べ読み」では様々な効果が期待できるが,二つの教材の共通点を見出させるような活動の場合,学習者の解釈が当然その共通点に限定されてしまいやすい。「比べ読み」後の読解では,その共通点を足場にそれぞれの教材の解釈が進む。つまり,比べ読みの際,指導者がどのような教材を選定したかに指導者の恣意的解釈が反映され,それが学習者の主体的読みを阻害しかねないという弱点を持つ。
「ハウルの動く城」を鑑賞する際には,あえてゼブラとの共通点を探すようには指示せず,「キーワード探し」と同じような授業展開を用いて,「疑問点」を思いつく限り抽出させ,その一つひとつを板書していった。その全てをプリントにして配布し,そこから4人班によって最も印象的な疑問点を選ばせ,班ごとに発表させた。
「ハウルはなぜ心を取り戻すことができたのか」や「ソフィーはどうやって呪いを解いたのか」等の最も大きな疑問点に混じって,多くの班が「なぜお城がソフィーの実家に引っ越したのか」や「なぜ黒い扉がハウルの少年時代につながっていたのか」を選んできた。狙い通りであった。
全班の発表が終わった後,指導者が「それぞれの扉は二人の思い出につながっているとも読み取れます。それにしても二人ともなぜラストで元気になったのでしょう。それぞれの思い出をのぞき合う過程で元気になっていくと言ったら,どこかで聞いたことのある話ですね。」等と思わずつぶやいた。学習者は不思議そうな顔をして聞いていた。
「『ゼブラ』ウィルスン視点からのリライト」〜平成18年9〜10月(2年次)〜
「ハウルの動く城」を鑑賞した後,リライト創作を開始した。その際,文章の構成を考えるための補助として「キーワード関連表」を4人班の各班に作らせた。何の準備もせずに感想等を書かせると,物語の限定された側面でしか文章を書かない学習者が出てくる。作品内の全てのキーワード相互の関連に目を向けさせるために「キーワード探し」の際に抽出したキーワード群に,再び引きあわせる必要があった。
まず「キーワード(心情表現)探し」の際に抽出されたキーワード(43個)の全てをキーワードカードにして,4人班に配布した。さらに各班にB3の色画用紙を配布して,その上にトランプのようにカードをまき散らさせた。そして画用紙上でカードをかき混ぜさせ,リライトの際に必要になりそうなキーワードを,相互の関係も考えさせながら抽出させた。(KJ法の応用である。)
「キーワード探し」によるキーワードカード(全43枚)
君を
食べちゃう
モンスター廃品と
がらくた恥ずかし
そう悲しそうな
顔夏の光に
輝く脂汗が
にじみ
体が震えるしま馬が
動くわしに
なったよう左そで 飛んでいる
ような足が
軽くなる空間 左手 想像力 ベトナム ヘリコプ
ターしま馬 フランクリ
ン通りあの日の
ことを
思い出す目頭に
手を当て立ったまま
手紙を
見つめる手が一瞬
こわばった笑わな
かった奇妙でみっ
ともない
肩を
すくめて明るい人生 絵 ビニール袋 驚いた
ように悲しそう
な目走るのが
大好き贈り物 レオン (予備) 人の顔 窓 特別に
心ひかれる美術 彫刻 道化師 輪郭を
包む空間傘 大きな影 本当に
うれしそう
な表情
上図の「キーワードカード」は,切り離してカードにしたものを班に一つ,一枚のプリントの状態のものを全員に配布している。
抽出するカードは5〜7枚に限定した。これ以上の枚数になるとただキーワードをつなげただけで作文することができ,言葉と言葉の間に生まれる「空所」の機能が,かえって弱まってしまうと考えたからである。また,それぞれのつながりを関連表上に図示するためにも7枚程度が限界だった。
まず採用するカードを5〜7枚確定させ,それを指導者に報告させた。黒板を10等分し,報告のあった班のキーワードを書き込んでいった。キーワードの変更をする場合は学習者に自主的に黒板上の書き込みを訂正させた。そして,「キーワード関連表」が完成した班から,黒板のキーワードの板書の上に,磁石で貼り付けていった。
次時に,簡単な「キーワード関連表」の発表会を班ごとに行った後,いよいよリライトの作成にはいった。
リライトが完成した後,班ごとに発表させ,鑑賞会を行った。
典型例をふたつ紹介する。(論者のインターネット上のHP「熊男の住処」に他の班の作品数十編を掲載している。)
リライトさせる際に,学習者はキーワードが5〜7個に限定されたことを不満に感じていた。そこで,「キーワード関連表」については数を限定し,そこからもれたキーワードについては直接リライト作品中で使用してよいとした。この班は「こわばっている」をリライト作品中に使っている。
題名「あの日のこと…」
ウィルスンは,手のデッサン中に,アダムの左手がこわばっているのに気がつく。
〃きっとあの日のことが思い出されるのだろう。〃
ウィルスンの脳裏にはアダムが大きな影から逃げる姿がうつしだされた。
「空間を見て描くんだ。」
そうアドバイスをすると,彼はもう一度左手を見て描きはじめた。
次の日アダムはヘリコプターを描いてきた。
一瞬,昨日のアダムのように,左手がこわばった。
そして,自分に暗示をかけた。
〃空間を見るんだ〃と…。
その日の夜,ウィルスンは考えた。
〃明日,きっと彼はヘリコプターを作るだろう。〃
そして思った。
〃自分ものりこえなければ〃
ウィルスンは,アダムのようにあの日のことを思い出した。
ヘリコプターが自分の大きな影となり,自分の左腕が消えていた。
翌日,アダムはヘリコプターをつくっていた。
左手が使えない分,〃ヘリコプター〃とは思えなかったが,アダムが左手を一生懸命使っていることが分かった。
そのヘリコプターをうけとった。
それはちゃんとしたものに見えた。 ※ 作品中の太文字はキーワード,下線は論者による補い。
この班の最大の特徴は「大きな影」と「あの日のことを思い出す」という二つのキーワードの使い方にある。これらのキーワードは『ゼブラ』本編では,主人公ゼブラに関する記述の際に使われている,いわばゼブラ専用語である。それを「キーワード関連表」,すなわちリライトの企画段階でゼブラとウィルスン両方に関わるキーワードとして位置づけている。
特にリライト作品中,最初の波線部にある「大きな影」は,ゼブラ専用語であることをそのまま生かして記述されているのに対して,後半の波線部に登場する「大きな影」は,ウィルスン自身のこととして記述されている。ゼブラとウィルスンそれぞれに関するキーワードがせめぎ合い,まるで融合して一つの世界のようになっている。ゼブラの側のそのようなウィルスンの心の中の世界との融合は,作品中,窓辺に置かれたヘリコプターの記述等にはっきりと描かれている。リライト作品はそれをウィルスンの側から見事に再現している。このような作品は各クラス2〜3班ずつあった。このような作品のおかげで,指導者は結論を話す必要が無くなったとさえ言える。
また次のようなリライト作品もある。
最も特徴的なのは「(不格好な)ヘリコプター」と「道化師」を、「大きな影」によって同格の存在と位置づけている点だ。「大きな影」そのものの使い方は、ゼブラ専用語であることを無視した形にはなっている。しかし、それによって浮かび上がってきた「(不格好な)ヘリコプター」と「道化師」のつながりは、決して恣意的解釈などではない。ベトナム戦争によって心身共に傷ついたウィルスンは、常に他者に対して「恥ずかしそうに」(キーワードの一つ)接しながら生きている。その思いは自らが創り上げた道化師に込められている。したがって、「道化師」の奥にはベトナムの辛い思い出があり、そのような意味で一見無関係な「ヘリコプター」と「道化師」を同格に置くのは、むしろ正確な作品理解による判断と言っていい。このような解釈は指導者である論者でさえも気づかないものだった。
題名「手が一瞬こわばった…から」
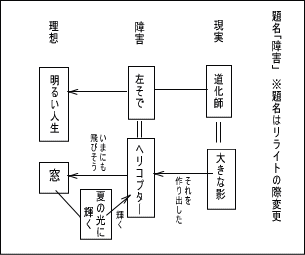
皆の絵は,よく描けていた。そしてウィルスンは次々に絵をかべにはっていく。
「おはようございます。先生。」
ゼブラだ。
「おはよう。」
「先生,これ。」
そういって手渡されたのは一枚の絵。これは…ヘリコプター?
と,その瞬間ウィルスンの目にはもう,いつもの教室は写っていなかった。そしてあの日あの時のことがよみがえってきた。ウィルスンは頭をふってもう一度ヘリコプターの絵を見た。それから壁に絵をはった。
次の日,またゼブラはヘリコプターを作ってきた。なぜかそれは,自分の作った道化師に見えた。大きな影をいだいたそれをウィルスンは窓の桟に置いた。不格好なヘリコプターが夏の光に輝いていた。彼の苦労が目に見えた。それに比べ自分は何だ?明るい人生を歩もうとせず,ただ無駄に生きているだけじゃないか。
それからウィルスンはゼブラの顔を見てうなずいた。
以上のように、様々な解釈に基づくリライト作品が学習者によって生み出された。他のグループの「キーワード関連表」を見て、自分達の「関連表」にさらに別の観点を付け加えながらリライト作品を完成させた班もあった。それぞれの班が既成の価値観をただ当てはめるだけの読みに終わらず、教材本文内の言葉と言葉のつながりをありのまま見つめた結果として、テクスト内に仕掛けてある様々な「空所」を発動させることに成功している。学習者の多様な読みが、融合しあいながら、単元の結末へと向かっていた。
〔4〕みつめ学習
リライト作品を全てプリントにして全クラスに配布した。単元の結論については、リライト段階で指導者の立場からは説明する必要がないほどの理解レベルに達しており、『ハウルの動く城』との共通点を種明かしするように話して、単元の結びとしたに留まった。(あくまでも指導者の恣意的解釈であることを確認しながら話している。)話したのは以下のような内容である。
二つの物語は,主人公格の登場人物が2人ずつ登場する点が共通してますね。しかも、全員が傷ついた心を抱えて生きている。他人や周囲の物事に対して積極的になれないまま生きている。しかし、お互いがお互いのことを知り合う過程で、徐々に心の傷が癒されていきます。単に知り合うというただそれだけで、生きる力を手に入れている。ゼブラはヘリコプターの絵を描いて模型を作っただけですし,多くの班が指摘していたようにソフィーが若返る理由は全く不明です。ただソフィーはラストシーンでハウルの少年時代に旅しています。ハウルが心臓を取り出すシーンは美しいけどいかにも寂しげです。この時ハウルは彼の孤独の原因となるなにかの出来事に出会っていたのかのかもしれません。そして彼の孤独の心を理解する過程で,ハウルの心が癒されるだけでなく,ソフィーの心も生きる力を取り戻しています。ゼブラも同じです。物語の途中でゼブラ自身の話は物語の奥に引っ込んでしまい,ほとんどのシーンがウィルスンだけの思い出であるはずのヘリコプターのエピソードで終始している。それなのにゼブラはラストで,『明るい人生』を歩めそうなほど,生きる力を取り戻している。例えそれが悲しい思い出であったとしても,他人のそれを理解したり,理解してもらったりすることは大事なのかも知れませんね。
⑧ 結果と考察
帯単元として「ひびきあう言葉と心 〜詩創作,キーワード探しからリライトまで〜」を設定し,実践してきた。文学的認識が,文学作品の鑑賞の際にのみ必要とされるものではなく,創作活動や,物語の筋道を追う読解においても必須の機能であることを確認した。
国語が苦手な生徒には幾つかの傾向がある。一つには,言葉が文章内のコンテクストによってその意味を変化させることが分からず,辞書的意味に固執し続けてしまうことがある。また一つには,一見関係のなさそうな言葉と言葉の間につながりを見出すことができず,学習済みの既知の価値観に結びつけることで,文章を理解したつもりになってしまっていることなどがある。もちろん明確な結論にたどり着くことは大事だ。しかし、右のものを左に置き換えるような思考を繰り返していては、文章内容を正確に読みとる読解力は身に付かない。重要なのは、読みの過程である。文章中に既に出来上がっている結論を探すのではなく、言葉と言葉のつながりの中から結論を見出していく姿勢が必要なのだ。
論理構造を読み解くことと,文学作品の鑑賞とは,一般的には対照的な教育活動と見なされる向きもある。しかし,教材内の言葉と言葉がつながりあい響き合う様子をありのまま見つめることに関しては,両者に等しく重要であるはずだ。それによってテクストが織りなす世界に没入することが出来る。没入することでその世界を正確に理解することが出来る。
そのような観点の元に,言葉と言葉のつながりを見出す訓練をまず「詩創作」を通じて行った。そこで獲得した文学的視点を,今度は文章構造理解の際に応用し,「キーワード探し」によって黒板上に言葉と言葉の詩的つながりを作りだした。さらに抽出された言葉と言葉のつながりをリライトという創作活動に応用し,同時に作品の精緻な読みへと昇華させている。それらの活動の多くを,4人班で行わせた。言葉と言葉の非日常的とも言うべきつながりを認識し,理解するために,他者の力を借りるのである。学習者それぞれの多様な読みの中にあって、自己の解釈に対する確信が薄れがちな読解活動において、相互主観の獲得という点でも4人班による活動には利がある。
来年度は文学作品以外の教材を対象として,文学的認識を足がかりとしたテクストへのアプローチを試みる。さらには,作品世界への理解がそのまま日常世界の理解へと繋がる学習活動のあり方を模索する。
多様な価値観に溢れる現代社会において,身の回りの現実を「読み解く」際にも,文学的認識力の役割は大きい。言葉やそれによって作り出される「現実」をありのまま見つめることを,国語科教育の目標の一つとして,今後も文学的認識力を育む教育方法のあり方を探っていく。
戻る