| 「星野さんの眼になれ!」作品集(平成19年 中3) |
※「星野道夫事務所の了解を得て画像を使用しています」
※「このページに掲載されている画像等の無断使用は固くお断りします」
平成19年10~11月の授業実践での、星野さんの写真作品をもとにした生徒達(中3)の創作小説です。1クラス10班×4クラスで40作品です。星野道夫事務所の了解を得ることができ、星野さん自身の写真付きという豪華版が実現しました。
作品は全て生徒のオリジナルで、指導者は一切手を加えていません。
写真のある位置をクリックすると創作の際の構想表「キーワード関連表」が新しいウィンドウで出現します。
1

「写真」
今回はアラスカの風景写真を主に撮る予定を立てている。
僕らは、アラスカの人々と山をおりて湖と平地のある場所へ大移動をしていた。
「今日は昨日より暖かいですね。」
ずっと側に付きそってくれているアラスカ人のマイクは言った。
そういえば、体はとっくにアラスカの寒さになれていた。自然を壊さないようにと僕たちの旅は歩いて移動をしている。
そんなことを考えていると今まで針葉樹林で閉ざされていた視界がある一線を越えるとぱっと開けてきた。
そこには、まだ日が高かったため、青々とした草原が広がり、日を反射してキラキラ光る湖があった。とてもきれいだった。気が付くともう十二時半を回っていた。
「そろそろお昼にしますか?」とマイクが言った。
「そうですね。」皆うなずいた。
持ってきていたパンと紅茶、ボイルドエッグを食べた。食べながらマイクが「この山のふもとにトナカイの里があるんですよ。」と言った。私は写真が撮りたくなった。
皆は、食後のお茶を飲みながら雑談をしていた。
「さあそろそろ出発しましょう。」私は言った。
どうしてもトナカイの里で写真が撮りたくて先を急ぎたかったからだ。私の心は既に「トナカイの里」にあったのかもしれない。
「星野さん急ぎすぎですよ。」とマイクの声が後ろから聞こえた。
「すみません、ついつい急いでしまって…。」
マイクが「トナカイは、逃げたりしませんよ。」
しかし「夕暮れの景色は本当に美しいんですよ。」と言った。
私は「夕暮れまで着くようにがんばりましょう」と皆を励ました。
どのくらい歩いただろうか、影が後ろに長く伸びていた。「星野さん、ここですよ。」とマイクが言った。
ついたのは湖と平地があったこの瞬間を見たかったからだった。
写真を撮るとき突然一頭のトナカイが山から出てきた。そして見守っていると夕日、湖、平地、トナカイのかさなりがすばらしく思えてきた。
(これだ)
一言いってシャッターをおした。
2

「はじまり」
「だめだ、こんな写真。」
私が契約していた雑誌の編集者からの一言が飛んだ。私を見ているくまの写真。このところ、なかなかOKが出ていなかった。一体、何が悪いのだろう。
頃は十二月。日本では年末の準備が進んでいるようだ。が、私はなかなか前に進めずにいた。
「もう一度チャンスを下さい。」
私は編集者に頭を下げた。もう一度北極圏に行こうと決意した。北極圏の自然に触れれば、悲しみにくれる私の心も洗われるかもしれない。初めて北極圏の自然に触れたときのことを思い出し、そう思った。日本では見られないものをたくさん見たからだ。そして、私は旅だった。
北極圏は、氷に閉ざされた極北の地である。一人で巡り歩くのは危険だと判断した私は、地元チームのノンに連絡した。彼は私の数年前の旅を覚えていてくれたので、すぐに応じてくれた。
私はそこで写真を撮った。真っ白な「無」の世界、清廉な「青」の世界、虹色のオーロラが織りなす「幻」の世界…こちらを愛らしく見つめるアザラシに、首をうずめたフクロウ。それらは私の心を癒してくれた。
ある晩、私はいつものようにぐっすりとは眠れずにいた。なぜだろう、とふと時計を見ると午前三時である。そろそろ寝なければ明日の仕事にさしつかえてしまう。そして、ようやく浅い眠りについた。
-ねえ、僕達のこと、撮ってくれないのかなぁ、ママ。
-そうね。星野さんにお願いしてみようかしらね。
夢に、二匹の子ぐまと母ぐまがでできた。子ぐまはまだからだが小さく、仲のよいように思えた。翌朝、私はある事実に気づかされた。ノンが、
「星野さん、今回は、くまの写真を撮らないんですか。前回は、一途にくまを撮りたがっていたようでしたが。」
と言ったのだ。日本でくまの写真が却下されたこともあり、心のどこかでくまを意識的に避けてしまっていたようだった。
「では、今日はくまを撮ることにしましょう。とびきりすばらしい場所へ連れて行ってください、ノン。」
時刻が正午近くになり、昼食のために休憩していた私達の背後で、ガサゴソという物音がした。振り返ると、そこには純白のシロクマが3匹。
「匂いにつられてやってきたんでしょうか。」
ノンは言ったが、私は直感で違う、そうではないと思った。3匹は、夢に出てきたあのくまだった。私を一心にきらきらとした黒い瞳で見ている。「僕たちを撮って。」そう言っている気がした。私はカメラをかまえ、ひたすらにシャッターを切った。横顔、うしろ姿、じゃれ合う親子の姿。そして、一列に並んでこちらへゆっくりと歩いてくる姿。この一枚は、今回の旅の最高傑作となった。
日本へ戻る飛行機の中で、私は今回の出会いを思い返していた。この出会いは、確かに偶然だったかもしれない。だが、人生は無数の偶然によって成り立っている。私は自分が今まで歩んできた人生が合わせ鏡のようにどこまでも続いてゆく気がする。あのくまの親子も、合わせ鏡のどこかに映っているのだろう。
日本に帰着して、現像した写真を編集者にさっそく見せに行った。彼はパラパラと写真をめくっていき、ある一枚で手を止めた。
「おっ、この写真はいいね。くまたちが君に好感を持っているよ。」
それは、あの最高傑作と思った写真だった。
北極圏に行ってよかった。また新たな自分が見つかった。偉大な大地の懐に抱かれた約一ヶ月間、私は「自分探し」をしていたのかもしれない。
今は一月である。人々の正月気分も抜け、それぞれがスタートを切ったようだ。そして、私は一ヶ月前のように前へ進めないことはない。私も新年のスタート地点に立ち、走り始めたのだ。
3

「青」
空を見上げると、いやなくもり空だった。どんよりとたれこめる雲は気分のよいものではない。けれども、そのくもりが晴れた時、自然はため息の出るほど美しい光景を見せてくれる。それが見たくて私は今、アラスカの大地を踏みしめている。私がこの地に来ることになった最大の原因であるジョージ・モーブリィ氏の写真も、雲の間から太陽の光が差し込んでいる光景だった。そんな写真を撮りたいと思いつつ、くもりの時はいつもこうやって歩き回る。いつもならば「ここだ!」と直感でわかるのだが、今日はなぜかしっくりとくるものがない。なぜだろう。首をかしげつつ、坂を上っていくと、急に視界がひらけた。眼下には、巨大な氷河があった。よく見ると、氷河の下には今までに見たことがないものが見られるかも知れないという興味と、「氷河がくずれたら」とい恐怖が頭の中でいたちごっこをしているのを無視し、未知の世界へと入っていった。洞穴の中は暗かった。静かに川が流れる音しか聞こえない。生物の気配も感じられない。けれども不思議と安らぎを感じた。しばらく歩き続けると、前方にわずかな光がさしているのが見えた。その風景を撮ろうとカメラに手を伸ばした……が、その時、何の前ぶれもなしに、差し込んできている光が「カッ」と明るくなった。あまりのタイミングの良さに、驚いている私をよそに光はどんどん強くなる。「あぁ。私の頭上の雲がたえきれずに太陽の恵みをこぼしたな。」と勝手に思っていると、私の頭の上にある氷が明るくなった。色は青。「未熟」を全く連想させない力強く、なおかつ包容力のある「青」だった。-ふと、なつかしき記憶がよみがえる。二十世紀、最大の芸術家、パブロ・ピカソは人の悲しみを表現する時、「青」を最も重視していた。また、いつしかの神田の古本屋でふと手にした本に、「青は、思考、理性を司る色」とあった。-今、私は青の中にいる。色のせいだろうか、悲しかった思い出が、頭の中で大きくなっていく。会いたいのに会えない悲しさ…。友との別れ…。偉大な友の死は、どれほど私を苦しめたことか。私はたえきれず、アラスカの氷の下、一人、涙をこぼした。悲しみは悲しみを呼ぶ。胸をしめつけられるような思いは強くなっていく。耐えきれなくなった時、うずめていた顔をあげると私はまだ青に包まれていた。するとどうだろう、なぜか心の波がしずまり、今の自分が見えてきた。頭も、冷静に動き出した。たしかに「会えない悲しさ」・「会ったことによって生じる悲しさ」はある。けれども、これがあるから「会えたことによる喜び」がある。昔を顧み、慕うことは決して悪ではない。けれども、いつまでも過去にしがみ続けることはよくない。せっかく生まれてきた命。はてるまで上を目指すべきだ………と、私は悟った。
カシャ
思わず笑ってしまうような間抜けな音と共に、私の人生にとって重要なものとなった空間が、写真として記録された。後世の人々は、この写真を見た時、氷河という自然によってつくられた青の裏に、大きな悲しみを多かれ少なかれ感じとってくれることだろう。悲しみは悲しみを呼ぶ。けれども悲しみがあるから喜びがよりすばらしいものに感じることができる。そういう意味では青、つまり、悲しみという存在に感謝しなければならないのかもしれない。
4

「孤独からの出会い」
「私は星野道夫、今、アラスカにいる。」
とぼとぼと冬の寒い道を歩いた。私は今、アラスカの凍土のように凍りついている。
なぜなんだろうか。自分でも分からない。私は昔、神田の古本屋で一冊の本に目がとまった。それはジョージ・モーブリィという人の写真集だった。
パラリパラリとページをめくると、一枚の写真に出会った。その写真を四六時中見ていると、俺の今の気持ちとピッタリあうような写真だと気がついたのだった。それで私はアラスカに向かった。アラスカではたくさんの人や動物に出会い、少しずつだが、私の凍土も溶け始めていた。その時だった。
私の目の前にまっ白なキツネが一匹姿を現した。まっ白なキツネはとても愛らしくその白さが雪と溶けあうように私の気持ちも少しずつやわらいでいった。
そしてキツネと目をあわせていると、なぜか、心で会話しているような気になった。
「僕、今一人ぼっち…ねえもしかして、道夫さんも?」
「いや…うん。私は今、どうしていいかわからなくて写真に興味を持って、アラスカに来たんだ。でも君に会えてよかったよ。なんだか気持ちが楽になってきたんだ。ありがとう。どうだい?君の写真を一枚撮りたいんだが…いいかい?」
「本当ですか?よろこんで…お願いします。」
「おや、なんだか暗い顔をしているんじゃないかい?」
「いいんです。僕と道夫さんの共通の気持ちをこの写真に残して思い出にしたくて…。」
「そうか…。それならいいだろう。」(間)
「ありがとうございました。これは一生の宝物ですね。」
「そうだなぁ、今日のこの時を私は一生忘れないよ。それじゃあ…。」
「さようなら…。」
また私の一人旅は始まった。今度はどこへ行こうか…なにして、どんな写真を撮ろうか…。(間)
私はまた冬の寒い道をとぼとぼと歩きはじめた。でも、今度の旅はなんとなく空が明るく感じた。気のせいなのだろうか…。いや、これはきっと気のせいなんかじゃないのではないか。そう思いながらもぐんぐんと進み続け、どんどん周りの景色が変わっていく…。ピンク、緑、赤、そして白…。またこの季節がやってきた。思い出深い白だった。一生忘れることのできない白。また会えたらいいなぁ。そんな思いだ。私は今、白い道を歩いている。
「あれ?」私はつい、口に出した。前には一つの大きな標札が…。
よく見てみるとそこには『希望への道』と書かれてあった。
私はまちがってなかったんだ。少し落ち着いた…。この道をまっすぐ進めばいいのだと…。
5

「アラスカの空」
ある日、ふとアラスカに旅立ちたいと思い、家族に
「一月くらいで帰る。」
と言って、銀行からお金を引き落とし、車で空港まで行く。空港に近づくにつれて、心音が体全体に響き渡り、更に鼓動が早くなっていった。なぜ、アラスカに行こうと思ったのだろう…。車から降りて晴れた空を見る、すると、心の中に一つの答えが出た。それは昔、友達が見ていた写真集の中に、この空によく似た一枚のオーロラの写真があったのだ。その写真を見た瞬間、言葉では表せないものがあり、強いて言うならば、
「こんなきれいな光景があるのか!」
という感動があったと思う。その時に、撮った人の名前を聞いたら、ジョージ・モーブリィと言っていた。とにかく、その出来事が頭のスミに残っていたからなのか、私の脳はアラスカを選んだのだ。違うにしても、そう思った方が面白いと思い、そういう人生を私は生きていくのだと考えた。そんなことを考えていると、もうすでにアラスカの上空だった。
「この地であの光景が見られるんだ!」
そんな軽い気持ちで考えていたのがそもそも間違いだった。外に出たとたんに雪だるまになりそうなこの寒さ…。本気で帰ろうと思うぐらいだった。しかし今帰れば、今までが水の泡になってしまうと思い、バス停へ急いだ。それは、案内をジョージ・モーブリィ氏に頼んでおいたからだ。返答はあやふやだったが、来てくれると信じていた。だが、バス停に行ってもそれらしき人はいなかった。
「来てくれなかったのか…。」
親友から突然嫌われたような絶望感が襲ってきた。その時、なぜ前を見たのか、そしてお互いに目が合ったのか分からないが、二人とも絶対的な確信があった。彼は来てくれたのだ。ホテルにバスで向かいながら、私は彼に、今までの人生は今日からのためだったと思うことを中心に様々なことを話した。次の日は、朝早くから起きて山へ登り始めた。私は、少し登るとクタクタで、会話する余裕もなかった。ジョージに何回も助けてもらい、山頂にたどり着いたのは夕方だった。私が疲れきって倒れていると、彼は夕焼けを見ながら、
「私も写真家になったのは、本当にあなたみたいな人から影響を受けた。」
と言いだし、彼のあこがれの人を語ってくれた。語り終わった直後から、オーロラが見えてきた。二人は互いに写真をとっていたが、ある瞬間〃カシャッ〃と、同時に一枚の写真を撮った。その時には、もう写真家になることを決心していた。
それからは、家族にアラスカで基本は暮らしていくことを言い、動物たちや風景をフィルムにおさめていった。
6

「カリブー」
「僕は今回カリブーを追うことにした。」
それを聞いたアシスタントは僕の目をあきれた表情で見つめてきた。
「先生、また北極圏に行くんですか?」
「これが僕の仕事だからね。」
二週間後、僕はアラスカの地に着いた。アシスタントはアラスカに来たことがなかったため、目の前の風景を見て驚いていた。
「空気がおいしいですね。」
「今から行くとこはもっとおいしいぞ。」
そして僕たちは車で目的地まで移動した。アラスカは広く、車の窓から見える光景はどんどん変わっていき、変わるたびに感動するのだった。
次の日の明け方、゛ほくはアシスタントを連れて湖に出かけた。僕はアシスタントを岸に置いて、ボートを静かに漕ぎ、カリブーが来るのを待った。アシスタントは車のライトで湖を照らした。ぼくは向こうの方から聞こえる「パシャッパシャッ」という音でカメラをかまえた。春になると大きな群れをなして北極圏へと集まってくるカリブーがいつもこの湖を通るんだとこの近くの村人が言っていたことは本当だったんだとアシスタントは思った。
目の前のカリブーを僕は必死に撮った。その後も、三週間くらい僕とアシスタントはカリブーを追い、写真を撮った。空港へ向かう車の中で、アシスタントが言った。
「星野先生って写真を撮る時、本当に幸せそうですよね。」
「これが僕の仕事であり、生きがいでもあるからね。」
日本に帰ってきて現像した写真を見てアシスタントは感動した。その写真には湖を一生懸命に通るカリブーの姿が映っていた。
「すごいですね、この写真は。」
とアシスタントは、言った。それしか言わなかった。それしか言えなかったのだろう。その写真を撮った僕ですらその美しさに驚いたのだ。
「なかなかよく撮れているだろう。」
僕は写真をずっと見続けているアシスタントに自慢げに言った。
7

「地球温暖化について」
私はアラスカに旅に行くために準備をしている。これから旅に出るアラスカは、私たちが暮らしている快適なくらしとは違うのだろうか。きっと何もないところだろうな。今日本は地球温暖化問題をかかえているが、私が撮った写真を通してアラスカの今の現実をうけとめてもらうために、体で感じようと思っているんだ。
私は出発した。長い長い時間をかけてやっとアラスカの地にたどりついた。ここで案内人とトムとの待ち合わせをしている。
「初めまして、トムです。星野さんに会えるのを楽しみにしていました。」
「こちらこそ初めまして。今回は、今のアラスカの環境を写真におさめにきました。」
「それではさっそく船にのりましょう。」
アラスカの船は、乗りごこちがよいとは言えず、木をつぎはぎしたようなボロいものだった。だが、私はそのようなことは気にもとめず、ただ目の前の風景を写真におさめ続けた。
すると突然静かだったこの場所にすごい音が鳴り響いた。
ふり返ると、氷河がくずれ落ちていた。
アラスカに来る前、日本のテレビで地球温暖化の影響で氷河がくずれ落ちるのは見たことがある。
しかし、その頃は自分にはあまり関係がないと思っていた。
今、この瞬間に地球が暖かくなってきており、自然界に影響を及ぼしていることを間近で感じている。
氷河は助けを求めるかのようにすごい音を立ててくずれ落ちていった。
私はその様子を見て、このままでは本当に何年か後には人間も動物もいなくなってしまうと思った。
人間はまだ、地球温暖化の恐ろしさに気づいていない。
人間のぜいたくのせいで地球が悲鳴を上げていることに気づいていない。
私はこのことを恐ろしく思った地球はこのまま崩壊してしまうのか…。
しかし、地球温暖化はどうにもならない問題ではない。
人間の暮らし方によっては、元のキレイな地球に戻すことができる。
しかも、地球温暖化のおそろしさに気づいている人もいる。
その人たちが今、対策を打っていないわけではない。
しかし、その人たちだけが頑張ってもどうにかなる問題ではない。
日本中の人、いや、世界中の人々が協力をし、地球温暖化と向き合わなければ地球温暖化が止まることはないだろう。
私はアラスカに来て、自分には関係ないと思っていたことが、世界中の人たちに関係あることを肌で感じた。
人間がちょっと頑張ればどうにかなる問題もぜいたくという欲望のせいでどうにもなっていない。
私が感じたことを人々に伝えるためにシャッターを切った。
8

「ボク、アザラシ」
ボク、アザラシ。今、話題の星野さんがもうすぐ、ボク達の所に来るらしい。どんな人かな。みんなは優しい人だっていってる。本当かな。早く来て欲しいなぁ。
ザック、ザック、ザック…。
人影が見える。もしかして、あれが星野さん?優しそうな顔してる。やっと出会えるんだね。これが、ボクと星野さんの最初で最後の出会いだった。
今日は、アザラシの写真を撮りに行こう。アラスカには、色んな種類のアザラシがいるって聞いているが、どんな子に出会えるんだろう。楽しみだな。さあ出発だ。
おっ、あそこにアザラシがいるぞ。私に微笑みかけている。今日撮るのはあの子だ。きっといい写真になるぞ。
「笑って笑って。」
「クウーン。」
「返事をしてくれたんだね。今まで、キミみたいにかわいい子会ったことないよ。私は、キミとの思い出に写真を撮りたい。いいかい。」
ボクは、日本語がわからない。でもなんとなく星野さんの言っていることはわかった気がした。早く写真を撮ってくれないかなぁ。なんだか気持ちよくて、眠くなっちゃった。
「最高の笑顔で、ハイ、チーズ」
ボクはその一言で、彼にとびっきりの笑顔をプレゼントした。そして彼は、ここへ来た時以上に、暖かい顔になっていた。ボクの笑顔をよろこんでくれているにちがいない。
今までに、何枚もアザラシの写真を撮ってきたが、この一枚は、味わい深かった。まるで私の気持ちが、そのままアザラシに通じているようだった。そろそろ、日も暮れて、周りがうす暗くなってきた。家に帰らなければならない。二度と出会えないかもしれないが、しかたないことだ。
「キミも、そろそろ家に帰りなさい。お母さんが心配するよ。」
星野さん、もう行ってしまうんだね。ボクも、もうすぐ行かなくちゃ。さびしいよー。冬が終わってしまえば、氷がとけて、もうここにはいられなくなってしまう。星野さんとの、出会いは終わった。
ザック、ザック、ザック……。
星野さんは、来た時と同じようにほほえみながらかえっていった。
9

「リラックマ白クマ」
「あれは私の求めている光景なのだろうか。」
私は何かを求めてここへ来た。何を求めているのだろう。
特に何も考えないまま気づけばこの地、北極へ来ていた。一面まっ白なこの地へ。
最初は白銀の世界に圧倒されていたが、しだいに目がなれてくると周りの景色がだんだんと違うものに見えてきた。私には今何が見えているのだろう。私はもっと北極について知りたくなったため。しばらく滞在することに決めた。
滞在して、日本では季節が変わり始めたと思われる頃、周辺の風景が動き始めた。一面の白の中に、動く点が現れだしたのだ。白クマだ。私がいるのは、北極でも南の方だ。きっと、エサを求めて北から移動してきたのだろう。
私はカメラを肩にかけて、キャンプを出た。
この度で、私はほとんど写真を撮っていなかった。目に映る景色はどんどん変化していったが、そのどれもが自分の求めているものでないような気がした。
私は何かを求めてここへ来た。何を求めているのだろう。
白クマ達は、三~四頭の小さなグループを作って、キャンプからそう遠くない場所で生活していた。といっても、明るい時間に家族-そう、その三、四頭のグループは明らかに家族だった-全員がそろっていることはあまりなかった。オスがエサをとりに行くからだ。だから、私はキャンプにほど近いところのある家族が、実は夫婦二頭だけで生活していたことになかなか気が付かなかった。
他のクマ達が子育てで慌ただしい生活を送っている中、その二頭は妙にどっしりと落ち着いていた。よく見ると毛の色も少しくすみ、つやがない。もう子供は成人し、親元から巣立っていたのだろう。人間でいうと40代後半から50代といったところだろうか。
私はその二頭を、親しみを込めてオヤジ、オフクロと呼ぶことにした、そして、もう10年もあっていない良心の姿を思い浮かべた。
北極に来たのは、これがはじめてではない。白クマの写真も、何度もとったことがある。しかし、そこに両親の姿が浮かんだことは今までなかった。私が撮ってきたのは、きびしい北極で生きるために戦い抜く雄々しい姿だった。
夫婦グマは、そんなものとは無縁な様子で私の前でくつろいでいる。私はためらいながらカメラをかまえた。オヤジグマはどーんとあおむけにひっくり返り、熟睡している。オフクログマはその横に眠たそうな顔をして立っている。そして、二頭の顔は両親の顔と重なり、私は微笑んでシャッターを押しかけた。
しかし、シャッターを押す寸前、オヤジグマの顔は父から、私に変わった。
私はふと、遠い昔のことを思い出した。母が夕飯を作っている。そこへ父が帰って来て、小学生の私がとびはねて喜んでいる。
私はもう一度、しっかりとカメラをのぞいた。
「これが私の求めていた光景だ。」
私はシャッターを押した。
10

「人生の瞬間♡」
アラスカで、写真が撮りたい。自然や熊を撮りたい。
そう思い、私は熊の前に立っている。
「パシャ」
二頭の熊の人生の一瞬を私のカメラはとらえた。カメラで撮った熊の動き。それと同じ姿を見せることは、私がカメラのシャッターを押した時からは、一時間以上なかった。
黄金のような輝きを放つ雑草たちに囲まれながら、熊たちは、私が遠くから眺めている間、ずっとお互いを見つめ合いながらじゃれ合っていた。
私は、そのじゃれていた熊たちの写真を現像してみた。私がしばらくその写真に見とれていると、ふと気づいた。これは「私」の人生をとらえた写真なのだと。
それと同時に熊たちが私に撮られた瞬間でもあるのだと。
たった一枚の写真だった。しかし人生の一瞬である。そして決して二度と撮ることのできないものである。
熊たちのその瞬間の動きを撮ることは、決して偶然ではない。
時間をかけなければ、私が認めた、私自身の人生の瞬間を撮ることはできない。それが私の写真集になっているのだ。
私は、そんな思いでこれからも、いろいろな人生の瞬間、そして、私自身の人生の瞬間を、カメラで撮り続けていきたい。
だが、撮り続けていきたいのは、アラスカでの写真だけなのである。アラスカの自然や動物、そして人間は、私が唯一写真を撮りたいと思ったものなのだ。
太陽に照らされ、明るく頬を染める自然。毎日、追いかけっこをする動物たち。
日本で、アラスカの厳しい寒さにも負けず、一生懸命そこで暮らす人々の写真を見てふとそう思った。
世界は広い。アラスカでの写真をもっと撮りたいと。
私の人生、イコール アラスカと言っても過言ではない。
私はアラスカが好きだ。これからも生涯死ぬまでアラスカでの生活を楽しみたい。私だけのアラスカの写真集を作りたい。
そんな思いで熊のじゃれあう姿を見ていると涙が出てきた。周りの景色がにじんでくる。その時、私は太陽に照らされ、私の涙は、太陽よりも強く、輝いていたのだった。
11

「大切なもの」
星野さんはアラスカのイヌイットの村で、たくさんの自然にかこまれて暮らしていた。
ちょうど20年ほど前、星野さんは、神田の古本屋で出会った一枚の写真のせいでイヌイットの村に行って、何年か滞在したあと、日本に戻っていった。そして、日本で結婚して、子供も生まれ、一家の大黒柱になった。家族と共に、楽しい生活を送っていた。そんなある日、星野さんは突然アラスカのことを思い出した。思い出してしまうと、なぜか不思議な気持ちになって、アラスカに行きたくなってしまった。そして、その日の夜、家族にあてた手紙を置いて、家を出た。
それから、星野さんは、一人でイヌイットの村に戻った。何年も前に住んでいた村は以前いた頃と全然変わっていなくて、星野さんは村の人々にあたたかい気持ちで迎えられた。その時、星野さんは自分が本当の家族に迎えられたような気持ちになった。
それからの毎日は、昔来たときと変わらない生活だった。毎日が自然に囲まれていて、たくさんの写真を撮り続け、星野さんの日本においてきた家族のことを忘れさせてくれるくらい充実していた。それが、星野さんにとってとても楽しかった。
そんなある日、星野さんはいつものように自然の中で写真を撮っていた。
いつものように森の中を歩き回っていると、小さな動物が一匹でいるのを見つけた。星野さんはいつものように、その動物にカメラを向けて、シャッターを切った。
その時、星野さんは、その動物の孤独な姿が、ふと、自分の姿に重なった。
星野さんはイヌイットの村で、村の人々と一緒に暮らしていたが、どことなく孤独感があった。それから、その動物が群れの中に帰っていくのを見ると、突然、胸が締めつけられるような思いがした。家族がなつかしくなり、いそいで日本に帰った。
日本の家に帰ると、昔のままの家族がいた。イヌイットの村で暮らしていても家族のことを思い出してしまった。これはやっぱり星野さんは自分にとってはイヌイットの自然の中での暮らしよりも家族が大切だったんだと感じた。
12

「雪の日」
星野さんはアラスカにいました。音は風と一緒に凍ってしまったようです。「寒いですね。」岸君が言いました。「寒いね。」ほぅっと息をはくと真っ白い息が星野さんの口からもれます。寒いのかな、天国も。かじかむこぶしをぎゅっとにぎって空を見ました。上ではどんよりと雲が光っています。
星野さんはもう一度息をほっとはくとよいしょとカメラをかまえました。カシャカシャ。レンズから見えるそれは冷たさもしゅっと溶ける弱さももっていないようです。カシャと七回目のシャッターを切ろうとした星野さんはふと手をとめました。少し前で雪が丸くもりあがっています。ゆきみ大福みたいだなぁ。ふいにもぞもぞとそれが動きました。星野さんがそっと近づくとくるんとしたものが二つ見えます。どうやら小さなあざらしのようです。
「迷子でしょうか。」ふいに岸君が言いました。「親が見えませんね。」星野さんはそっとうなずきます。「死んだんでしょうか。」星野さんは何もいわずにそのあざらしを見つめます。あざらしがもぞもぞと動きます。雪がおちてあらわになった背中が居心地悪くゆれました。
急に空気がピンとはりつめます。あざらしが動きをとめています。星野さんはアザラシがじっと自分を見つめていることに気付きました。あざらしは突然の侵入者をうかがうようにそっと見ています。親は死んだんだ。いないんだ。星野さんは、はっきりそう思うとますますあざらしをみつめました。
その時でした。ずっとずっと空気のゆれる音がします。はっと一人と一匹は音のほうをむきました。むこうの灰色の点がだんだん大きくなっています。きゅっきゅっ。あざらしは泣くと星野さんにくるっと背をむけてずっずっと雪の上をすべりだしました。急に星野さんは息苦しいと感じました。酸素がどんどん星野さんから逃げていきます。灰色の点がアザラシと出会うころには宇宙に放りだされたようでした。二匹の線はつながり一直線になりました。きゅう。小さいあざらしが泣きます。あざらしが灰色の大きいあざらしの体に顔をうずめます。「良かったですね。」「ああ。」星野さんは胸が締めつけられる思いでやっとそう答えるとそっと七回目のシャッターをおしました。カシャ。シャッター音を聞くと星野さんはフゥーッと長く息をはきました。岸君もほうっと息をはきます。星野さんはくるっと回れ右をしました。後ろには星野さんと岸君の足跡がくるくると動きながら続いています。なめらかに広がる雪のその静かなしずみが星野さんが生きていることを語っていました。星野さんはそつとしゃがむと自分の足あとをじっと見てポケットから親友の写真をとり出して、そっと足あとの上におきました。「星野さん。」岸君が不思議そうな声で言います。星野さんは雪を両手ですくってかけました。一杯、二杯、三杯、白い雪がすっぽりと写真を隠します。星野さんはぎゅっと目をつむりました。岸君もまねをします。やがて星野さんはひざをはらって立ち上がりました。もう一度回れ右をすると小さなあざらしは顔をうずめたまま眠っています。星野さんは優しくほほえむと回れ右をして歩き出しました。岸君もあわてて続きます。星野さんは上を見ました。あいかわらずの空だな、次は何を撮りに行こうか。」星野さんは人生がちょっと見えたなぁと思いました。
13

「孤独から見た現実」
私は今、カバンの中だ。星野さんの顔を見たのは一体何年ぶりだろうか。もうすぐ彼は、あのあこがれのジョージ・モーブリィとついに出会うのだ。
星野さんと私が出会ったのは今から二十年以上も前のことだった。あの日いつものように神田の古本屋の棚に並んでいた。そこに彼はやって来た。彼は私を手に取りしばらくくい入るように私を見つめた。それからというもの、彼がどこに行くときも私は連れて行かれた。彼はいつも私のページで手を止めた。
私は一体何なのだろうか。
私のどこに星野さんはひかれていったのだろうか。 私がまだアラスカの大自然にいたころ、星野さんとよく似た男が私の前に現れた。彼は温かい眼で私を見つめたが、どこか悲しそうな目だった。私と似たものを感じた。私の分身が彼の中に生まれた。彼は彼の中の私を多くの人と分かち合いたいと思った。彼は写真という手段を選んだ。そして私の旅は始まった。
それから私は彼の撮った写真にのって遠く離れた日本に着いた。気がつけば、私は神田の古本屋にいたのだった。
ドアをノックする音が聞こえる。どうやら、星野さんは来ジョージ・モーブリィのいるホテルの部屋についたようだ。
ここはどこなんだろうか。
今まで聞こえづらかった彼らの話し声がだんだんはっきりと聞こえてきた。どうやらジョージ・モーブリィが星野さんに今までの人生を後悔しているか尋ねているようだ。
「いや、そういうわけではないんですが…。大きなきっかけとなりました。」
私の心の中の声と星野さんの話し声が少しずつかさなっていた。私は本当に、今カバンの中にいるのだろうか。ジョージ・モーブリィが私に対して優しくほほえみかけてきた。
ああ!この人だ!!
この人の中にも私がいる。
そうか、この人がアラスカで出会った男の人だー!!! あっ、今目が合った。何年ぶりだろうか。
なぜ彼の顔が見えたのだろうか。
私はカバンの中にいるはずなのに。
なんだか あたたかい
そうか、私の旅は星野さんの心の中に続いていたのだ。 そして星野さんも写真を撮り続ける。その中の一枚が このふくろうの写真だ。
雪の中を連想させる真白の羽に身を包んだ一羽のふくろう。彼がこの写真を撮ったのは、このふくろうの中に私を感じたからだろう。今、こうしている間にも何人の私が生まれているだろうか。
14

「自然の摂理」
アラスカの寒さに身をふるわせながら私は旅にでた。いつも一緒にいるアシスタントには内緒で…。
来年は一時的に日本に帰国する予定にしている。
大好きな写真を撮り続けてあっという間に15年…。
ホッキョクグマやキツネの親子の写真を撮っているときに、自然に家族の意味を教えられた。また母親に寄りそう子どもの姿を見て無性に自分の母親に会いたくなった。ただそれだけのことだ。そんなことを考えながら地図にはない森の中を歩き回った。自分が思う方向へと…。
少し疲れた私は地べたに座りこみ、パンをほおばると音が聞こえた。ガウッガウッ、危険を感じた私はうずくまる。
その時熊の姿が見えた。その熊は何かおどおどしながらまわりを見て歩いていた。親をみると何かさびしいような表情だった。それは何か今の私の気持ちと同じように感じた。
私はその熊のことが気になり後をつけていった。気付かれないように…。その時の私の気持ちはだるまさんが転んだをしているような感覚だった。すると突然目の前の森がどこかに消え、川が見えた。川の向こうにはまた森がある。新しい風景に驚かされ不思議さを感じているとき……
〃バシャー〃と大きな水の音が聞こえた。
私は言葉を失った。
さびしそうな顔をうかべていたあの熊が一匹の大きな魚をくわえて食べている。自然の厳しさを自分の目で見たのははじめてでとても心がいたく自分でもその痛みを感じた。これが自然の摂理なんだと……。
〃あっ〃カメラを手にすばやくもちかかえてシャッターを押そうとしたとき不思議な出来事がおこった。あまりの不思議さに私はシャッターを押せなかった。
鳥だ…白い鳥だ…自分に言い聞かせながら現実へと戻っていく…。熊のまわりに白い鳥が舞い降りてきた。一匹じゃない、十匹以上も…。
しかし熊はまわりの気配など気にせず魚を食べ続けた。まただ……白い鳥が熊の方を向いているではないか。
またその白い鳥は熊を囲むようにしてずっと見つめている。もう一度私はカメラをかまえなおして、不思議の世界にとけ込めていない私は、ふるえている手を必死で押さえながらシャッターを押し続けた。フィルムが切れていることも知らずに不思議な世界へとひたっていた。熊が私の方を向いたときの表情は満足そうな幸せそうな表情だった。私は全てのことがわかった。自然という過酷な地で弱肉強食があたりまえのことであり、命は一つのエネルギーに過ぎないと。誰かを犠牲にすることで自分の新たな命を生み出すと…。
私は今までどれくらいの命を食べてきただろうか。
そんなことを考えながら夕日を見ていると白い鳥が飛んでいった。
15

「つながり」
私は、撮影のため、アラスカに向かった。飛行機の中からアラスカを見ると落ち着けなかった。空港からスタッフに車を運転してもらいさっそく撮影をしに向かった。車から見える看板を見ると「アラスカに来た。」という気持ちでいっぱいになった。
十代のころ、アラスカにあこがれていた。ある日東京の神田の古本街の洋書専門店で、一冊のアラスカの写真集が私を待っていたかのように目の前にポツンと置かれていたのだ。そうして学校へ行くときも、どこへ行くときにも持ち歩くようになっていた。その中でも、北極圏のあるイヌイット村の空から撮った一枚の写真は気になっていた。
初めは、その写真のもつ光の不思議さにひきつけられたのかもしれない。しかし、だんだん村が気になりはじめた。
村の人はなぜこんな所で暮らさなければならないのだろう。どんな人々が何を考えて生きているのだろうと考えたりもした。そして、私はその村の人々に会ってみたいという気持ちになった。
そうして、数年たったある日の朝、ある会社から依頼の手紙をもらった。依頼の内容はアラスカの景色を写真におさめ送ってくれ」といってきた。そうして私はあこがれの地アラスカに飛ぶことにした。
車を止めて、雪道をモービルで進むことにした。さすがアラスカ素晴らしい景色が一面に広がっている。その時に妙な感覚になった。景色に対しての感動でも好奇心でもなかった。
雪道を進むと遠くに影が現れた。それは一匹のあざらしだ。アラスカで初めて出会った野生の生き物だった。私は近づいて写真を撮ろうと思った。あざらしにかなり近づいたがあざらしは逃げずに私をじっと見つめていた。
さっそくカメラの準備もできたので、撮ろうとした。しかし、真っ黒の目で見つめてきた。私はシャッターを切った。その時にまた妙な感覚におそわれた。今度は確かにその感覚を理解できた。
それは、限りなく続く真っ白の雪に、太陽の光が射して目の前で一匹のアザラシがこっちを見つめているだけだったが、私がよく見つめてみると、何もない白い世界で一匹寂しく生きていたアザラシのように見えた。そこへ私が来たから、真っ黒の目で私に寂しい気持ちを伝えようとしているようだった。
目の前にいるアザラシ、周りの自然の景色、これは偶然私が依頼を頼まれたからうまれたことであり、アザラシに会えたのも、偶然出てきたからうまれた。たった一つのことで私の人生をかえられたといっても過言ではない。しかし、私が今まで生きてきた人生を後悔するようなことはないだろう。
16

「自然と人生」
星野さんは19歳の時にアラスカに行き、日本ではけっして体験できないこと、けっして見ることのできないものを見てきた。ただアラスカに行きたいから行く。いかにも動物的な考え方だ。この考えが、のちに星野さんがアラスカに根をおろす要因だった。
初めてアラスカに降り立ったとき、星野さんはいったいどんな暮らしをしていたのだろう。シシュマレフ村の人々も、会ったことも話したこともない東洋人を、かんたんに受け入れはしないだろう。
「なぜあんなやつが来るんだ。」
「英語もしゃべれないで来るなんて非常識だ。」
などと言われたのかも知れない。この孤独を、星野さんは日本でも体験していた。
電車から見える家族団らんの風景を見る度、星野さんは胸が締めつけられるような思いがしていた。星野さんの家庭に団らんはなかったのだ。
「ただいま。」と言っても返事は返ってこない。
こんな家庭で暮らしていたのだ。
アラスカでもこんな生活を送るのかと思った。しかし、アラスカには動物がいる。白クマ、アザラシ、トド、カリブー…。例を挙げればきりがないほどの動物に出会った。孤独感は消えていき、暮らしにも慣れた。アラスカに行くきっかけとなった、カリブーの写真は、動物たちにかこまれて暮らせば、孤独は消えていくということを表していたことに気付いた。
7年後、再びアラスカへ行き、この写真を撮った。撮らずにはいられなかったのだ。白クマに限らず、動物は、群れや家族で行動を共にする。この白クマはまさしく、学生時代の星野さんを表している。一匹で孤独に立ち向かい、遠くをひたすら見つめている。その目には、今までいた群れか、家族が映っていることだろう。
この姿に、星野さんは涙した。孤独から解放され、アラスカに戻り、再び孤独を目にする。この白クマの歩く先には、孤独は無いで欲しい。そんな思いで星野さんはシャッターを切った。
17

「カメラの空間」
私は急に写真を撮りたくなった。
すぐに持ち運びできるようにしてあるバッグをつかんで、お世話になっている家を飛び出す。
そういえば、昨日雪が少しつもっていたな。もうとけてしまっただろうか、と、あれこれ考えているうちに、森に到着した。
カメラを片手にウロウロ歩いていると、木がはえていない、小さな広場のような草原に出た。燃えているようにたって、生えていた、青々とした草の上には白い雪がたくさんのっかっている。三脚をバッグから取り出しながら、けっして日本では見られない自然をながめた。
「おや星野さん。」
ふりかえると、そこには一人の村人が笑顔で立っていた。
「やぁ、こんにちは。お一人でどうなさったんです?」
とても本場の英語になりきれないそれに、散歩ですよ。とあたたかな返事が返ってくる。
「こんな森の中でも、偶然人間が会うこともあるのですね。」
私の頭の中にでも、突然、今まで見てきた動物達が浮かんできた。それが引き金だったかのように、村の人々、一通の手紙。そして昔、あの古本屋で見つけた本にあった、つい先刻までいた村の写真の記憶がおしよせてきた。
「どうしたんですか?」
怪訝な顔をした村人に声をかけられ、ハッとした。何でもないと言うと
「本当ですか?ボーッとしちゃって。この寒さで風邪でもひかれたのですか?」
「いえ、ちがいますよ。大丈夫です。」
「そうですか?それでは散歩をしながら私は村に戻ります。星野さん、写真もほどほどに」
森に消えていく村人に手をふってから、景色に目をもどした。
白に覆われた山、白にかぶされてなお輝く草、そして真っ白である雪。
これを自分の手で小さなわく入れてしまった時の充実感を思いふるえた。
もしかして、彼もそうだったのだろうか?
昔、私の一番の宝物だったあの写真をとった……
あぁ、もしかして、彼にとってのあの一枚が自然をとったあの一枚は、今まさに私が撮ろうとしているこの一枚とどこか似ているのかもしれない。
その考えは、一瞬頭にうかんですぐに消えてしまった。代わりに、昔、写真集を買った古本屋、その写真集、出した手紙とその返事、と、思い出が次々おしよせてきた。
そうだなぁ。よく、あんな、たくさんある本からあの一冊を見つけたなぁ。よく、手紙なんて出そうと考えたなぁ。よく村長さん、受け入れてくれたなぁ。
そして気が付いた。
私の人生には〃偶然〃が多い。
私だけのことなのか、そうでないかはわからないが、私は偶然に感謝したいと思った。
あの北海道を目指していた頃なら絶対に出会えなかったことに出会い、満ち足りた生活を送れているから。
これからも、そんな良い偶然に、まさに今とろうとしている素晴らしい風景に出会えるように祈った。
カメラをのぞき、今現在私が居るこの空間をカメラにおしこめている時、つもった雪の中から小動物が鼻をだした。
二本足で立った。まるでこちらを見るようになった。
たまたまカメラに入ったそいつを見て、この一枚に入った空間を写真集にのせようと思った。
軽く微笑んだ。
そうして、私はシャッターをおした。
18

「赤」
山を登る。
一歩一歩、岩をふみしめて、ゆっくりと…私は、山を登った。
「星野さん。あと一時間ですよ。」
後ろについている地元の案内の人が私の肩をたたいた。
もう少し、早めに出発しておけばよかった…。
左手にはめている銀時計を見る。
「少し、急いだほうがいいでしょうね。じゃないと、せっかくのアレが見れなくなる。」
自分が山登り用の杖ではじいたじゃりが、転がって戻ってきた。
今日は厄日なのかもしれない。
明日は晴れそうだからと思って、この山に登ろうと決めたのは昨日の夕方。
急な話だったが、ガイドはちゃんとついてくれるようになり、私は安心して床についた。
目を覚ますと、もう日は高い位置にあった。
急いで作った朝食、いや、もうそのように呼べる時間帯ではないが、とにかく胃へ流しこみ、登山道具をかかえて家を出た。
そして今、思っていたとおり、時間はたりなくなり、その上どこからか、雲まで出始めている。
その雲は少しずつ厚さを増し始めていた。
…これは私に対する嫌がらせか。
心の中で、頭上に広がる奴らに少し文句を言ってやった。少しにらんでやった。天候は変わらない。
まあ、人生こんな日もあるだろう。
私は、もう一度、杖に力をこめた。
「こりゃあ、だめだなぁ」
頂上についた私は、肩を落とした。
厚い雲がずっと先まで続いている。
自然は、自分の手では動かせない。人工物のような生やさしい物ではない。この一すじ縄ではいかない大物にひかれ、この仕事についた私だが、やはり、見たい物が見れない寂しさはある。
しかし、無数の偶然の可能性の中で、自分の求めていた偶然に出会える喜びを忘れないからこそ、この仕事を続けているのだろう。
「今日はあきらめましょう」
私は少しぐずついた足どりで、来た道を戻ろうと方向を変えた。
ふみ出した片方の足に光があたった。
案内の人が、驚いてふりかえった。
光はだんだんと広がっていく。
私はやっくりと、その方角へ顔を向けた。
空が赤かった。
赤色、紅、緋色、朱、丹、茜色、暗紅、唐紅色。
自分が日本人でよかった。これだけたくさんの赤を言葉で表現できる国に生まれたことに感謝した。
いや、これだけでも足りないだろう。
周りの山で反射した赤と空を伝って地平線からのびてきた赤が私を包みこむ。
かばんから相棒を取りだし、シャッターをきった。涙でぼやけた。
私は今日また、自然の奇跡の目撃者となることができた。
そしてまた、この不思議さにはまっていくことになるのだろう。
今日は厄日だった。
(でも、それは、過去の話)
19

「夕焼け」
夕焼けをみた。日本とちがい、空がとてつもなく広いから、油断していると簡単にすいこまれそうだ。私は仲間から連れられて、この場所にきた。
「今の時間は夕日がとてもきれいだから、いい絵が撮れるよ。」そう言われて。
第一印象は「赤」だった。ぐるりと一回転してみても目に映るのはやっぱり赤で、それは私になつかしい人を思い出させてくれた。母である。
優しい人だった。常に私を支え、見守り続けてくれた。私が突然はるか遠くの土地、アラスカに旅立ちたいと言い出した時だ。母に、なぜアラスカなのか、そこで何をしたいのか、はっきりと言葉にして説明することができず、もどかしかった。なんと言えばいいのだろう。夕暮れ時で、どこからかみそ汁のいいにおいがしていた。それがなぜか私を焦らせた。しかし彼女は、私の目をまっすぐ見て、
「あなたの人生なんだから、好きにしなさい。たくさんのものをその目に写して帰ってきなさい。」
と、おだやかに言った。何かいいものがひろえるといいわね、と笑って。
目の前が急にひらけたような気がした。焦りも消えた。窓から見える空は、見事に夕焼けだった。
会いたい。 当然無理だ。現実がじわりと心に染みこむ。
しかし、見上げる空は優しく笑っていた。
自然は偶然によって作り上げられている。一瞬でこんな素晴らしい風景を描くと同時に、今は会えない遠くの人と、こんな形で再会させてくれる。
誰にどう感謝をしてよいかわからなくて、またもどかしい思いをするのだけれど。今はそれすらも心地良い。
私がひろったたくさんのものを、あなたに届けたい。
私はゆっくりとカメラをかまえた。
流れる雲の間から、優しく「赤」が降ってきて、私はそれにしばしつつまれる。
パシャ という小気味よい音が風に運ばれて消えていった。
20

「写真を見て感じたこと」
星野さんは、一枚の写真を撮ろうとしていた。
カメラのレンズを通して、2匹の熊を見ていた。2匹の熊を見ながら悲しみを感じていた。
「なぜ、母熊がいないのだろうか?」
「もしかしたら、死んでしまったのだろうか。」
悲しみを感じながらも、カメラのシャッターを切った。
この写真はやがて一冊の写真集となって売り出された。
2匹の熊の写真は、星野さんの気持ちと、熊の思いがとじこめられた写真となっていた。
この写真には偶然が無数につながって、ある人にたどりついた。
学校の先生は、この写真集を買って、生徒にこの時の心情を考えるように言った。
星野さんの気持ちがたくさん入っている写真の中で、ある人たちが、あの2匹の熊の写真を選んだ。
この2匹の熊の写真を選んだ人は、この2匹の熊の写真を見て、何を思うかを小説にしていた。
アラスカのある2匹の熊を写している写真を見て思うことを考えてみよう。
そしてその時の星野さんの気持ち、考えてみたときのことを思ってみよう。
「母熊がいないから、母熊は死んでいるのかな?」
「家族が他にはいないのだろうか。」
「熊として生きていることに、どう思っているのだろうか。」などなど考えていたとき、「星野さんの気持ちはどうなんだろうと考えていた時、写真をとった星野さんは、こんなことを思っていた。シャッターを切ってしまった後、カメラをおろして、星野さんはあの2匹の熊を見つめてまたこう思っていたのだろう。
「この写真を見て、見た人はどう思うのかな。」
「この写真を見て、同じことを考えてくれるかな。」
と思っていたことが無数の偶然によって今、僕たちによって、この星野さんの気持ちが考えられていた。
21

「写真」
カヤックに乗って海に出る。天気は曇りだ。晴れればいいのに、と思いながら静かに穏やかな波の間を進んでゆく。今日はどんな写真を撮ることができるのだろうか。
私がこの地に住むことになったきっかけは神田の古本屋で見つけた一冊の写真集だった。どこへ行くにも持って行くほどの熱心さで、自分でも驚くほどだった。その写真集の中でも特に気になる写真があった。ジョージ・モーブリイという人が撮った写真だ。灰色のベーリング海、雲間から差し込む太陽、ぽつんとたたずむ民家…。なぜ私はこの写真にひかれたのだろう。たいして特別な写真、というわけでもなかった。ただ、その写真の持つ雰囲気にひかれたのだ。気がつけば私はこの地に来ていた。19歳の夏のことだった。
天気はまだ曇っていた。まだ、自分の撮りたいと思う風景は見えてこない。
私の一回目のアラスカ滞在は三ヶ月で終わった。それは一時の感情にまかせてアラスカに行くといった、つっぱしった行動にたいして十分な時間だったと思う。それだけの期間だったなら、アラスカに行ったこと、自分の行動を冷静に考えることもできただろう。普通の人ならたぶん選ばないだろうという道について。しかし、7年後、私は再びアラスカに帰ってきた。今度は写真に見せられたのではなく、自分の意志で。たとえ無数の偶然が積み重なっていたとしてもこれは自分で選んだ、自分の人生だ。
雲間から光が差し込んできた。遠くに鯨の尾ひれが見えた。目の前の景色がとても愛おしいものに思えて、私は夢中になってシャッターを押した。何もかも吸い込んでしまいそうな黒色の海、雲間から差し込む太陽、ぽつんとたたずむクジラの尾…。ふと気付いた。これは、あのジョージ・モーブリイの撮った写真にそっくりだ。
ジョージ・モーブリイもこんな気持ちで写真を撮ったのだろうか。彼もこんな景色に囲まれて、シャッターを押したのかもしれない…そう思うと見たことのないジョージ・モーブリイが身近に思えて、少し笑えた。
私のこの写真も、誰かの人生を変えるのかも知れない。無数の偶然の中で、たとえばどこかの古本屋で、偶然私の写真と出会い、自分の人生を変える人もいるのかも知れない。その人は私のことをうらむだろうか。自分の人生を変えたのはあなたの撮った写真だ、と。しかし、それがいくら無数の偶然の上に成り立っていたとしても、それを選ぶのは自分だ。それに、この写真を見ることで選び取る人生が増えて、その人が自分の人生を進めればいいと思う。
何より、私は自分の見た風景を他の人に伝えたい。私はその写真を他の人に見せることで自分の見た風景を見せることだ。それは、間接的とはいえまだ見ぬ人に会う方法、そして、数多くの人に出会う方法の一つなのだ。
雲はどこかにいってしまい、空は青く光っていた。私は光の降りそそぐ海の中をゆっくりとカヤックを進めた。
22

「偶然とクジラ」
「星野さん、クジラが来てますよ。」
ガイドを頼んだシシュマレフ村の若い男が言った。
アザラシを撮るために海岸にやってきた私たちは、クジラの群れを発見した。
「あのクジラは何という名前のクジラですか。」
私はガイドに聞いた。
「ああ、あれは、ザトウクジラですね。」
「めずらしいものなのか。」
と私。
「いえ毎年来ていますよ。」
ガイドは珍しくもなさそうに言った。
「知らなかった。」と私は思った。もう五年もこの辺を写真で撮り続けて来たにもかかわらずまだまだ知らないことがたくさんこの世にはある。
「バッシャーン」
こんな音が辺りにひびきわたる。何事かと振り向けばクジラがジャンプしている。私は夢中でカメラをかまえクジラのジャンプを撮る。
「星野さんよかったですね。クジラのジャンプって結構めずらしいものなんですよ。」
とガイドは言うが私は聞いていなかった。そうすると一瞬クジラの目をとらえた。何と悲しそうな目をしているのだろうか。そんなことを私は思った。あの目は、私の昔の目によく似ている。あのとき私は、なかなか出会えないものに出会いたいということで胸がしめつけられるように気がしていたように思う。
今思えばなぜあんなことで胸がしめつけられるような気がしたのか不思議である。なぜならアラスカには動物園には絶対いないような動物、なぞめいた行動をする動物。雪に埋もれながらも新芽を出して生命のいぶきを感じる植物。そんなたくさんのものが私を出迎えてくれる。そんなアラスカは神秘に満ちている場所である。
「では次にいこう。」
次の偶然の瞬間を撮るため、ガイドに声をかけた。
23
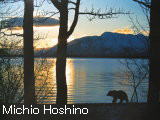
「出会い」
僕は大自然の中で大きなクマに出会った。
それは日が沈みかけて暗くなろうとしているところだった。
僕は湖の近くで休んでいると目の前に大きな黒い物体が突然現れた。
目をこらしてよく見るとそれはクマだった。
僕は思わず手に持っていたカメラで写真を撮ってしまった。写真を撮りながら僕は思った。
「僕はこのクマと出会った。」
でもクマにしてみればどうだろうか。クマは僕という存在に気づいていない。つまり、クマにとっては僕とは出会ってはいないというのだ。そんなことを考えているとクマはもういなかった。多分自分の帰る場所に帰ったのだ。
やどに帰る途中僕は思った。本当の出会いとは何だろう。互いが出会うことを実感できるのは人間どうしだけなのだろうか。本当に人間とその他の生物が出会うことができないのだろうか。いや出会うことはできるだろうしかし動物たちはこころよくうけいれてはくれない。まるで、敵がきたというようなかんじだろう。
やどについて、部屋のまどから空を見ながら考えた。だとしたらなぜ僕はここにきたのだろう。そうだ、あの本だ。神田の古本屋で見つけたあの本だ。あの写真だ。しかし、僕はあの写真を撮ったジョージ・モーブリィと出会ったことはない。
でも、たしかにあの写真がきっかけで僕はアラスカに行ったのだ。そして、多くの人々、自然に出会った。多くのアラスカの神秘を見てきた。
出会いというのは実に不思議だ。どんな形であったとしても、僕は多くのものと出会った。僕はクマと出会った。その現実は変わらないのだ。
僕は時計を見て、明日の準備をしながら思った。
-もしかししたら、ジョージ・モーブリィと出会うことができるかもしれない-
そう思うと、少し希望がわいてきた。
準備が終わり、もう一度僕は空を見た。アラスカの夜空がいっそう美しく見えた。夜空を見ながら、僕は過去をふりかえってみた。出会った人々、自然、動物たち、そしてアラスカの神秘。そして、最後に僕はもう一度思った。
-出会いは不思議だ-
24

「出会いの環」
僕はアラスカに来てたくさんの出会いを経験したもしあの時モーブリイ氏のあの写真に出会わなくても、きっと今ここに立っていることは変わらないだろう。僕がここで写真を撮るのは必然だったのだろうか。
バシャ バシャ……
目の前の川を熊がゆっくりゆっくりと歩いている。
前の一頭と後ろの一頭はそれぞれ波紋を生み、それはお互いの作り出している波紋と重なっては消えていく。夕日によって紅く染まった空が、熊の姿を優しく照らしていた。
僕は何故だか彼らを撮るのなら今しかないと思った。
アラスカに来てたくさんの出会いを体験したからの勘だろう。今を逃せば、彼らと会うことは二度とない、そんな感じがしていた。
日本では決して出会えなかった彼らだが、ここで会うことができた。
そんな偶然を写真として残すことは僕にとってもその写真を見る人にとってもきっと重要な意味を持つだろう。
僕にとってジョージ・モーブリイ氏のあの一枚がそうであったように僕の撮るこの一枚が、誰かにとって重要な意味を持てるだろうか。いや、これを僕が考えてもしかたがない。見る人が変われば、その写真の持つ意味も変わるものなのだから。
「星野さん、そろそろ帰った方がいいのでは…」
この場所に案内してくれた彼がそっと声をかけていた。
写真に熱中しすぎて、彼のことをすっかり忘れていた。後ろにいる彼を振り返れば、紅い夕日に照らされ、紅く輝く彼の顔があった。
「きっと今、自分の顔も紅いのでしょうが、星野さん、あなたの顔もとても紅いですよ。紅いのにいつにも増して優しそうに見えます」
僕はゆっくりとうなづいて、それから笑った。今、世界はただ紅いのだ。青い山々もすみわたった川も、すべてが紅く染まっている。それは僕も例外ではなかった。あの夕焼けの日、電車の窓から見えた家族と出会うことはなかった。それどころか、彼らはきっと僕のことを知らないのだ。彼らが僕に出会いたいと思わなければ、出会いにはつながらなかったろう。そして、ずいぶんと時がたってしまった今、あの家族に僕が出会うことは、きっとない。それを考え、それでも僕はあの時のような悲しみを感じることはなかった。何故なら僕はこの世界に拒まれているわけではないことを感じたからだ。
僕はゆっくりとシャッターを切った。
全てを包み込む、この紅い夕焼けの世界を誰かと出会わせるために。
25

「僕を見つめて」
今日はいつも以上に寒かった。しかし、カメラをにぎる僕の手はあつかった。周りには誰もいない。真っ白な雪景色がどこまでもどこまでも続いていた。
「僕はなぜここにいるのだろう。」
ふと、心の中でじぶんに問うてみた。自分でも答えは分からない。だが、僕がこの地にひきつけられたのは確かで、今もこの地にこがれている。
* * * *
最近寒い日が続いている。昨日、仲間と争ったキズがまだ生々しくのこっている。
「ザクッザクッ」
誰かがこっちへ近づいている。誰だ。ヒトの臭いがする。イヌイットか。誰が来ようと俺には関係がない。朝日が輝いている。あぁ、今日も一日がはじまる。あいつは元気だろうか。もうこの世にいないあいつは、元気なのだろうか。
* * * *
朝日が美しい。あぁ、なんてすがすがしいのだろう。
「ウォー」
なんだろう。遠くでシロクマの鳴く声がする。ゆっくり、ゆっくりと道をのぼっていく。足音をたてないように、ゆっくり、ゆっくりと。見つけた。白くまだ。一匹の白くまが、朝日に向かってさけんでいる。まるで何か大切なことを伝えようとしているかのように、見えた。
* * * *
「なぜなんだ」
毎朝、朝日に向かってさけぶ。
「なぜ、あいつは死んだんだ」
俺は一人、とりのこされた。孤独だ。こんな人生なら俺はあいつのかわりに死にたかった。今ごろあいつはイヌイットの服になっているのだろうか。それとも食べ物になり、彼らの胃の中なのだろうか。分からない。「偶然」ということはなんて苦しいのだろう。
「偶然、イヌイットに出会い、うたれた」
なんておそろしく悲しいのだろう。熊としての一生を終えるには、とても無惨だった。だが仕方のないことだ。おそらく、あいつと俺が出会ったのも「偶然」のことなのだ。
* * * *
人のような目をした白熊は、何か考え事をしているようだった。そしてふと、僕は気が付いた。熊の目のおくにあるものを、僕は見てしまった。かばんからカメラをとり出す。ピントを合わせる。
「カシャ」
美しいシヤッターを切る音が響いた。
26

「偶然の出会い」
僕は軽くため息をついた。
今日の朝、僕は勇みたち、興奮して出かけた。友達から見せてもらった写真を見て、いても立ってもいられなくなってしまったのだ。僕はその景色にすっかり魅了されてしまい、なんとしても自分の目で見てみなくては気がすまなくなってしまった。しかし、雪と氷と光でできた造形は陽の光に溶かされてあとかたもなかった。そこにあったのは小憎らしいほどにすみきって美しい川の流れだけだった。この寒いアラスカにおいて暖かい陽光は限りなく優しく輝く。しかし、この時ばかりはその暖かさが恨めしかった黄色い太陽がまぶしく輝き、思わず顔を背ける。その僕の目を小さなキラリという一瞬の輝きがとらえる。川に小さく浮かんだ残雪がなぐさめるかのように僕を見上げる。出会いたいのに出会えない。いつもそんなにすれ違いばかりだ。自然が相手なのだから当たり前だが…。そう思った時、ふと、今日自分は友人が見たその景色を見られるだろう、自然は自分にそれを見せてくれるだろうと勝手に自分で決めつけていたことに気付いて苦笑した。自然がそんな約束をするものか。自然が人間の思う通りになるわけがない。自然が自然であるから、出会いがあって、その変化がすばらしいのだ。
* * * *
自嘲気味に考えながら歩いている時に、背中にくすぐったいような不思議な視線を感じて振り返った。そこにいたのは雪よりも白い北極ぎつねの子供だった。僕たちは見つめ合った。真っ黒なクリクリした目がキラキラ光って僕を見つめる。何だこいつ、まだチビのくせにやたらと大人びた目をしている。そう思って僕がフワリと笑うと、子ギツネの目もフワリと柔らかくなる。ああ、少し幼い色になった。その時、僕たちの上にあった雲のすそから光がこぼれ、僕等の間に光が差し込んだ。その光が僕等の間にほんのすこし残っていた緊張を溶かしていった。
僕は思わず首に下げたカメラをとり、シャッターを切った。
透きとおった空の下で、白銀の雪の中で彼の柔らかい純白の衣が豊かに波打つ。
* * * *
気がつくと子ぎつねは駆け去っていた。
残された僕は満ち足りた気持ちでカメラを見つめ、出会いたい時に出会えなかった、とさっきまで落ち込んでいたことを頭の一隅で思い出した。そして考えた。僕はさっき出会いたいものに出会えなかった。出会いたいのに出会えない、すれ違いを偶然が結びつける。偶然が、無数で多様な出会いを導く。だからこそ、その偶然の出会いをしたくて僕はこのアラスカにやって来た。いやもしかすると、アラスカとの出会いが偶然でありながら必然であったように、僕の多くの出会いも自然が結びつける必然なのかも知れない。僕にそれはわからない。僕はただただ出会いたい。自然が引き合わせてくれる出会いに会いに、さて今日はどこに行こうか。
27

「私がひかれたもの」
私は今、北極に近いところに行く。もちろんここにきたのは偶然ではない。この北極に近い場所でオーロラを撮ってみたいという目的があったからである。この辺境の地で、今現地ガイドに、オーロラの見える場所まで案内してもらっている。
「ガイドさん、、後どれぐらいしたら着きますか?」
「後5、6分です。」
沈黙が流れる。ここには、一人で写真をとりにきたわけだから、ガイドと私しかいないし、私はまだいろいろなことをしゃべれるほどこの国の言語をマスターしていなかったのだ。しばらくして、目的地に着いた。まだオーロラが見ることができるほど暗くはなっていないので、早めの夕食をとることにした。いつも通りのレトルトカレーである。夕食も食べ終え、食器も片付けたあたりから、周りが暗くなってきたのでカメラをセットした。さすがに自然の産物なのでなかなかオーロラが現れなかった。しばらくして、大きな赤いオーロラが見えたので、見ることにした。
オーロラはキラキラと多彩な色で輝いていた。
こんなにきれいなものなのだろうか。
「あー。」
思わず声が出てしまった。私は今までこんな自然で広大なものを見たことがなかった。
「そうですね。」
ガイドさんが言った。
「こうしてみると落ち着きますよ。」
ガイドは顔をニコニコして言った。
一瞬、私はガイドさんを不気味に思った。
「なぜ、ニコニコしているのだろう。」
私の不思議そうな顔を見て、ガイドさんは答えた。
「オーロラなんてものは、見あきるほど見たけどやっぱり見れば見るほどいいもんですよ。」
ガイドは自信に満ちあふれていた。
しかし、自然とは不思議なものだ。私のかたわらにいるガイドのように自信に満ちている風景を見せてくれる。私は、それにひかれ写真を撮り続ける。そしてその写真を本にする。その本は日本だけでなく、様々な国々の人々が見る、いや見てくれるのである。私はそれを喜びと感じ、そして、その本を見た人がこの世界の自然に興味を持つことを望んでいる。
28

「カヌーという人生」
「ここは本当にすばらしい居場所だ、こうしていることが私の本当に生きているということなのだろう。」そう私は周りの自然に囲まれながらしみじみと思った。そもそもなぜこんな人生を送ることになったのだろう。すべての始まりは一枚の写真からだった。高校生の時見つけたあの写真、私はとても心を動かされた。あのときこそ人生の中での最もすごい偶然だったのかも知れない。その偶然に人生を動かされたのかもしれない…。
ジョージが撮った写真は、私にとっては、どれも感動的なものであった。私はあの時までは、〃写真〃というものの意味をよく理解できてはいなかったが、今こうして、あの写真を撮った当時のジョージと同じように、いろいろな土地を巡り、色々な人、色々な動物、色々な光景に出会いながら、それらをこのカメラの中に収めると言う仕事をやり始めてからは、少し変わったような気がする。
もしあの一枚の写真に出会わなかったら、私はいったい何になっていたのだろう。私は写真を撮ることで、色んな場所に行き、たくさんの人と出会い無数の偶然と出会った。ジョージもきっとこんな人生だったのだろう。
ある日、私は偶然的にジョージと出会った。そしてジョージは私に「人生に後悔しているかい。」と尋ねてきた。私は少し考えた。確かに、こういう人生でなく、もう一つの人生を生きていたら…。と考えると、ワクワクするし、とても楽しい。しかし、楽しい人生を想像するということは、自分が生きてきた人生が楽しいものだったからだと思う。もし、つらい人生だったら、ワクワクしないだろう。だから私はジョージに「後悔していない、むしろ誇りに思っている。」と答えた。人生とは無数の偶然で成り立っている。だから今私はこのカヌーの上にいるのだ。今、この景色を見ているのだ。そして、私はこの人生をふり返ることが少なからず未来の私の偶然ということになるのだろう。ある日、私に一通の手紙が届いた。内容は「あなたの写真を見ました。ぜひ会わせていただきたい」というものだった。私は考えた末、「いいでしょう。いつでも会いにきなさい。」と送った。これも何かの偶然なのだろう。これから私の人生はどうなるかわからない。ただ、ジョージにいった言葉に責任と自信を持って、後悔しない人生を送りたいと思う。
29

「つながり」
夕暮れ時、僕は一緒にアラスカの山々を撮っていたカメラマンと村への帰り道を歩いていた。今日は、夜の写真を撮ろうとは決めていなかったので早めに村へ帰って、村人の手伝いをしようと思っていた。「今日の夕焼けはとてもきれいですね。星野さん。」
ぼんやりしていた太陽がゆっくりと下へさがっていく様はきれいで見る者の心を動かそうとする。だが、同時に胸を締め付けられるような痛みも伴った。きっと隣にいるカメラマンの人も同じ気持ちを味わっているに違いない。僕の名前を呼んだが別の人に言っているように聞こえたから。「あ、あれはなんですか?」
カメラマンの言葉によって見てみると、キツネか何か分からないが小さい動物が丈のあまり大きくない草に囲まれ、ふるえていた。山で生活する動物のはずなのだが、迷子になってしまったのか、村に近いところまで来ていた。この動物を見ているとどこかが自分とかぶる気がしてても放っておく気にはならなかった。「さきにもどっていていいですよ。ちょっといい写真が撮れそうな気がするんです。」
カメラマンの人は、では先に戻りますね。と穏やかに言って別れた。村へ帰るその人の背中がだんだんと小さくなっていく、そういえば、子供の頃にもだんだんと小さくみえなくなっていく背中をみた気がする。そうだ、自分もあの時、迷子になった。
次々とあらわれる子供連れの親子。自分しか乗っていないブランコ。大きな公園で途方に暮れてしまったあの時、世界でひとりぼっちなのではないかと思ってしまった。だからだろうか、一匹しかいない小さな動物の風景と小さな時の自分の気持ちが共鳴した気がする。私はカメラを握りしめた。あの時の気持ちを、この写真をみて、思い出せますように。そう思い、レンズ越しに小さい動物をみた。もしかしたら、あの時の自分を見守ってくれた人がいただろうか。いてくれたら、とてもうれしい。
パシャッ
カメラを撮った音があたりにひびいた。もうぼんやりとした太陽は下の方にいる。はやめに帰らなければならない。一人で夜道を歩くのはとても危険だ。ゆっくりと村の方向へ体をむけると、草の原っぱをかける一つの音がした。あの小さな動物の親が子供に向かって走ってきたのだ。どうやら僕を警戒して出てこれなかったらしい。けれどやはり、子供のことをきちんと親はみていた。ひとりぼっちではなかったのだ。親子は走っていってしまった。それを見た僕は、ゆっくりと村へと向かって歩き出す。あの親子は、もう巣へと帰っただろうか。僕はだんだんと暗くなっていく空を見上げ、ゆっくりとほほえんだ。
「今日一番の写真が撮れた。」
村へと向かう足どりは軽く、小さなあかりが村にともっていた。
30

「人生とは」
見わたすばかりの青い海。私は今、船の上にいる。知り合いのカメラマンにクジラの写真を撮りに行こうと誘われたのだ。しかし、いざ現地につき、船に乗ったものの気分が乗らない。最近いい写真が撮れていないのだ。いい写真とは自分の納得のいく写真のことだと思うのだがそれが最近撮れていない。こんなことでいい写真が撮れるのだろうか。愛用のカメラをいじりながら考えていた時だ、船の乗員が「星野さん、クジラの群れが見つかりました。もうすぐでポイントにつきます」と声をかけて来た。私は「そうですか」と短く返すとまたカメラいじりをし始める。すると、目の前にすわっていた同伴者のカメラマンが口を開いた。「どうしたんですか?星野さん、あまり嬉しくなさそうですね。」彼は私とは反対に嬉しそうだった。私は「いや、嬉しくないわけではないんですが…。」と語尾を濁した。「?ならなぜそんな落ち込んだような顔をしているんです?」かれは小首をかしげている。「最近、自分の納得のいくような写真が撮れていないんです。それで…自信というかやる気がなくなってしまって…。」私ははぁとため息をついた。すると彼は「カメラマンの仕事は好きですか?」と私に聞き返して来た。私は始めどういうことなのか分からなかったが、とりあえず「好きです。」と答えた。「なら。」彼は一呼吸すると「いいじゃないですか。カメラマンは写真を撮るのが仕事です。写真を撮らなければそれはもうカメラマンとは呼べない。カメラマンが好きだということは写真を撮ることが好きだということだ。嫌いなものには自信もやる気も付いてきません。写真を撮って撮って撮ってそうやっていればいつか自信ややる気も出てくるんじゃないですか?ほら好きなことなんだから。」そう言ってにこりと人のいい笑顔をうかべた。
私はまだしっくりとこなかったが彼につられるようにして笑った。「星野さんポイントにつきましたよ。」乗員の言葉に私はカメラを片手に船の甲板へと向かった。「星野さんこっちです。こっち。」知り合いのカメラマンが甲板の前方で手招きする。私は誘われるままそちらへと足を運んだ。彼はもうカメラを構えシャッターを切っていた。私も写真を撮ろうとカメラのレンズをのぞき込んだ。レンズの中には富士壺のたくさんついた大きなザトウクジラがうつっていた。それを見てふと昔同じようにザトウクジラを撮りに行った時のことを思い出した。その日、私は鯨と初めて会うということでドキドキしていた。クジラたちはテールステップやブロウなどをして私の目を楽しませてくれた。その後同伴していた仲間からは、「子供みたいにはしゃいでいたる」とクスクス笑われたことをも思い出した。ジョージと出会う数年前のことだ。するとどうだろう、今までのやる気のなさや自信のなさがすっとひいていくではないか。私は夢中でシャッターを切った。隣で他のカメラマンの「クスリ」と笑う声が聞こえてきたが、そんなことにかまっているひまはない。一枚、二枚、三枚とどんどんと増えるクジラの写真。それらはどれも自分の納得のいく写真だった。甲板から部屋へと戻ると、カメラマンがストーブに冷えた手をかざしていた。いくら手袋を付けているとはいえ、カメラを握っていたその手は赤くなっていた。彼は私を見つけると「いい写真が撮れましたか。」と笑いながら言った。私も「はい。」と笑った。「にしても今回はクジラたちはサービスしてくれましたね。」クジラたちのテールステップのことだ。「そうですね。」私は思い出すように笑った。
31

「無題」
それは、季節はずれに咲く、花のように……
咲いてもすぐに散る、儚い花のように……
いくら咲いても、実を結ばない
僕は、徒花。
アダバナ。
「ミチオ、ちょっと来てくれ」
延々と続いている銀世界を眺めていると、一緒にいたガイドのルイスさんが僕を呼んだ
何か珍しいものでも見つけたのだろうか
「どうしたんですか?」
「ここを、見て下さい」
そう言って、自分の足元を指差す
僕は小走りでそこまでかけつけ、ルイスさんの足元を覗き込んだ
そこには、小さな窪みがあり、その中には…
「…花、ですか」
「はい、キレイでしょう?」
「えぇ、とても……」
そう相槌をうった後、僕は食い入るようにその花を見つめた
金色の花びらは、白一色に染まったアラスカの大地によく映え、己の存在を必死で主張しているようだった
そんな姿が、一瞬だけ自分と重なる
どうしようもなく、自分がその花に惹かれていくのが分かった
「この花の名前は何というのですか?」
もっとこの花について知りたくなり、せがむように尋ねる
我ながら子どものようだと思ったが、ルイスさんは何の気がかりもないようにすぐ答えてくれた
「シンドラローズというんです」
「シンドラ、ローズ……」
無意識のうちに、花の名前を復唱していた
その言葉の響きに、不思議と安心感が込み上げる
「本当はこの花、もっと暖かくなってからしか咲かないんですよ。この時期に見れるなんて、本当に珍しい」
「この時期の花じゃ、ないんですか?」
「まぁ、春の花なんですけどね。今が春と言っても、アラスカが寒いことには変わりありませんし、この時期に咲いてもすぐに散ってしまいますから…。だから本当に、今の時期には滅多に見れない花なんですよ」
この言葉を聞いて、僕はこの花に対する「必然的な運命」を感じた最も僕は、そういう囚われた考え方を人生においてあまり持ったことはなかった
でもその時は、そう思ったのだ
出会うべくして僕は、この花と出会ったのだと思った
「……冬咲く花は、金色(コンジキ)の花…」
「え?」
「あぁ、いえ、すみません。僕の村に伝わる詩(ウタ)なんです。この花を見てたら思い出しちゃって…」
ひどくその詩に、興味がそそられた。
「あの、その詩…。教えてもらってもいいですか?」
「別に構いませんが、短い上に変わってて、あまり意味が分からない詩ですよ?」
「それでもいいです。是非、お願いします」
「分かりました…。
“冬咲く花は、金色の花
だってソイツは馬鹿だから
よほど目立ちたがるのさ
冬咲く花は、金色の花
周りを拒絶し離れさせ
孤独を味わうためなのさ
冬咲く花は、金色の花
あらん限りに輝いて
大地の太陽気取るのさ”
これでお終いです。ね、変わっているでしょう?
……って、ミチオ!?大丈夫ですか?どこか、痛いのですか?」
「いえ、大丈夫です。具合が悪いわけではないんです」
心配してくれるルイスさんをよそに、僕はただ、涙を流していた
自分の意思とは関係なく、ただ、泣いていたのだ
理由は、分かっている
感動したのだ、この詩に。
共鳴したのだ、この言葉に。
惹かれたのだ、この花に。
だから僕は、泣いたのだ
この花は、自分と同じだから
自分の存在を主張しているくせに、自ら孤独になろうとして、明るくふるまいそれを隠す。
この花と全く、僕は同じだった
「な、何をしているんですか?」
そんなことを考えた後、僕はカメラを取り出した
涙が止まったとはいえ、泣きあとが残っている状態で急にそんなことをしだしたものだから、ルイスさんは驚いたように尋ねてきた
「もちろん、この花の写真を撮るんです」
今撮らなければならないと思った
すぐに枯れてしまうこの花が、ここに、確かに咲いていたという事実を残すために。
「…分かりました。じっくり撮って下さいね」
短い溜息をついた後、ルイスさんは、優しい笑顔を向けて僕にそう言ってくれた
何故かその響きに安らぎを覚えて、僕の花に対する興奮が落ち着いていった
カメラのレンズを覗き込むと、そこには切なげな金色の花が映っている
僕は、ゆっくりとシャッターを押した
カシャリ
軽やかな音が響き渡り、僕はひどく穏やかな気分になった
それは、ルイスさんが隣で僕を静かに見守ってくれたからなのか。
あるいは、自分にとっての同士のような存在を見つけたからなのか。
それとも、全く別の理由なのか。
僕には分からないけれど、その空間は、とても居心地が良かった
まるでいつも1人で背負っていた重荷が、消えて無くなったようだ
その刹那、花びらが一枚、散った。
僕は、季節はずれに咲く、花のように……
咲いてもすぐに散る、儚い花のように……
いくら咲いても、実を結ばない
それは、徒花。
32

「孤独から芽生えるもの」
今日も寒い日だった。いつものようにアラスカを歩き回り、そろそろ日も低くなってきた。わたしはそろそろ寝る場所を探そうと、夕焼けに赤々と染まる大地の中をさまよいつづけた。すると果てしない地平線の中に一つポツンと、黒い点が見えた。
「あれはなんだろう。」私は黒い点に向かって歩いてみることにした。近づいてみるとそれが一匹のキタキツネであることがわかった。「なぜこんな所に…。」周りには何もない。ただ果てしない地平線が続いているだけだった。しかしキツネはその場所から離れようとはしない。辺りをずっと歩き続けていた。
「家族は?仲間は?」そう思った時、私はハッと息を飲んだ。キツネのその孤独な姿が、自分の歩んできた人生と重なったのだ。私は、人生の様々な場面において、孤独というものを感じてきた。大学時代、親友の突然の死、その時感じた心にポッカリと大きな穴があいたかのようなひどい孤独が脳裏を駆け巡った。そして、私巣はキタキツネのたくさんの足あとを見つめた。
「こんなにも、一人で歩いてきたんだ…」
涙が頬をつたうのを感じた。そうして私はキツネからはなれて、足あとが全て見渡される、私のこれまでの人生を全て見渡される位置に立って、カメラのシャッターを切った。
「ふう、今日もいい写真が撮れた。」
「孤独」とは、私の人生においてとても大きな意味を持った。孤独はつらいことばかりを運んできたわけではなく、様々な「出会い」を私に与えてくれた。大学時代、孤独から芽生えた「出会いたい」という感情がなければ、アラスカへ行くこともなかっただろう。
今日撮れた一枚の写真には、私の人生が集約されている。地平線をさまようキツネはきっとあの真っ赤に燃える夕日に向かって歩んでいくことだろう。私も、孤独から芽生えた希望に向かって、一歩一歩、歩みを進めている。今日もまた確実に一歩進んだはずである。
今日のキタキツネとの、偶然の出会いは、私に自分の人生を見つめるきっかけをくれた。私は、出会いを写真として形に残すことで、いつまでも変わらずそれを持っておくことができる。だからこそ私は、明日もアラスカで写真を撮る。
33

「はじまり」
かき分けてもかき分けても、木の枝が僕の行く手を阻んだ。彼らとはぐれてからどれくらいの時が経っただろうか。頭の上で真っ白に光り輝いていた太陽は、もう見えない所にまで落ちてしまった。自分がどちらに進んでいるのか分からない。このまま歩き続けて、僕はどこに辿り着くだろうか。正しい道に戻ることをすでに諦めているのかもしれない。しかし、暗くなってしまったら、そう考えると本当に怖くなった。けがをしてしまうかもしれない。熊に出会うかもしれない止まるわけにはいかないが、進み続けるのが不安でたまらない。どんな些細なものでいいから、目印がほしい。一緒に歩く仲間がほしい。心細さで壊れそうになったそのとき、前方に黄色の光がみえた。まだだいぶ先の方だったが、光をみたことが嬉しかった。枝で僕の体が傷ついていくのが分かったが、そんなことはどうでもよかった。ひたすら前を向いて、光の方へ夢中で歩いた。一刻も早く光のもとへ行き着きたかった、光は消えてしまいそうな気がしたからだ。光のもとに辿り着いたところで、元の道に戻れるわけでもないのに、何かが僕を待っていてくれる気がした。必死で歩いた結果、僕は広大な湖に着いた。太陽は既に赤い色に変わっていた。目の前に広がる景色にただただ呆然とする僕がいた。自分の存在があまりにも小さく感じだ。時を忘れ、そして自分のおかれている状況を忘れ、そこにたたずんでいた。真っ赤に染まった太陽が発する光が雲の合間からもれ、湖面を染めている。澄み切った光は湖のほとりの木々も自らうつしていた。まるで湖の底に別の世界があるかのようだった。カリブーの群れが、何一つ迷うことなく湖の中を歩いていた。僕はきっとこの光景に出会うために、森の中をさまよい続けたのだろう。迷わなければならなかったのかもしれない。この時間でなければならなかった。あの時、ひたすら足を進めてよかったと心から思った。きっと今日みたこの場面はこの先の僕の人生に、物の見方に影響をもたらすことだろう。僕の未来で、道に迷ったら、この瞬間を思い出すだろうと思った。もうすぐ太陽は完全に色を見せなくなるだろう。
また歩き始めよう。
34

「アラスカにきて」
小さい頃から、僕には家族がいなかった。物心ついたころから田舎の叔父のところに預けられていて、それとなく父・母がいない不思議さを感じていた。しかし、何一つ不自由することなく、大学にまで行かせてもらえた。ある日、東京の神田の古本屋で僕はある一冊の本を見つけた。いや、見つけたというより、その本の方から僕の目に飛び込んできた。僕は古くからの友人である、古本屋の主を呼んで、尋ねた。
「この本は、いつからここにあるんだい。」
「えーっと、20年ほど前からです。」
その本は僕と同じくらいの年齢だった。
僕は前々からアラスカに興味があり、迷わずその本を買った。
その日から僕は僕だけの家族ができた気分だった。どこに行くのも一緒だった。
僕の家族は、僕に無限の可能性をくれた。アラスカの、シシュマレフ村への旅もその可能性の一つだった。
そこでも、僕は新しい家族を見つけた。言葉の壁なんて、すこしも苦にならなかった。ただ、父・母と呼べる人がいることが嬉しかった。
僕は自分の父と母には出会えなかったが、その分、絶対に出会うことのなかったであろうアラスカの人々と出会った。それは、僕という人間をつくり、心のよりどころとなった。
二度目のアラスカへの旅。一度目は、なにもかも手探りだったが、今回は違う。言葉の壁を載りこえ、もう何もこわいものはないと思った。
しかし、ふと一人、雪しかない大地に沈む夕日を見ていると、いたたまれない気持ちになることがあった。また、僕は一人になってしまうのではないか、自分の周りの人が僕を置いていなくなってしまうのではないか。出会えた、と思えていた人々は本当は出会っていなかったのではないか。幼い頃に夕暮れの町を見つめていた時のように、胸がしめつけられる思いにかられることがあった。
そんな思いをかき消すように僕はカメラのシャッターを切りつづけた。その中に写るものを見て、僕は一人ではないと自分に言い聞かせていた。
旅の途中、日本に帰った時、僕はある人に出会った。その人は僕の心の支えとなり、僕がアラスカへ戻った時も、僕の心を支えとなってくれた。つまり、僕は運命の人と出会ったのだった。本当に、本物の、僕の家族。それは言葉では言い表せないほどのものだった。僕は彼女に一緒にアラスカに行ってくれるように頼んだ。僕の言葉に彼女は驚いたが、快く一緒に行くことを承諾してくれた。
それからのアラスカでの生活は非常にたのしかった。一人の男の子にめぐまれ、幸せな日々を送っていた。
そしてある日、アラスカの大地に立ち、遠い地平線を見つめていた。そこにふと、2匹の親ぐまと一匹の子ぐまがあらわれた。それはまるで僕ら自身を見ているようだった。僕は写真を撮りたいという衝動にかられ気がついたらシャッターを切っていた。現像しながら、僕はいままでの人生をふりかえっていた。これでよかったのだろうか。
あの時、アラスカにやってきていなかったら、どんな人生がまっていただろうか。
しかし、僕は後悔していない。今まで出会った人、出会った写真に勇気づけられてきた僕は、あの時よりひとまわりもふたまわりも成長していた。
35

「熊との出会い」
撮影日の前日、僕のもとに一本の電話があった。内容はこういうものだ。「明日の撮影を同行させてほしい。」とのこと。初めてのことに僕は驚いた。いつも撮影には一人だった。だからもちろん明日も一人だと思っていたからだ。簡単に自己紹介をし、明日あう場所と時間を伝え、電話を切った。僕は明日の為に寝ようとベッドに入ったのだが…寝れない。「緊張のせいだろうか?」「いやちがう」「じゃあなぜ?」「そんなもの知らない。」と心の中で一問一答していた。ようやくねむりについたころには…明け方であり、待ち合わせの時刻まであと2時間程度だった。そんなことも知らず、僕は夢の中へと入っていったのだ。
夢は僕が小学生の頃のことだった。ランドセルも何も持たずに学校に行って、先生に怒られている。授業中はいつも外の景色を見てたっけ。そうそう、休み時間はサッカーしてたなあ。サッカーボールが飛んできて、「あぶない」と目を閉じた瞬間…僕は現実の世界に戻ってきた。僕のの額には、流れるほどの汗であふれていた。ふと時計を見ると、約束の時間を1時間も過ぎていた。もう間に合わないだろうと思い、今日は行くのをやめようとしたが…。約束していることを思い出した。なんていう名前だったかさえ忘れてしまった僕は…昨日の記憶をたどって考えたが…思い出すことができなかった。まあ、名前が分からなくとも約束の場所に行ったら、わかるだろうと思い、僕はいそいで用意した。
約束の時間より1時間半遅れた自分がとてもなさけなかった。いつからこんなに時間にルーズになってしまったのだろうか…。そんなことを考え、待ち合わせ場所に着いた僕は、名前さえもわからない人を探さないといけないというとても困難なことをはじめようとした。
とても無防備なことだったが、しかたがなかった。そんなことを思っていた矢先に「山田」と名のる男の人が現れた。昨日の電話の主だったらしい。ゆっくり話しているひまもなく、さっそく現地へ。今日の予定は熊だった。熊がこの道を通ることは前から計算していた。動物なのだから計算通りに行くはずがないことはよくわかっている。だけど僕も何十年とカメラと共に動物を見てきた。行動や1日の生活など大体のことは頭の中にある。計算通りいけばまだこの道は通ってないはずだった。だが…時はもうすでに遅く、熊が通ったと思われる足あとがあった。僕は肩を落とし、ただただ地面をながめていた。だが山田さんはちがった。とても輝いた目で足あとを見ていた。そして遠くを見ながらこう語ったのだ。
「出会うことも出会えないことも人生なんだ。だから自然というものが存在するんだ。」と。
僕は動物に、美しい自然に出会い、今までカメラのシャッターを切ってきた。だけど、いいものに出会えなくともそれが自然であり、僕の人生だと初めてわかった瞬間だった。
もう一度熊の足あとを見つめ、僕は心にちかった。
「これからは僕の人生を写真に撮ろう」と。
そして、シャッターを押した。僕の人生を変えるであろう目の前の風景を。
36

「めぐり合い」
友達の死は突然すぎて心の整理がつかず、漠然としていた。だが、それから時は経ち、友達がいないことを実感するようになると、何事にも意欲がわかなかった。実家に戻り倉庫に「明日のジョー」があることを思いだし、取りに行った。ガラッとあけるとマンガの横にカメラを見つけた。手に取るとほこりがまった。なつかしい。そういえば私は少年の時、このカメラといっしょに世界をとびまわりたいと父によく言っていたなぁ。しかし、現実は近所に咲いているオオバコや、隣の犬しか撮れず夢をあきらめた。そうだ。意欲のわかない今だからこそこの夢をかなえてみよう。こんなにせまい日本を抜け出して広い世界へ出ていこう。この時の私は昔の夢をかなえたいという思いと暗い現実から逃げ出そうとしていたのだろう。
夢の実現のために私は日本を飛び出していろんな国へ行った。行った国はどれも自分が素直に行きたいと思った国だ。自分が行きたいところに行って撮りたいものを撮れば満足できると思っていた。しかし、撮った後にはいつも写真を撮ったことに対する達成感と撮り終わってしまったことに対するさびしさを感じるだけで満足はできなかった。なぜだろう。答えは見つからなかった行きたいと思う国もなくなってきたので日本へ帰ることにした。日本へ戻ってきてから1ヶ月がたたったある日、アルバムを部室で見つけた。それは中学時代の写真だった。おもしろい写真を見て笑いながら次のページをめくると、死んだ友達と二人で撮った写真があった。すぐにとじようとした。しかし私の心の中に「このまま逃げてていいのだろうか。」といういつもとは違う感情が芽ばえた。私はずっとその写真を見つづけて、この写真が存在していたこと、この友達が死んで今はいないということを受け入れた。
次の日友達の墓参りに一人で行った。その数日後再び日本を出て世界へ飛び立った。今回は本当に撮りたいものを見つけるために。見つかるまでシャッターを切らないと決めた。そして一年間シャッターを切らずに旅をつづけアラスカについた。たくさんの動物や人に出会った。「カシャッ」この風景に出会ったとき無意識にシャッターを切っていた。凍っていた氷がとけて水となって流れている。これは私の何かの象徴だろう。たくさんの偶然が積み重なって実現した本当の夢。そして、これからももっとたくさんの偶然と出会い、私自身が成長していくのだろう。
37

「白」
とても暑い夏の日、私は一枚の写真を見た、暑いはずなのに、その写真を見るとなぜか涼しくなる。そういう写真を撮りたくなり私は旅にでた。
外の世界は、日本と違いさまざまな動物を間近に見ることができた。でも、あの日見た写真にはおよばなかった。
「私がとりたい景色はこんなものではない…。」
私はふと空を見た。青い中にある白い雲は私を呼んでいるかのように、ゆっくりと流れているのだ。
「あっちへ行ってみるか。」
その時、私は気づきもしなかった…。軽い気持ちで進んだ道の向こうに、私のとりたい景色があるとは…。
「星野さん寒いでしょう。」
と付きそいの男が言ってジャケットを渡してくれた。
「ありがとう。」
私はジャケットを着た。それと同時に白い雪がぽつぽつと降りはじめた。見わたすかぎりの銀の世界が広がっていた。
今にも雪の結晶が降ってきそうだ。
「星野さん見てください。」
そう言って彼は遠くを指差した。
彼が指した指の先には、アイスクリームのような白い物体が横たわっていた。
「あれは何ですか」
「何でしょう」
ふと空を見た。あの時見た白い雲は、はじめからなかったように消えていた。
なぜか暑い夏の日に見た一枚の写真がよみがえる。
「私がとりたい景色はここなのか…?」
すると冷たい風が私をとりまくようにふいた。
「とりましょうよ。」
彼の一言で私はカメラのピントをあわせた。
「あっ…」
アイスクリームのような物体の正体はアザラシだった。
アザラシは黒い瞳で私を見つめていた。
レンズから私もアザラシを見つめた。
「カシャ…。」
38

「写真と家族」
星野と安部は写真を撮るために山に登っていた。少し歩いては立ち止まり、風景を写真におさめていった。
「相変わらず見事な写真ですね、星野さん。」
「私はただシャッターを押しているだけです。写真を撮るのは私の生きがいですしね。」
しばらく歩くと、看板があった。
「はぁー、だいぶ登ってきましたね。」
星野と安部はペットボトルのお茶を少し口に含んだ。
「星野さん、ここでもいい写真が撮れそうですね。」
しかし星野は返事をせず、とある方向をずっと見ていた。安部も星野が見つめている方向を向いた。そこにはヤギの群れがいた。母親と思われるヤギが一頭と、子ヤギが数頭。子ヤギたちはじゃれ合ったり母親に甘えたりしている。そんなヤギ達のようすを星野は少しさびしそうな表情で見つめていた。
「…どうかなさったんですか?」
「懐かしさを感じていてね…私にもあんな頃があったなぁ、と。」
星野はカメラを構えた。カシャッ。カシャッカシャッ。星野の指は止まることなく、ひたすらシヤッターのボタンを押し続ける。
「不思議だなぁ…。このヤギ達を見ていると幼い頃を思い出すよ。兄貴とかとよく喧嘩したり…、そのたびにいつもお袋の方に行ってたっけ…。」
カシャッ。
「親父もお袋も元気かなぁ。青二才の時に家を飛び出したっきりだからな…。」
ジー。フィルムがなくなってしまった。星野は何十枚者写真を撮っていた。星野の目からは一筋の涙が流れ出ていた。それはどのようなものからなのかは安部にもわからなかった。気がつくとヤギの親子の群れは目の前から消えていた。どこへ行ったのかと周りを見回していると、じゃれ合いながらまた出発していた。
「星野さん、私たちもそろそろ出発しましょうか。」
再びペットボトルのお茶を口に含み、出発した。頂上付近になった時、星野がゆっくりと口を開いた。
「今度、親父とお袋に会いに行こう。」
39

「視線」
寒い。
僕はそう思った。いや、しかし本当なのだ。実際寒いのだ。
しかしそんなことはおかまいなしに、僕の胸のざわめきは止まなかった。これはいったい何なのだ?初めて感じるものではない…ここ、アラスカに来てからいくどとなく感じてきた。このざわめきは何なのだ?
いろいろな思いをふり切るように僕は何回か首をふり、ほう……と息をつく。僕の口から出た白い息……それは気温が低いことを見せつけるように僕の前ですっと煙になって消えた。ああなるほど。ここは寒いのだ。僕はそれで妙に納得した。
森には入ってしばらくたつ。もう40分は歩いただろう。ここらでちょっと休憩するか、と腰をおろそうとしたとき、突然、僕の全身の血がドクンと大きく脈打ち、さわぎだした。と、同時にさっきまで感じていた胸のざわめきがいっそう強くなる。そして僕の体の中のどんちゃんさわぎはいつのまにか「写真を撮らなければ。」という衝動に変わっていた。写真を撮るに値する〃何か〃に、僕は出会いたい、と強く思った。〃何か〃に早く、早く出会いたい。
だが〃何か〃に出会うためにたま何十分も歩き回る必要はなかった。その〃何か〃は、僕の後ろに、すでに存在していた。そして僕を見つめていた。それは振り返らなくても感じることができた。〃何か〃はそれほどに強い思いを僕にぶつけてきていたのだ。僕はふり返ってその〃何か〃の思いに負けないほどの強い思いをぶつけてやるのだ、と決心してふり返る。
次の瞬間、僕は胸がしめつけられた。目が合ったのだ。体中がしばりつけられたように言うことを聞かない。さっきの決心もどこかへ行ってしまったようだ。体内ではざわめきが頂点に達している。僕は狂ったように叫びたくなった。それほどにその〃何か〃の思い、いや、想いは強かった。
〃何か〃は、ふくろうだった。一匹のふくろうだった。
そのふくろうはじっと僕を見つめ、何かを訴えている。まばたきもせずに、僕の目の奥底までも見すえようとしている。
チーッチッチッ…… どこか遠くで鳥が鳴いた。僕は我に返った。
「写真を、写真を撮らなければ。」
急いでカメラをとり出し、レンズを合わせ、ふくろうの方に向きなおった。レンズごしに目が、合う。ふくろうは、いまだに、まばたきをしない。僕はまたあのふくろうの魔力のようなものにまどわされないうちに、とシャッターを切る。
カシャー……
ふくろうはまばたきをした。僕はニヤッと微笑した。僕が勝ったと思ったのだ。今まで一度もまばたきをしなかったふくろうは、まばたきをした。僕は優越感を覚え、たて続けに何度もシャッターを切った。また、まばたきをするだろう、そう思った。そうなれば僕の勝利は確実だ。
はたしてふくろうは、………まばたきをしなかった。10回シャッターを切ったのに、一度もしなかった。
僕は焦った。ここはひとまず一時休戦だ。胸のざわめきがおしよせてくる。僕はふくろうに背を向けた。僕の背後で、フクロウは優しく笑った。
勝利のトロフィーは砕けちった。はへんが内から僕にささった。そして胸がしめつけられる。
この瞬間こそ、僕の人生なのだ。僕はふくろうに背を向けたままふくろうと同じように優しく笑った。
40

「神聖な森」
僕は昔、ある森を訪れた。写真を撮ろうと思ってやって来たが、興味をそそられる景色はない。奥へ奥へと入っていった。その時、目の前に大きな熊が現れた。僕は思わず見がまえた。熊はただじっと僕の方を見ていた。襲ってくる気配はないようだ。突然熊はひと声あげた。そしてついてこいと言うかの様に僕に背を向けて歩き始めた。一瞬あとをついていくか悩んだが、熊が僕の方を振り向いて待っていてくれているのを見てついていくことを決めた。
熊は森の奥へとどんどん進んでいく。もう僕はどこにいるのか全く分からない。熊は険しい道では立ち止まっては僕がついてこれるのかを確認している。奥に入っていくにつれて、森全体が不思議な雰囲気に包まれていた。途中でほかの動物も見かけたが、みな優しくあいさつをするようにこっちを見ていた。何匹か子どもは近付いてきた。なんておだやかな森なんだろう。その不思議な空間をぬけて熊はさらに奥へと進んでいった。
ふと気付くと熊は目の前で止まっていた。熊のいる場所には光が差し込んでいた。僕が上を見上げた瞬間、熊はひと声あげ、僕が熊のいた方を見た時にはすでに熊は消えていた。僕は走って熊が立っていた場所にいった。
カメラをかまえるのも忘れて、僕は目の前に広がる光景に見入ってしまった。誰もいないのは分かっていたはずなのに、
「だれか…。」
と叫んでしまった。風と木のざわめく音しかせず、生き物の気配が全くしなかったからだ。世界から僕以外の人たちが消えてしまったかの様だ。
僕はいそいでカメラをかまえ、シャッターを押した。それから森に一礼し、その場を去った。
僕はゆっくりと目を開いた。昔来たこの森に、今、僕は立っている。今考えてみると、本当に不思議でしょうがない。あのころは自分もまだ若く、あの神聖な空気を怖いと思ってしまった。しかし、年をとった今では、貴重な場としか思えない。できることならもう一度…。と思ってやって来たのだが、何だかもうあの美しい森には行くことができないことが私の体は分かっているのだろうか、足がもう動かないのだ。
あの場所は人生でたった一度しかいけないのだろうか…そうつぶやきながら私はあの時撮った写真を見つめた。カメラとは一瞬の風景しか撮ることができないが、私はそのシャッターを押す瞬間に命をかけ、そのためにこれからも旅をし続ける。